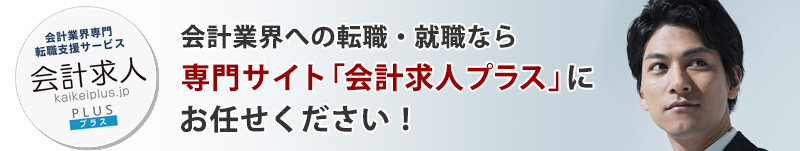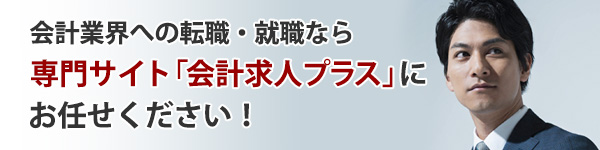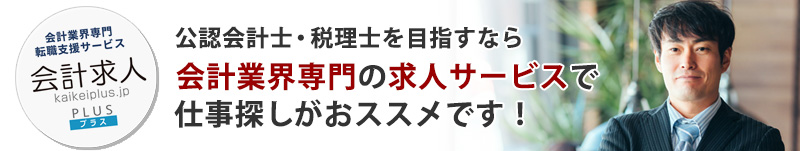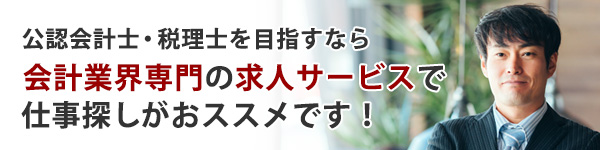公認会計士と税理士の違いを徹底解説!業務内容、資格取得の流れ、年収・働き方の特徴とは?
公認会計士と税理士は、どちらもお金に関するプロフェッショナルとして知られています。しかし、その業務内容や役割は異なり、それぞれの資格が求められる場面も違います。本記事では、両者の違いを詳しく解説し、どちらを目指すべきか迷っている方の参考になる情報をお届けします。
どちらを目指すべきか決める前に、前段階の知識として公認会計士と税理士の違いを理解しておきましょう。
■□■□会計業界へ効率的に転職活動を進めるなら専門転職サイト「会計求人プラス」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□
コンテンツ目次
公認会計士と税理士の独占業務の違い
公認会計士と税理士では、独占業務(メイン業務)が異なります。
独占業務とは、対象の資格を有する方のみが法的に行える業務のことです。他の専門家や資格者が関与することが許されていない業務範囲を指します。
公認会計士の独占業務は「財務諸表監査」と呼ばれる企業の財務状況を、第三者の立場から評価する業務です。 一方、税理士の独占業務は「税務代理」「税務相談」「税務書類の作成」の3つになります。
以下で、公認会計士と税理士の独占業務を詳しく見ていきましょう。
公認会計士の独占業務
公認会計士の独占業務は会計監査ですが、一般的には財務に関するコンサルティング業務も行います。
会計監査とは、企業の財務諸表の内容が正しいかを第三者の視点で確認する業務を指します。財務諸表は、企業の経営状況や財務状態を客観的に示す重要な書類であり、銀行融資や投資判断の際に不可欠な資料となります。
そのため、財務諸表の内容が間違っていると正しい判断が下せず、経営状況に影響をもたらす可能性があります。
公認会計士が財務諸表を確認することで、財務諸表の信頼性が保証され、銀行や投資家などの関係者が正しく判断を下せるようになるのです。
財務に関するコンサルティングでは、企業の経営戦略や財務計画の策定、コスト削減、資金調達の支援など多岐にわたるサポートをします。
税理士の独占業務
税理士の独占業務は、税務代理・税務相談・税務書類の作成の3つです。
●税務代理:企業に代わって税務署に税金の申告や不服申し立てなど行う業務
●税務相談:税金に関する疑問や悩みに対して、アドバイスをする業務
●税務書類作成:税務に必要な書類を作成する業務
監査を専門とする公認会計士に対し、税理士は税務申告や書類作成など、税務に関連する実務を企業や個人に代わって行います。企業や個人が行う税務申告は複雑で、特に年末調整や確定申告、決算書の作成に関しては、多くの企業が税理士と顧問契約を結ぶのが一般的です。
また、税務に関するコンサルティングや記帳代行、資金調達サポート、組織再編などの企業が不利益に被らないための支援も行う場合があります。
最適な求人を探すなら
「会計求人プラス」
会計求人プラスは、「会計事務所、経理専門の求人・転職サイト」です。会計業界に関連する求人のみを扱っているため、知りたい情報、希望する条件に合った求人が見つかります!
公認会計士が活躍できる求人をご紹介!
就職先・働き方・年収の違い
公認会計士と税理士では、就職先・働き方・年収の面で違いがあります。以下で見ていきましょう。
就職先・働き方の違い
公認会計士と税理士の主な就職先は、以下の通りです。
| 職種 | 就職先 |
| 公認会計士 | 監査法人 税理士法人 公認会計士事務所 コンサルティングファーム など |
| 税理士 | 税理士事務所 税理士法人 金融機関 コンサルティングファーム など |
公認会計士試験合格者の約9割は監査法人に就職するとされています(※)。監査法人では、大企業の財務監査を中心にチームで業務を行うのが一般的です。監査法人では大規模な企業の監査を扱うため、個人で完結する業務は少なくチームで業務を進めるのが一般的です。
また、大手監査法人4社の監査シェア率は、平成29年度から令和3年度まで常に70%以上を維持しており、勤務地も東京や大阪などの大都市が中心です(※)。
税理士の就職先は、主に税理士事務所や税理士法人、金融機関、コンサルティングファームなどです。2月中旬から3月中旬の確定申告の時期は繁忙期のため、残業が続く場合もあります。
将来的に独立を考えている場合は、個人経営の税理士事務所で実務経験を積んでから開業する流れが良いでしょう。
※参考: 金融庁「Ⅰ.監査業界の概観」“(2)⾦商法・会社法監査の状況等”(2024-11-01)
年収の違い
厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、公認会計士と税理士の平均年収は746万7,300円です(※1)。(平均年収は、毎月の給料と年間賞与を合算した数値です。)
国税庁が発表した令和4年の日本全体の平均給与は458万円のため、公認会計士や税理士は比較的高収入な職業に分類されます(※2)。公認会計士で大手4社の監査法人に勤務した場合は、年収が1,000万円を超える場合があります。
またハローワーク求人統計データによると、公認会計士の月額給与は40.1万円、税理士が34.6万円です(※3)(※4)。月額給与の差額は5.5万円であることから、公認会計士の方が若干高めの月収になる傾向があります。
年収は、会社規模や職位、個人が持つスキルによって異なりますが、どちらも専門職として安定した収入が期待できる職業です。
税理士の年収について、さらに詳しく知りたい場合は「税理士の平均年収の現実とは?税理士の給料を年齢別や働き方別に解説!」の記事をご覧ください。
※1 参考:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」(2024-03-27)
※2 参考:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」(2024-11-01)
※3 参考:厚生労働省「職業情報提供サイト(日本版O-NET)」”公認会計士”(2024-11-01)
※4 参考:厚生労働省「職業情報提供サイト(日本版O-NET)」”税理士”(2024-11-01)
公認会計士の年収について、さらに詳しく知りたい場合は「公認会計士の平均年収の現実とは?役職別・勤務先別の給料の違いも解説!」の記事をご覧ください。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
税理士が活躍できる求人をご紹介!
クライアントの違い
公認会計士と税理士では、クライアントにも違いがあります。
公認会計士のメインクライアントは「大手企業」
公認会計士のメインクライアントは、上場企業や大規模な会社です。例えば、最終事業年度の貸借対照表に資本金として5億円以上を計上した企業や、貸借対照表の負債額が200億円以上の株式会社が監査の対象となります(※)。
中小企業や個人経営の店や会社では、財務諸表作成の義務はないため、一般的に公認会計士が監査することはありません。
※参考:日本公認会計士協会「会社法監査」(2024-11-01).
税理士のメインクライアントは「中小企業・個人」
税理士の主なクライアントは、納税義務がある中小企業や個人です。税理士は税務全般に関わる業務を行います。そのため、企業の規模に関わらず、税務代理や申告手続きを必要とするあらゆるクライアントに対応します。
クライアントの数で比較すると、公認会計士より税理士の方が圧倒的に多いです。
最適な求人を探すなら
「会計求人プラス」
会計求人プラスは、「会計事務所、経理専門の求人・転職サイト」です。会計業界に関連する求人のみを扱っているため、知りたい情報、希望する条件に合った求人が見つかります!
税理士が活躍できる求人をご紹介!
資格取得条件の違い
公認会計士資格と税理士資格の取得には、試験合格に加えて実務経験が必要です。
試験の合格前後で補助業務などの実務経験を積んだ後、登録を行うことが条件となっています。ここでは、それぞれの資格取得条件を解説します。
公認会計士になる方法
公認会計士試験に合格しただけでは、公認会計士を名乗れません。
公認会計士の登録を受けるには、いくつか条件があります。合格制度と受験資格と併せて、資格登録要件を見ていきましょう。
| 合格制度 | 一括合格制 | 受験資格 | なし | 資格登録要件(※) | 以下3つの要件を全て満たさなければ資格登録はできない
1.公認会計士試験に合格している |
公認会計士になるためには、試験に合格した後、監査法人や企業で3年以上の実務経験を積み、さらに実務補習および修了考査を修了する必要があります。
公認会計士になる方法は、以下の記事で詳しく紹介しています。
公認会計士の就職先とキャリアプラン!合格から就職までの流れも解説
※参考:金融庁「公認会計士の資格取得に関するQ&A」(2024-04-03).
税理士になる方法
公認会計士と同じく、税理士も合格後に2年の会計実務を経験しなければなりません。以下で、合格制度と受験資格、資格登録要件を見ていきましょう。
| 合格制度 | 科目合格制 |
| 受験資格 | 会計科目のみの受験:なし 税法に属する科目を含む受験:国税庁が指定する学識・資格・職歴のいずれか一つの要件を満たす必要がある |
| 資格登録要件(※1) | 1.税理士試験に合格した者 2.税理士法に基づいて、試験科目の免除を受けた者 3.弁護士 4.公認会計士 うち1と2に該当する者は、会計の実務経験が2年以上あることを要件とする |
うち1と2に該当する者は、会計の実務経験が2年以上あることを要件とする
税理士になるには、試験の合格前後に関わらず会計関係の実務に2年間以上従事した後、税理士登録を受ける必要があります。ただし、弁護士や公認会計士の登録が済んでいる場合は、税理士試験が免除されます。なお、2017年4月1日以降に公認会計士になった方が登録を受ける際は、所定の研修を受講しなければなりません(※2)。
税理士になる方法は、以下の記事で詳しく紹介していますのでチェックしてみてください。
税理士になるには?受験資格から登録までの道のりを徹底解説
※1 参考:国税庁「税理士の登録」(2024-11-01)
※2 参考:日本公認会計士協会「国税審議会における実務補習の指定について(官報掲載のお知らせ)」(2024-11-07)
試験内容の違い
公認会計士と税理士では、試験内容が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。
公認会計士の試験内容
公認会計士試験では、幅広い会計知識と分析能力が問われます。具体的に実施するのは、4科目の短答式試験・5科目の論文式試験です(※1)。
始めに行う短答式試験では、以下の4科目に合格する必要があります。
●財務会計論
●管理会計論
●監査論
●企業法
上記4科目の短答式試験は、公認会計士・監査審査会が適当と認めた得点比率(総点数の70%を基準)が合格ラインです。1科目でも得点が40%に満たない場合、不合格となる可能性があります(※2)。
短答試験合格後は、以下の5科目の論文式試験を実施します。5科目のうち4つは必須科目、残り1つは選択科目です。
【必須科目】
●会計学
●監査論
●企業法
●租税法
【選択科目(1科目を選択)】
●経営学
●経済学
●民法・統計学
論文式試験の合格基準は、総点数の60%を基準として公認会計士・監査審査会が適当と認めた得点比率とされています。短答試験と同じく、1科目でも得点が40%に満たない場合、不合格となる可能性があります。科目合格制度はありますが、有効期限は2年です(※2)。
公認会計士は一度に複数科目を受験しなければならないため、幅広い分野でバランス良く進めていく必要があります。
※1 参考:公認会計士・監査審査会「目指せ、公認会計士!-公認会計士試験にチャレンジしてみませんか-」(2024-11-01)
※2 参考:金融庁「合格基準について」(2024-11-01)
税理士の試験内容
税理士試験の科目は、全11科目で構成される会計学と税法に分かれています。この中で、必須科目、選択必須科目、選択科目があり、受験者はこれらから合格を目指す科目を選びます(※)。
【必須科目】会計学に関する科目
●簿記論
●財務諸表論
【選択必須科目】税法に関する科目(※以下のどちらかの選択が必須)
●所得税法
●法人税法
【選択科目】税法に関する科目(以下の中から1~2科目選択)
●相続税法
●消費税法または酒税法(併願不可)
●国税徴収法
●住民税または事業税(併願不可)
●固定資産税
期限なしの科目合格制度を取っており、合格点は各科目満点の60%以上です。ただし、配点が公表されているわけではなく、合格率は10〜15%を推移しているため、実質競争試験となります。
公認会計士試験と税理士試験の違いについては、以下の記事に詳しく紹介しています。
公認会計士試験の難易度を徹底解説!税理士試験との違いや合格率、必要な勉強時間とは?
※参考:国税庁「税理士試験の概要」(2024-11-01)
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
税理士が活躍できる求人をご紹介!
公認会計士と税理士、どちらを選ぶべきか迷ったら
公認会計士も税理士も、難関の国家資格であり、合格率の低さが共通しています。どちらの資格を目指すべきか迷っている方に向けて、判断基準となるポイントをお伝えします。
●向いているかどうかで選ぶ
●受験環境で選ぶ
●携わりたい業務で選ぶ
向いているかどうかで選ぶ
ご自分の性格や価値観に照らし合わせて、どちらに向いているかを考えてみましょう。
公認会計士に向いている方
公認会計士は、客観的な視点で法令や基準に基づいて判断し、適切な指摘ができる責任感の強い方に向いています。監査業務は、主観的な考えではなく、法令に基づいて財務諸表を公正公平に確認しなければなりません。そのため、一定の厳格さをもって業務に臨める方が向いています。
公認会計士が活躍できる求人をご紹介!
また、大企業の担当者と直接話す機会が多いため、チームで仕事するのが好きな方やコミュニケーション能力が高い方も向いている職業です。
税理士に向いている方
税理士は、企業の成長をより近い立場でサポートしたいと考えている方に向いています。
税理士のクライアントは主に中小企業や個人のため、企業に寄り添いながら相手目線で考える能力が求められます。普段から他人との会話に積極的で、他人のために動ける方にとって税理士はおすすめの選択肢の一つです。
また、情報を自分から吸収しようとする方にも向いています。税理士は、最新の法改正に基づいてクライアントにお金に関するアドバイスをしなければなりません。常に知識を吸収し、学ぼうとする方は税理士業務に楽しさを見出せるでしょう。
受験環境で選ぶ
受験環境で選ぶのも一つの方法です。
公認会計士の試験合格に必要な学習時間は、2,500〜4,000時間程度と言われています。1年半~2年ほどの短期の勉強期間を経て合格するスタイルのため、勉強が好きで継続して試験勉強に取り組める方におすすめです。
また、公認会計士試験は一度で複数科目を受験しなければなりません。そのため、公認会計士試験は、特に学生や学業に専念できる方に適しており、短期間で集中した学習が求められる難易度の高い試験です。
一方で税理士の試験合格に必要な時間は、2,000〜5,000時間程度です。学習期間も3~5年と長期にわたり科目別合格制度もあるため、働きながら資格取得したい方や、ご自分のペースでゆっくり試験に臨みたい方は、税理士の取得が適しています。
また、独立して個人で税理士事務所を開きたい方も税理士取得を目指すのがおすすめです。
携わりたい業務で選ぶ
携わりたい業務に必要な知識は何か考え、どちらかを選択する方法もあります。
すでに説明したように、公認会計士資格を取得した方は、所定の条件をクリアすれば税理士登録も受けることが可能になるので、公認会計士になってから税理士登録をする方が効率的だと捉える方も多いでしょう。しかし、必ずしもそれが将来のキャリア形成にとって有利になるとは限りません。
なぜなら、公認会計士として独立を目指すとしても、税理士の専門知識が求められる場面があるからです。特に、財務諸表の監査業務では税法や税務知識が不可欠であり、税理士の知識が強みとなるケースがあります。
そのため、今後、税務業務を中心にしたいと考えている場合は、一概に公認会計士から始めるのが近道とは言い切れず、税理士試験の勉強を進める方が将来的に役立つ可能性があります。
自分がどちらの業務に携わりたいかを考え、将来のキャリア形成に役立つ方を選びましょう。
公認会計士と税理士は、業務内容や収入、働き方などで違いがある
公認会計士は、企業の財務情報の透明性と信頼性を保証し、経済社会の健全な発展に寄与する専門職です。一方、税理士は個人や企業の税務相談や申告業務に携わります。対象のクライアントや役割、試験内容が異なるため、ご自分の性格やキャリアプランを考えた上でどちらの資格を目指すか決定しましょう。
会計業界への転職を考えている場合は、会計業界に特化した転職サイト「会計求人プラス」をご活用ください。資格取得後の新たなキャリアを考える方に、会計事務所や税理士事務所などの求人情報をお届けします。
これまでの税理士・公認会計士のキャリアを生かしたい方も、ぜひご相談ください。転職に関する不安や悩みを専門のエージェントに相談しながら、効率良く転職活動を進めていきましょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
税理士が活躍できる求人をご紹介!
投稿者情報

-
会計事務所や税理士事務所、一般企業の経理職など会計業界の求人情報が豊富な「会計求人プラス」を運営し、多くの求職者の方、会計事務所の採用ご担当者とお話をさせていただいています転職エージェントです。
異業種から会計業界へ転職を希望している方をはじめ、これから税理士や公認会計士を目指す未経験の方や、今までの税務・会計の知識・経験を活かして年収アップやスキルアップしたい方などを全力で支援しています。
その一環として、会計業界でお役に立つ情報をお届けするために10年以上記事を書いています。是非、会計業界で働く人が楽しく、知識を得られるような情報をお伝えできればと思います。
最新の投稿
 転職ハウツー2026.01.20会計事務所は未経験でも目指せる?仕事内容・資格・年齢別の成功ポイントとは
転職ハウツー2026.01.20会計事務所は未経験でも目指せる?仕事内容・資格・年齢別の成功ポイントとは 公認会計士2026.01.19もう限界…監査法人を辞めたい人が知っておくべき転職戦略と準備のすべて
公認会計士2026.01.19もう限界…監査法人を辞めたい人が知っておくべき転職戦略と準備のすべて 経理2026.01.19経理にMOS資格は必要?現場の声と転職成功の秘訣を紹介
経理2026.01.19経理にMOS資格は必要?現場の声と転職成功の秘訣を紹介 成功者インタビュー2025.12.11朝日税理士法人 城南支社 成功者インタビュー 2025年度
成功者インタビュー2025.12.11朝日税理士法人 城南支社 成功者インタビュー 2025年度