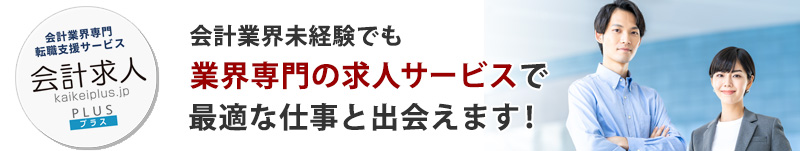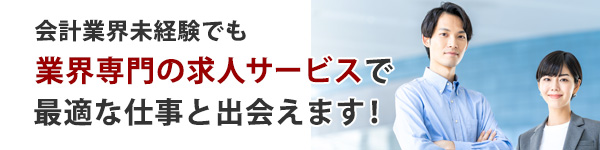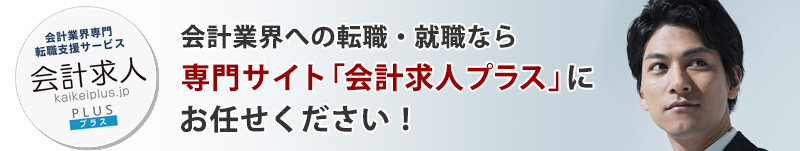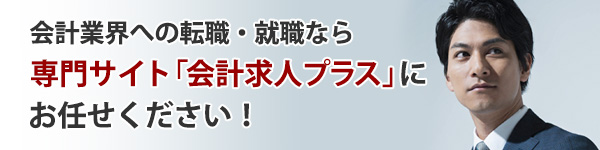税理士の平均年収の現実とは?税理士の給料を年齢別や働き方別に解説!
2025/06/26
税理士資格を取得するためには、まず国家試験の中でも最難関とされるほど難易度の高い税理士試験で5科目合格しなければなりません。科目制度を活用して何年もかけて5科目合格した上で、実務経験も積まなくては税理士登録できないことから、高年収を期待して、税理士を目指す人も多いと思います。
しかし、税理士の働き方にはさまざまな種類があるため、雇われ税理士として勤務しているのか、独立開業しているか、勤めている会社の規模や勤務地によっても年収や給料が異なるのはご存知でしょうか?
また、税理士が独立開業した場合は年収1000万円を軽く超えて、年収3000万円といった高年収が狙える可能性がある反面、独立開業には様々なリスクがあることにも注意が必要です。
実際に会計事務所の勤務税理士として働くためのポイントや、税理士が高年収を勝ち取るためのコツなど、知っておきたいですよね。
今回は、税理士の平均年収は本当に高いのか、会計業界での経験豊富な会計求人プラスの転職エージェントで多くの求職者の相談を受けているキャリアコンサルタントからのリアルなコメントも交えて詳しく解説していきます!
税理士資格を取得していることが貴重な20代からまだ若手といわれる30代、40代さらには、税理士登録者の50%を超える50代以降の給与や、勤務税理士や開業税理士など働きた方別でも紹介します。
■□■□会計業界へ効率的に無駄のない転職活動をするなら専門転職サイト「会計求人プラス」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□

学生時代に取得した日商簿記の資格を活かすため、卒業後は経理職に従事し会計業界に携わりました。
2014年より会計求人プラスの営業として会計業界での転職サポート業務の経験を積み重ねて、現在はキャリアコンサルタントとしてもトップの成績を更新しています。多くの会計事務所様、一般企業様からのご要望により人材紹介事業もスタート。転職エージェントとして、日々多くの求職者と、会計事務所の最適な出会いとなるよう奮闘しています。
コンテンツ目次
税理士の平均年収(厚生労働省発表)
厚生労働省が発表した「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、公認会計士を含む税理士の平均年収は約780万円と報告されています。(※1)同年の一般労働者の平均年収と比較すると2倍近い額になり、高水準といえます。
この結果は、企業規模が10人以上の事務所に勤めている勤務税理士の場合なので、事務所の規模や立場によって違いが出るでしょう。会計事務所の場合は10名以下の事務所が大半を占めますので、給与水準はもう少し下回るものと思われます。
※1 引用元:厚生労働省 政府統計の総合窓口e-Stat「賃金構造基本統計調査」
会計業界へ転職したいなら
「会計求人プラス」
未経験でも会計事務所で働くことは可能です。簿記資格を持っている、税理士を目指している・目指したことがあるなど、あなたの知識を活かせる職場をお探しします!
税理士と他士業の国家資格の年収を比較
税理士と同じく、高年収が期待できる職種として、医師や弁護士が挙げられます。税理士と同様に企業規模が10人以上の法人という条件をもとに厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、医師の平均年収額は約1,436.5万円です。(※2)
一方、弁護士は約1,122万円で、税理士の方が平均年収は低い印象を受けます。しかし、国税庁の「民間給与実態統計調査」において、一般事業会社などの会社員の平均年収は約461万円と発表されていることから、国家資格を必要とする士業の給与水準はかなり高額だといえます。
※2 引用元:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※3 引用元:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」
税理士が活躍できる求人をご紹介!
税理士の年齢別平均年収はどれくらい?

税理士の年収は、年代によって異なります。更には、男女別でも年収に差が出るというデータがあります。また、経験年数、キャリアやスキルも、収入に大きく影響してくるため、ある程度の勤続年数がある人の方が、高年収を得やすいでしょう。続いては、年代別の平均年収の目安を紹介します。(※2)
貴重な若手20代税理士の平均的な年収
20代の平均年収は約462万円といわれています。20代の前半(20歳~24歳)の平均年収は約428万円で、後半(25歳~29歳)になると約495万円にアップしています。一般企業に勤める20代全体の平均年収が300万円前後ですので、年収にも恵まれている環境だといえますが、これには理由があります。
税理士試験合格に必要な勉強時間は3000時間や5000時間という膨大な学習時間を必要とします。そのため、20代で合格するのはかなり困難で20代税理士の割合は全体の1%未満という低い数字にすぎません。需要に対して20代税理士の供給が極端に少ないため、年収も恵まれているというわけです。
大半の方は科目制度を活用して、複数年かけて5科目合格を目指しますから、税理士事務所などに就職し税理士補助の仕事などをしながら、残りの科目の合格を目指すことになりますが年収は低めです。つまり、科目合格者として下積みの期間も税理士のキャリアに含めるのであれば、収入面においては必ずしも始めから恵まれているとはいえないのです。
2023年より受験資格などが大きく緩和されて、年齢が若い段階から税理士試験に挑めるようになりました。高齢化が進んでいる税理士業界の若年化が進む兆しが見えるということは明るいニュースと言えます。
まだまだ若手30代税理士の平均的な年収
30代税理士の平均的な年収は約626万円になります。30代前半の税理士は約581万円で、後半になると約671万円まで年収が上がります。
勤務税理士のスタートである350万円代より大幅にアップしますが、人によってはそれほどもらっているとは感じないかもしれません。先ほど述べたように、税理士の資格試験が難関で、勉強を始めてから資格を得るまで平均5年以上とも、8年以上ともいわれているので、30代になって、ようやく正式な税理士として活躍しはじめる時期になるからです。
ですので、30代の税理士は、まだまだ若手と見られているのです。そのため、税理士の転職市場では30代から40代が活発に動いています。一般的なサラリーマンであれば、35歳以上は転職が厳しくなってくるといわれることがありますが、税理士に関しては、資格も取得し、経験を積んだ30代からキャリアップの転職を考えるケースも多いのです。
30代中頃で独立するケースもありますが少数で、ほとんどはキャリアを積んで少しずつ年収を上げながら、独立後も顧客として付き合ってもらえる関係づくりが中心になります。そのため20代と比べて大幅に年収は上がらず、キャリアを積んで自信をつけはじめた40代になってから独立開業を果たして一気に年収を上げていくケースが多いようです。
活躍する世代40代税理士の平均的な年収
40代の税理士の平均年収は約1,041万円といわれています。40代前半の税理士の年収は約745万円で、後半の年収は約770万円です。40代になると税理士として実務経験をこなし、組織をまとめるマネージャーや役職者になっているケースも少なくありません。そういった役職者の場合、年収1,000万円を超えることも珍しくありません。また、税理士法人などでの勤務時代に培った経験や人脈を生かして独立開業する人が多いのもこの40代後半の年代といえます。
実際には、30代と比較しても平均年収はそれほど変わっていないのが特徴です。30代から税理士としての経験を積んでいる最中であったり、40代後半に独立開業してまだ軌道に乗っていない状況だったりすることが要因としては考えられます。
このことからも税理士は40代でも若手と見られることが多く、定年の無い税理士は高年齢化が進み後継者も育ちにくいという状況に陥っています。

経験豊富な50代税理士の平均的な年収
50代の税理士の平均年収は約957万円といわれています。50代前半の税理士の年収は約853万円で、後半の年収は約1,061万円と50代は平均年収の上下があまりないことがわかります。50代になると税理士として独立開業をして税理士事務所の経営も安定してきており年収も上げやすい状況の方が多いことが伺えます。違う視点から見れば、税理士が独立開業をした場合、税理士が50代になっても残っている会計事務所は業績を伸ばせた事務所であることがわかります。開業して順調に顧問先も増えて経営できている状況であることから、年収15000万円を超えることも珍しくありません。

多くの知識を有した60代以降の税理士の平均的な年収
60代以降のシニアスタッフとも呼ばれる世代になり、年収は下がっていく傾向となります。65歳以上になると基本的には引退される税理士が多くなりますが、一般企業に勤めている勤務税理士ではない限り、税理士に定年はありませんので65歳を過ぎても一線で活躍されている方も多いのです。
税理士の高齢化が進んでいる背景には、若手税理士が減少傾向にあり、後継者が育たないとうことも影響しています。近年では税理士試験の受験者が増加傾向にありますので、税理士業界の傾向が良い方向に変化していくことが期待されます。
税理士が活躍できる求人をご紹介!
税理士試験の合格科目によって年収が変わる?
税理士試験の科目合格制度とは、税理士試験の全11科目のうち、5科目に合格すれば資格が得られる制度です。各科目は一度合格すれば次年度以降も有効となります。つまり1年目で2科目合格すれば、次年度以降に3科目合格すれば5科目合格となります。
試験範囲が膨大なため一度で5科目合格することは難しく、大半の人は1科目づつ受験し、5科目合格して税理士登録するまでには何年かかるのが通常です。
そのため、いくつか科目合格した状態で、社会人として税理士事務所で働きながら残った科目の合格を目指します。
一般的に税理士の年収は合格科目の数によって異なります。科目合格者に対して資格手当を支給するケースも多く、1科目ごとに上乗せされるため、複数科目合格している人の方が年収アップしやすくなります。
科目合格者であれば、一定の評価をしてくれる事務所も多いので、5科目合格を目指し実務経験を積みながら勉強を進めるという人も多いのです。
会計業界へ転職したいなら
「会計求人プラス」
未経験でも会計事務所で働くことは可能です。簿記資格を持っている、税理士を目指している・目指したことがあるなど、あなたの知識を活かせる職場をお探しします!
合格科目者の年収の違いについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
年収と税理士試験での科目合格数は関連あるのか?
税理士は働き方によって年収が変わるの?
税理士の資格取得後は、税理士事務所、税理士法人に就職するのが一般的です。
中には独立開業を目指す人もいますが、取得後すぐはハードルが高く、まずは経験値を上げるために一旦、会計事務所に就職する人が多いでしょう。事務所の規模はさまざまで勤務先によって年収も異なります。職務経験や実績を積んでからでしたら独立開業を検討することをおすすめします。
社員として勤めることは、安定した環境を得やすいというだけではなく、キャリアアップのための転職がしやすいということもメリットの1つでしょう。
税理士の年収が働き方によってどのように変わってくるのかを解説します。
会計事務所(税理士事務所、税理士法人など)の平均年収
一般的な会計事務所に勤務税理士として所属している場合、平均年収は約300~600万円程度といわれています。もちろん、年代やキャリアによっても年収が異なりますが、税理士は年代が上がると年収も比例して上がる傾向です。より専門性が深まると給料も高くなると考えられます。
その中でも、世界的に実績を持つ大手税理士法人がいわゆる「BIG4税理士法人」です。BIG4税理士法人とは「PwC税理士法人」「KPMG税理士法人」「EY税理士法人」「デロイト トーマツ税理士法人」の4つを指します。BIG4税理士法人は大企業向けの税務や特殊税務、国際税務などを請け負っており、年収も高額でBIG4税理士法人の給与額(年収)は、約600~1200万円程度といわれています。
BIG4に勤めることは1つのステータスとしても捉えられていたり、BIG4が世界規模のコンサルティングファームとしても有名であることからキャリアアップを図る上でも目指している人が多い企業になります。
BIG4税理士法人では役職によって年収が大きく違います。一般的な税理士の役職としてはスタッフ、シニアスタッフ、マネージャー、シニアマネージャー、ディレクター、パートナーの6つがあります。スタッフとパートナーでは3倍以上の年収の開きがあるケースもあります。
企業内税理士の年収
一般企業に就職して、財務や税務に関する業務を行う人を企業内税理士と呼びます。経理に関わる仕事が一般的ですが、金融機関で働く場合は経理だけではなく財産評価といった税務業務も手がけるケースが多いでしょう。
また、一般企業に勤務税理士は管理職として部門のマネジメントに携わったり、CFOという立場に立ったりすることで、年収が上がる可能性が高いでしょう。
企業内税理士の年収は、企業によって異なるため一概にはいえません。例えば大手企業で業績がよければ、高い年収をもらえる可能性があります。一方で、中小企業に就職した場合は、一般的な税理士の年収以下というケースもあるでしょう。しかし、最低年収でも約500万円以上といわれており、さらに国際税務等のスキルや経験があれば、約600万円以上の年収が期待できます。
独立開業した税理士の平均年収
経験を積んだ税理士は、独立開業を選択する人も少なくありません。一般的に独立開業した場合は、平均年収が3000万円程度といわれています。
勤務税理士と独立開業税理士を比較すると、独立開業した方が年収が増える可能性も高まります。
現在、減少傾向だった税理士試験受験者数は2023年度には増加傾向に転じており、税理士を目指している人も増えていると考えられます。
それに対してクライアントとなる企業数が減少傾向にあるため、競争が激化すると言われていますが、いろいろな見解もあり、フリーランスなどの個人事業主が増加傾向にあることから、現在は顧客数は増えているという意見もあります。
また将来的にはAIの発展に伴い、より付加価値の高いサービスが求められるでしょう。こうした背景を踏まえると、単に独立開業したからといって高年収が得られるとは限りません。

独立開業はハイリスク・ハイリターン?
税理士として独立開業するとなれば、ゼロからのスタートです。顧客獲得に関しても、戦略を立てる必要があります。無計画に独立しても仕事が得られずリスクだけが増え、税理士事務所経営はうまくいかずハイリターンは望めないでしょう。また戦略を立てたとしても実現できる営業力も持ち合わせてないと必ず顧問先が獲得できるとは限らず、高収入といったリターンだけを求めるために独立するのはリスクが高いでしょう。
独立開業を想定していらっしゃるのであれば、ポイントをしっかりとおさえ、準備をしてから進めることが成功の秘訣といえるでしょう。
税理士として経験を積んだからと言って、安易に独立開業しようとするのはおすすめできません。
税理士が独立開業するためにどのような準備が必要なのか、詳しくはこちらをご覧ください。
税理士が独立開業するにはどのような準備や費用が必要か徹底解説!
税理士の将来性については、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
税理士に将来性はあるのか?これからの税理士のあり方とは
税理士は今後も高年収を持続できるの?

近年は、AIやRPAが普及しており、簿記の入力や仕分けは、人の手をほとんど使わずに済むようになりました。記帳までは社内で行えるケースが多く、記帳代行の需要は減少傾向にあります。そのため作業量が減り、顧問料も安くなりつつあります。
ChatGPTなど生成AIの急速な進化にも驚きますが、AIの進化により税理士の仕事なくなるとも言われています。実際には、AIが不得意な仕事は残るはずですが、作業として処理できる業務はAIで賄えるような時代になりつつあります。(※6)
また、日本の中小企業数は年々減少傾向にあります。(※5)税理士にとって中小企業は最も多い客層です。取引先が減っているため税理士事務所の収入の低下も起こり得ます。しかし、個人事業主やフリーランスとして独立して働く人は急増しており、その層を専門とする税理士も増えています。
税理士は企業のパートナーとして経営者の意向を汲み取ったコンサルティングも仕事の1つです。コンサルティングはAIが不得意なので、今後も需要が伸びると考えられます。
※5 引用元:中小企業庁「令和5年度(2023年度)の中小企業の動向」
※6 引用元:Michael A. Osborne「The Future Of Employment(雇用の未来)」
年収アップ、必要とされる税理士になるには
税理士として収入アップを望み、必要とされる税理士になるためには、キャリアアップ転職するのも1つの方法です。BIG4税理士法人や年収が高い税理士事務所に転職できれば、スキルアップにもつながるでしょう。
また、より専門的な分野のキャリアに磨きをかけていくのも大切です。例えば、法人や個人の税金申告が得意または、相続や事業承継、税務調査対応が得意など、得意分野や強みがある方が、クライアントから必要とされる可能性が高まります。また、最近は業種特化型の税理士も増えており、特定の業種知識を身に着けスキルアップするのも良いでしょう。
近年では、フリーランスや個人事業主が急増しているため、対象や仕事も増えており人手不足となっている事務所も急増しています。

税理士が活躍できる求人をご紹介!
平均年収を把握して効率的な転職活動を進めましょう
平均年収というのはあくまでも対象をならした平均値であり、目安の金額であることを理解しておくことが大切です。
中央値でみれば平均年収との乖離がある可能性もありますし、実態調査報告書のデータは税理士だけではなく公認会計士も含まれていますので「平均年収」を鵜呑みにしないように注意が必要です。しかし、裏を返せば勤務税理士として雇われていたとしても年収3000万円という人もいるのですから、高年収を目指すことも不可能ではありません。
また、男性、女性といった性別や、北海道から沖縄まで各地域によっても年収に差があります。そのような現実を踏まえて計算されているのが、賃金構造基本統計調査で公開されている税理士の平均年収なのです。
年収を上げていくためにはどのようなスキルが必要か、どのような経験を積むことが必要なのかを自分自身で分析し、高年収を勝ち取ってください。
もし、現在の職場の年収に満足されていない、違う業務やスキルを身につけてキャリアアップを図りたいということなら、転職という選択も1つの方法です。
税理士専門の会計求人プラスで最適な転職活動をしよう
会計業界専門の転職支援サービス「会計求人プラス」であれば貴方の経験や職務歴、スキルから想定年収も試算してくれて、現在の待遇を超える非公開求人情報を紹介してもらうことも可能です。
希望の条件が明確になっていて、検索条件の設定に迷わないという方であれば、会計求人プラスの求人サイトをご利用いただくと、希望条件にマッチした求人を検索することも可能です。
転職の目的や条件明確であるなら、求人サイトで転職活動を進めるのが最適だと思います。
もし、応募書類の作成で悩んでいたり、忙しくて転職活動に時間を割けない、初めてで不安があるなどの場合は、会計求人プラスの転職エージェントをご利用ください。キャリアアドバイザーが面接対策もしてくれて、履歴書や経歴書の魅力的な書き方や、添削まで対応してくれますし、貴方の希望をお伺いして最適な非公開求人を紹介してくれます。面接などで聞きづらい質問や、給与交渉なども代行してくれたりしますので、効率的に転職活動をすすめることが可能です。
あなたに最適な転職先を効率的に探すお手伝いを完全無料でご利用いただける会計求人プラスが求人サイトと転職エージェントの2つのサービスで実現します。
最適な求人を探すなら
「会計求人プラス」
会計求人プラスは、「会計事務所、経理専門の求人・転職サイト」です。会計業界に関連する求人のみを扱っているため、知りたい情報、希望する条件に合った求人が見つかります!
また、公認会計士の平均年収について、更に詳しく知りたい場合は「公認会計士の年収はどれくらい?年代別・勤務先別の収入の違いなど徹底解説!」の記事をご覧ください。
税理士が活躍できる求人をご紹介!
投稿者情報

- 現役の税理士として10年以上、会計事務所に勤務しているかたわら、会計・税務・事業承継・転職活動などの記事を得意として執筆活動を5年以上しています。実体験をもとにしたリアルな記事を執筆することで、皆さんに親近感をもって読んでいただけるように心がけています。
最新の投稿
 税理士2025.06.29独学で税理士試験合格はできる?合格を勝ち取るポイントを解説
税理士2025.06.29独学で税理士試験合格はできる?合格を勝ち取るポイントを解説 税理士2025.06.22税理士の平均年収の現実とは?税理士の給料を年齢別や働き方別に解説!
税理士2025.06.22税理士の平均年収の現実とは?税理士の給料を年齢別や働き方別に解説! 税理士の仕事2025.05.29税理士の独立開業は厳しい?業界事情や開業に失敗する原因、成功のポイントをご紹介
税理士の仕事2025.05.29税理士の独立開業は厳しい?業界事情や開業に失敗する原因、成功のポイントをご紹介 税理士試験2025.05.21実務経験なしから税理士になるには?税理士登録に必要な要件や経験を積める場所を解説
税理士試験2025.05.21実務経験なしから税理士になるには?税理士登録に必要な要件や経験を積める場所を解説