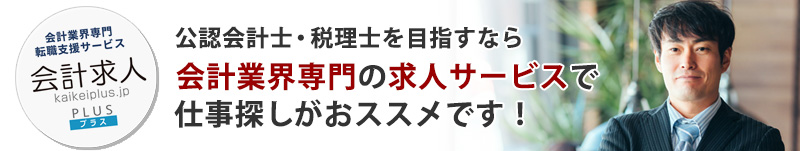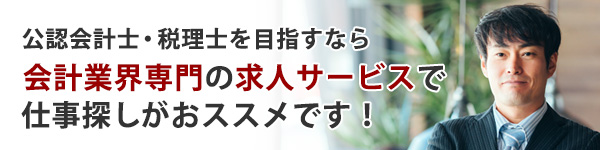公認会計士試験の難易度を徹底解説!税理士試験との違いや合格率、必要な勉強時間とは?
2024/10/22
一般的に公認会計士のような国家資格を取得して仕事をしたいと考えるときは、仕事の内容だけでなく、試験の難易度を判断基準の一つにする人も多いのではないでしょうか。
公認会計士は医師や弁護士、司法書士などと同様の士業となる資格で三大国家資格とも言われており、取得できれば将来独立開業して大幅な年収アップも可能になってきます。
なんといっても資格を持っている人のみが対応できる独占業務がありますから資格を有していないとできない業務があることが強みと言えます。
公認会計士試験と税理士試験、司法試験や司法書士試験はいずれも国家試験のなかでも超難関と言われるほど難易度が高い資格ですが、その内容には大きな違いがあります。
そのため、どの資格を目指すのかは、難易度だけではなく、それぞれの特徴を理解して決めたほうが良いでしょう。
また、いずれも合格まで数千時間という長い時間の勉強が必要となりますので、事前の情報収集をしっかり行い、スケジュールを立ててモチベーションをたもちながら受験することがとても大事です。
この記事では、公認会計士試験の難易度を中心に難易度や学習時間・学習範囲、試験の仕組みについて税理士試験と比較しながら解説しますので、ぜひ資格取得のご参考にしてください。
今回は、公認会計士と税理士の難易度の違いについて、会計業界での経験豊富な転職エージェントが徹底解説していきます!
■□■□会計業界へ効率的に無駄のない転職活動をするなら専門転職サイト「会計求人プラス」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□

学生時代に勉強していた日商簿記の資格を活かすため、卒業後は経理職に従事し会計業界での経験を積む。
2014年より会計求人プラスの営業として会計業界での人材支援事業の経験を重ねてきました。
多くの会計事務所様のご要望から人材紹介事業もスタート。キャリアアドバイザーとして、日々多くの求職者と、会計事務所の架け橋となるよう奮闘しています。
求職者の皆さん、会計事務所様多くの方から信頼を頂いている会計業界専門の転職エージェントとして好評をいただいています。
コンテンツ目次
公認会計士試験と税理士試験の難易度の違いとは
公認会計士試験と税理士試験の難易度の違いを一言で表すなら、
- 「質」の難易度が高いのが公認会計士試験
- 「量」の難易度が高いのが税理士試験
と言えます。
どちらも会計学系の資格としては最難関、最高峰な資格と言われていますが、試験制度や試験の性質は大きく異なります。
その中でも、重要視しなくてはならないのは難易度の性質です。
試験制度やそれぞれの業務内容を事前に調べているだけでは分からない部分があります。
これからどちらを目指そうかと検討されている方は、本記事を読んで頂き比較検討するためのご参考にしていただければと思います。
税理士が活躍できる求人をご紹介!
公認会計士試験の難易度を数字で分析
世間では公認会計士試験は難しいと言われていますが、具体的な内容を知らない人は少なくありません。
公認会計士資格の難易度を、合格率や合格するために必要な勉強時間、合格までに必要な年数などをもとに見ていきましょう。
合格率は10%前後
公認会計士試験の平均合格率は、短答式が10%台前半、論文式が30%台半ばで推移しており、全体の合格率は10%前後です。
過去5年間の合格率は、以下のとおりです。ここでの合格率は、公認会計士試験合格者数を出願者数で割った数値を指します。
| 年度 | 出願者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和元年(2019年) | 12,532人 | 1,337人 | 10.70% |
| 令和2年(2020年) | 13,231人 | 1,335人 | 10.10% |
| 令和3年(2021年) | 14,192人 | 1,360人 | 9.60% |
| 令和4年(2022年) | 18,789人 | 1,456人 | 7.70% |
| 令和5年(2023年) | 20,317人 | 1,554人 | 7.60% |
近年の公認会計士試験の合格率は、10%前後で安定しています。
受験者数が過去5年で最多となっており、今後に期待が持てます。
突然大きく変動した年も過去にはありましたが、基本的には10%程度の水準でこれからも推移していくと考えられます。
合格に必要とされる勉強時間は約5,000時間
公認会計士試験に合格するために必要とされる勉強時間は、5,000時間程度と言われています。
5,000時間を短答式試験と論文試験のそれぞれの科目に割り振り、効率的に勉強を進めていかなければなりません。短答式試験と論文試験の科目別必要勉強時間は、以下のとおりです。
短答式試験科目別の必要勉強時間
| 科目名 | 必要勉強時間 |
|---|---|
| 財務会計論(計算) | 600時間 |
| 財務会計論(理論) | 300時間 |
| 管理会計論 | 400時間 |
| 監査論 | 200時間 |
| 企業法 | 300時間 |
論文試験科目別の必要勉強時間
| 科目名 | 必要勉強時間 |
|---|---|
| 財務会計論(計算) | 100時間 |
| 財務会計論(理論) | 300時間 |
| 管理会計論 | 300時間 |
| 監査論 | 200時間 |
| 企業法 | 200時間 |
| 租税法 | 300時間 |
| 選択科目 | 200時間 |
科目数が多いため、それぞれの科目に必要な勉強時間の目安を確認した上で、計画的に勉強を進める必要があります。
合格までの必要年数は2〜4年程度
公認会計士試験合格するまでの必要年数は、約2〜4年程度と言われています。
合格に必要な勉強時間を5,000時間として、1日に確保する必要がある勉強時間を算出すると、以下のとおりです。
| 合格までの年数 | 1日に必要な勉強時間 |
|---|---|
| 2年(730日) | 6〜7時間 |
| 3年(1,095日) | 4〜5時間 |
| 4年(1,460日) | 3〜4時間 |
こちらは、休日を設けず毎日同じ時間を勉強に費やす場合の1日に必要な勉強時間です。
休日を設ける場合やまとまった勉強時間の確保が難しい場合は、1日の勉強時間が減少するため、上記よりも必要年数が増えることになります。
これだけの学習時間を必要とすると、いかにメンタルを維持して勉強期間を過ごせるかがポイントです。
大学生は比較的まとまった勉強時間を確保することができることから、大学在学中に公認会計士に挑む人も多いのです。
しかし、受験資格に学歴はありませんから高卒であったとしても全く問題なく挑戦することができます。
また、社会人になってから公認会計士を目指す人にとっては、以下に勉強時間を確保できるかが合格への道筋となります。
稀に独学で勉強して合格したという強者がいますが、大半の人は予備校や専門学校、スクールで専門的な講義の受講を重ね、順序立てて勉強を進めています。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
税理士が活躍できる求人をご紹介!
公認会計士試験の難易度が高い理由とは?

■この「マークシート用紙」は撮影用にデザインしたオリジナルです。
いくつかのデータや数値を参考にしてみると、公認会計士試験の難易度の高さが伺えます。
では何故、難易度がこんなにも高いのでしょうか。それには、以下のようないくつかの理由があります。
- 試験範囲が広い
- 試験内容が複雑
- 問題数が多い
- 試験科目に合った学習方法を確立が必要
- 合格基準点が決まっている
試験範囲が広い
まず試験範囲が広いことが挙げられます。
財務会計論(計算・理論)や管理会計論、監査論、企業法、租税法の他、選択科目として経営学や経済学、民法、統計学の中から1つを選ばなければなりません。
さらに、会計や監査分野は毎年改正や基準の追加が行われるため、インプットする範囲が膨大になります。
試験内容が複雑
また、内容が複雑であることも公認会計士試験の難易度を高めている原因です。
公認会計士の試験は、会計や監査に関わる法律に基づいた問題が出題されます。つまり、難解な法律を正しく読まなければ問題を解くことができません。
さらに公認会計士の試験は簿記の知識も求められることから、各項目における計算式も身につけておく必要があります。
問題数が多い
問題数の多さも難易度を高めている要因です。
基本的に、制限時間内にすべての問題を解き終わるのは難しいです。1つでも多くの問題に正解して得点を伸ばすためにも、適切に取捨選択をする必要があります。
多くの問題に効率良く対応しなければならない点も、公認会計士試験の難易度を高めていると言えます。
試験科目に合った学習方法の確立が必要
効率良く学習するためには、その科目に合った学習方法を確立しなければなりません。
公認会計士試験の科目は、いずれも専門性および難易度が高いものばかりです。
暗記をするだけでは合格できない点も、公認会計士試験が難しいことを表しています。
合格基準点が決まっている
そして、短答式試験でも論文式試験でも、合格基準点は決められています。
しかし、合格者数を一定水準にするため合格基準は上下することがあります。
つまり、何点以上獲得すれば必ず合格するというわけではない相対評価の試験であり、他の受験生の成績が良ければ自分が不合格になる可能性があるのです。

税理士が活躍できる求人をご紹介!
税理士試験の難易度を数字で分析
忙しい社会人にとっては公認会計士試験よりも合格しやすい税理士試験ですが、難易度の高い試験であることに変わりはありません。
公認会計士試験とは合格率や合格までにかかる年数などが異なるため、詳しく確認した上で受験を決めることが大切です。
税理士試験の難易度について様々な数字から解説した上で、公認会計士試験との違いにも触れていきます。
また、税理士試験の難易度について、更に詳しく知りたい場合は「税理士試験の合格率や難易度がどれくらいかを解説。他士業との比較とは?」をご覧ください。
合格率は18%前後
税理士試験の合格率は18%前後で推移しており、法律系の国家資格の中では高いほうです。
直近5年間の合格率の推移は、以下のとおりです。ここでの合格率は、受験者数を合格者数で割った数値としています。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和元年(2019年)第69回 | 29,779人 | 5,388人 | 18.10% |
| 令和2年(2020年)第70回 | 26,673人 | 5,402人 | 20.30% |
| 令和3年(2021年)第71回 | 27,299人 | 5,139人 | 18.80% |
| 令和4年(2022年)第72回 | 28,853人 | 5,626人 | 19.50% |
| 令和5年(2023年)第73回 | 32,893人 | 7,125人 | 21.70% |
合格率が20%を超える年がある一方で15%にまで落ち込む年もありますが、平均すると大体18%程度で推移しているのが分かります。
直近の2年では若年層の受験者数が増えており、若手税理士の拡充が期待できます。
先述の通り、公認会計士試験の合格率は10%前後のため、税理士試験のほうが比較的合格しやすいと言えるでしょう。
※出典: 国税庁税理士試験
合格に必要とされる勉強時間は約5,000時間
税理士試験に合格するために必要な勉強時間は、約5,000時間と言われています。
税務に関する知識量や実務経験の有無によって必要な勉強時間が異なりますが、公認会計士試験と同様の時間が必要になります。
税理士試験と公認会計士試験の違う点は、科目ごとの勉強量です。勉強時間は同じでも、税理士試験では暗記しなければならない内容が非常に多いです。
税理士試験には必須科目と選択必須科目、選択科目があり、それぞれに学習時間を割り振ると目安は以下のようになります。
必須科目の必要勉強時間
| 科目 | 必要勉強時間 |
|---|---|
| 簿記論 | 500時間 |
| 財務諸表論 | 500時間 |
選択必須科目の必要勉強時間
| 科目 | 必要勉強時間 |
|---|---|
| 所得税法 | 600時間 |
| 法人税法 | 600時間 |
選択科目の必要勉強時間
| 科目 | 必要勉強時間 |
|---|---|
| 相続税法 | 500時間 |
| 消費税法 | 300時間 |
| 酒税法 | 200時間 |
| 国税徴収法 | 150時間 |
| 住民税 | 200時間 |
| 事業税 | 300時間 |
| 固定資産税 | 300時間 |
選択必須科目の所得税法と法人税法は、いずれか1つを必ず選択しなければなりません。
選択科目は、上記の7科目のうちいずれか3つに合格する必要があります。必要勉強時間だけでなく、自分が持っている知識量や理解のしやすさなどを考慮して科目を選び、学習を進めることが重要です。
合格までの必要年数は3〜5年程度
税理士試験に合格するまでに必要な年数は、約3〜5年と長期間になると言われています。
合格に必要な勉強時間を5,000時間として、1日に確保しなければならない勉強時間を算出すると、以下のようになります。
| 合格までの年数 | 1日に必要な勉強時間 |
|---|---|
| 3年(1,095日) | 4〜5時間 |
| 4年(1,460日) | 3〜4時間 |
| 5年(1,825日) | 2〜3時間 |
1日に必要な勉強時間は公認会計士と同様です。
税理士試験であれば1科目ずつ受験できるため、合格までの年数はかかりますが1日の勉強時間を調整しながら仕事と両立させることが可能です。
そのため、税理士試験は社会人でも挑戦しやすいと言えます。1年に何科目受験するかによって勉強時間も異なるため、自分に合った計画やスケジュールを立てる必要ことが大切です。
また、独学よりも予備校や通信講座、ビジネススクールなどで体系だったカリキュラムで勉強を進めることが効率的な学習時間を過ごせるといえます。
<税理士試験の各科目を詳細に解説している記事をご紹介>
超難関の税理士試験の合格率はどれくらいかを解説。難易度や必要な勉強時間とは?
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
公認会計士試験と税理士試験どちらがおすすめ?

ここまで両資格の難易度の違いや必要な勉強時間を見てきましたが、結局のところどちらを受けるのがおすすめなのでしょうか?
もちろん、将来目指したい働き方や仕事内容にもよりますが、「試験に合格する」という観点から考えた場合は、以下の内容に分かれます。
- 受験勉強に専念できるなら公認会計士
- 忙しい社会人なら税理士
受験勉強に専念できるなら公認会計士!
受験勉強に専念できるのであれば、公認会計士を目指すのがおすすめです。
公認会計士試験は短答式試験と論文式試験の両方に一度で合格しなければならず、必然的に勉強量は多くなってしまいます。
膨大な知識を吸収しながら1度の試験で全て合格しなくてはならないことからも、限られた時間の中で戦略的にスケジュールを立て勉強を進めなくてはなりません。
さらに効率的に勉強を進めるのであれば、予備校や通信講座などに通える時間を確保できたほう有利です。
実際に合格者は膨大な勉強時間を確保できる学生やフリーターが多く、働きながら勉強時間を捻出しなければならない社会人は不利になりやすいと言えます。
勉強時間を十分に確保できる環境を整えられるのであれば、公認会計士の試験合格を目指すと良いでしょう。
大学生など年齢が若い方が公認会計士試験に挑む人が多いのは、決して学歴が必須というわけではなく、勉強時間を確保しやすい環境にあることが大きな要因だと考えられます。
忙しい社会人なら税理士がおすすめ!
大量の勉強時間を確保するのが難しい社会人には、税理士試験がおすすめです。
税理士試験は公認会計士試験と異なり、科目合格制を採用しています。
一度にすべての科目に合格する必要はなく、例えば毎年1科目ずつ受験することも可能です。
合格できない科目が出る可能性を考えて、毎年2科目ずつ受験するような形を取る受験者がほとんどですが、いずれにしても公認会計士試験よりも勉強量の負担が減るのは間違いありません。
1〜2科目ずつ受験する場合は、最終合格まで更に時間を必要とします。具体的に何年かけて税理士試験に合格することを目標にするのか、 継続可能なプランをきちんと立てることがコツです。
会計事務所で働きながら合格を目指す人も多い
税理士試験は、会計事務所で働きながら合格を目指す人も多い傾向にあります。
一度に全科目を合格しなければならない公認会計士試験と異なり、税理士試験は科目合格制です。1年に数科目ずつ合格し、数年かけて5科目合格を目指すことができます。
働いている人は1日にまとまった勉強時間を確保することが難しいため、一度の受験における勉強量をコントロールして現実的な勉強時間を確保できる税理士試験のほうが向いていると言えるでしょう。
ただし、税理士試験は数年かけて少しずつ合格を積み重ねていくため、きちんと計画を立てないと無駄に年数がかかってしまう懸念もあります。税理士試験に挑戦する際は、試験対策の計画を立てて挑みましょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
公認会計士と税理士業務の違いを把握しておくことも重要
公認会計士も税理士も、ともに人気のある国家資格です。
いずれも会計やお金に関する業務を担うため重複すると考えられる部分があるものの、基本的には異なる専門分野で業務を進めることになります。
業務の違いについて公認会計士と税理士の仕事、イメージとしてはおおよそは把握されているかと思いますが、業務のレイヤーが全く違っているのをご存知でしょうか。
公認会計士の業務の概要
公認会計士の主な業務は、独占業務である会計監査です。主に事業規模の大きい法人が対象であり、従業員数が多い監査法人に所属しチームで業務を進めるのが基本となります。
会計監査の対象となるのは、金融法で定められている上場企業だけではありません。会社法で定められている大手企業や、学校法人や独立行政法人なども対象となるため、公認会計士は幅広く会計監査業務を行うのが特徴です。
独占業務以外では、経営戦略や組織再編など経営に関わる相談や助言をするコンサルティング業務も行います。
クラウド会計の普及が進んでいる昨今では、以前から公認会計士が担当していた税務を社内で行う企業も増えたため、独占業務以外に独自の事業を展開する事務所が増えている傾向にあります。
公認会計士資格を取得していれば、無試験で税理士として登録も可能とありますので、ダブルライセンスを取得して幅広いキャリアパスを設定することだってできるのです。
BIG4などの大手監査法人(コンサルティングファーム)などではグローバルな対応も必要なケースも多いため、公認会計士に加えUSCPA(米国公認会計士)を取得し、業務の幅を広げている人も増えています。
業務の詳細は「公認会計士とは?ゼロからわかる仕事内容と魅力」で紹介しています。
税理士の業務の概要
税理士は、税金が関わるすべての業務を担います。
身近な例では、企業の年末調整や個人事業主の確定申告などが挙げられます。これらに必要な書類は税務書類のため代理で作成できるのは税理士のみであり、独占業務に該当します。
また税理士は、個人や法人から仕事を請け負うのが特徴です。
確定申告や高額所得者の相続税の申告など、個人に関する業務を行う会計事務所もあれば、法人向けの月次・年次決算や資金調達などの業務を中心に行う会計事務所もあります。
基本的に税理士は長期間に渡ってクライアントと付き合いを続け、幅広くサポートを行うのが特徴です。
近年では中規模以上の税理士法人も増えておりますが小規模な税理士事務所とは業務範囲や業務内容にも違いがありますので注意が必要です。
詳しくは「税理士の仕事内容とは?実は意外と知らない業務の中身を解説」でご紹介します。
また、両者の違いについて、更に詳しく知りたい場合は「税理士と公認会計士、資格取得するならどっちがおススメ?目指す前に違いを知ることが大切」をご覧ください。

働きながら資格取得なら会計求人プラスに相談
公認会計士試験や税理士試験は最高難易度レベルともいえる国家資格の試験です。
しかし、それぞれ難関資格の試験内容、難易度、資格取得後の仕事など大きく違う部分があることはご理解いただけたかと思います。
いずれの資格も会計学などについては共通に必要となる知識もありますので、全く違う資格というわけではないことは覚えておいてください。
そのほかにも受験資格にも違いがあり、税理士試験を受験するためにはクリアしないといけない条件がありますが、公認会計士試験には受験資格がなく誰でも受験することができるという違いもあります。
また、両者の受験資格などの違いについて、更に詳しく知りたい場合は「税理士と公認会計士の違いを解説!資格を取得するならどっち?」をご覧ください。
公認会計士の場合、勉強時間を十分に確保できる学生やフリーターにはおすすめですが、社会人が働きながら公認会計士試験の合格を目指すことは簡単ではありません。
そのため、働きながら試験勉強に臨む方は、税理士試験に挑戦するのがおすすめといえるでしょう。
税理士試験であれば、年数はかかっても少しずつ科目合格を積み重ねていくことができる科目合格制度がありますので、会計事務所や会社で働きながらでも挑戦しやすいと言えます。
ただし、公認会計士と税理士のどちらの資格試験を目指すのかは、将来のキャリアプランやメリット・デメリット、貴方の興味があるやりたい仕事などを明確にイメージを持ち、平均年収、業務内容、働く環境など多角的に検討することがポイントです。
公認会計士や税理士など会計業界に特化した会計業界専門転職支援サービス「会計求人プラス」は無料相談いただけます、貴方に最適な転職先の求人情報を見つけ出すサポートをいたします。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
投稿者情報

- 税理士や公認会計士、会計業界に関する記事を専門に扱うライター。会計業界での執筆歴は3年。自身でも業界についての勉強を進めながら執筆しているため、初心者の方が良く疑問に思う点についてもわかりやすくお伝えすることができます。特に業界未経験の方に向けた記事を得意としています。
最新の投稿
 公認会計士2025.06.29監査法人の就職は難しい?難易度・就活対策・Big4の特徴を徹底解説
公認会計士2025.06.29監査法人の就職は難しい?難易度・就活対策・Big4の特徴を徹底解説 経理2025.06.24日商簿記2級・3級の正式名称とは?履歴書に記載するポイントを解説
経理2025.06.24日商簿記2級・3級の正式名称とは?履歴書に記載するポイントを解説 税理士試験2025.04.04税理士試験に合格後のキャリアパスとは?選択肢とそれぞれの特徴を解説
税理士試験2025.04.04税理士試験に合格後のキャリアパスとは?選択肢とそれぞれの特徴を解説 転職ハウツー2025.03.12簿記1級を取っても就職できない?「やめとけ」といわれる理由とは?
転職ハウツー2025.03.12簿記1級を取っても就職できない?「やめとけ」といわれる理由とは?