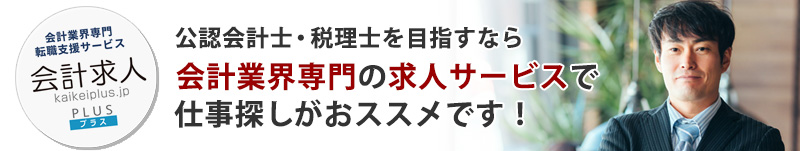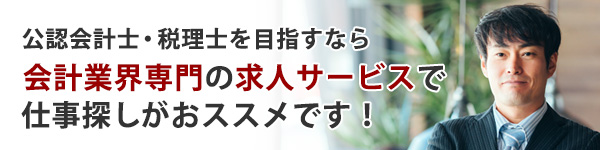簿記論とは?合格率・難易度・勉強方法などを解説
簿記論は、税理士試験の登竜門ともいわれる重要な科目です。近年の合格率は16~23%と、難易度は日商簿記1級と同程度と考えられます。合格には効率の良い勉強と問題演習が不可欠です。
本記事では、簿記論の概要や出題例、勉強方法などを紹介します。
会計事務所や経理へ転職をするなら会計業界専門の転職サイト「会計求人プラス」が最適!
完全無料の会員登録はこちらから
コンテンツ目次
簿記論とは?
簿記論とは、帳簿の記録(簿記)のルールや財務諸表の計算方法を学ぶ科目です。税理士として働く上で必要な、基本的な内容を学習する科目となります。出題範囲が広く出題論点が毎年異なるため、広い範囲を学習しなければなりません。
簿記論は税理士試験の必須科目
前提情報として、税理士試験の試験科目を紹介します。税理士試験の試験科目は、大きく「会計科目」と「税法科目」の2種類に分類されます(※)。
| 会計科目(必須) | ●簿記論 ●財務諸表論 |
| 税法科目(選択) | ●所得税法(選択必須科目) ●法人税法(選択必須科目) ●相続税法 ●消費税法または酒税法 ●国税徴収法 ●住民税または事業税 ●固定資産税 |
このうち、会計科目に属する2科目「簿記論」と「財務諸表論」は受験が必須です。税法科目は「所得税法」「法人税法」「相続税法」「消費税法または酒税法」「国税徴収法」「住民税または事業税」「固定資産税」の中から3科目を受験者が選択します。なお「所得税法」または「法人税法」のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。
税理士試験を突破するには、会計科目の2科目と選択必須科目のいずれか1科目以上を含む税法3科目、合計5科目に合格する必要があります。税理士試験は科目合格制を採用しているので、一度に5科目受験する必要はなく、1科目ずつ受験しても構いません。一度合格すると、生涯有効です。
なお、税理士試験は取得している資格や学位によって、科目免除制度が利用できます。科目免除されるための条件や利用時のメリット・デメリットは以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。
※参考:国税庁「税理士試験の概要」(参照 2024-11-13)
簿記論から学習すべき理由
上述のように、税理士試験にはさまざまな科目がありますが、学習するときは、まず簿記論を学び、次に財務諸表論に進むのが定番です。これら2科目は「簿財」と呼ばれ、合格が必須なだけでなく、法人税などの税法科目を学ぶ上で、土台となる基礎知識です。そのため、最初に学習すると良いでしょう。
中でも簿記論は、全て計算問題で構成されており、初学者にとって難しいとされる理論問題がありません。また日商簿記の学習をしたことがある人なら、同じように学習を進められるため、学びのハードルが低くなります。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
簿記論の試験日程
例年、税理士試験は8月上旬~中旬までの連続する3日間で実施されています。試験は1日3科目、1教科120分で時間は9時~17時30分までです。簿記論は日程中の試験1日目、9時~11時に実施されます。
参考までに、2024年の試験日程は以下の通りでした(※)。
| 日程 | 科目 | 試験時間 |
| 試験1日目 8月6日(火) |
簿記論 | 9時~11時 |
| 財務諸表論 | 12時30分~14時30分 | |
| 消費税法、酒税法 | 15時30分~17時30分 | |
| 試験2日目 8月7日(水) |
法人税法 | 9時~11時 |
| 相続税法 | 12時~14時 | |
| 所得税法 | 15時~17時 | |
| 試験3日目 8月8日(木) |
国税徴収法 | 9時~11時 |
| 固定資産税 | 12時~14時 | |
| 住民税、事業税 | 15時~17時 |
※参考:国税庁「試験日程・試験科目について」(参照 2024-11-13)
申し込みから合格発表までのスケジュール
税理士試験の申し込みには期日があるため、余裕を持って準備しましょう。令和7年度のスケジュールが公開されているため、ご紹介します。(※)。
●試験実施官報公告:令和7年4月4日
●受験申込受付開始:令和7年4月21日
●受験申込受付終了:令和7年5月9日
●試験実施:令和7年8月5日~令和7年8月7日
●合格発表:令和7年11月28日
ただし日程は今後変更される場合もあるため、受験を考えている人は都度最新の情報を確認してください。
※参考:国税庁「令和 7 年度(第 75 回)税理士試験 実施スケジュールについて(予定)」(参照 2024-12-12)
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
簿記論の特徴と出題例
税理士試験の簿記論は、計算問題が中心となり、問題のボリュームが多いのが特徴です。試験時間は120分ですが、1問当たりに費やせる時間が短いので、合格をするにはスピーディな解答が求められます。簿記論の問題は、大きく3問に分けて出題される形式です。ここでは、簿記論で出題される3問の主な内容を紹介します。
第1問(25点満点)
第1問では、資本の増減による取引を想定した計算問題などが出題されます。三分法による商品売買取引の記帳や商品売買益の算定に関する問題が含まれます。
第2問(25点満点)
第2問では、会計についての理解を問う問題が出題されます。解答するためには、帳簿上の処理と合併財務諸表の作成手続きの違いなどへの理解が必要です。さらに、国内支店とは異なる貸借対照表で行われる純損益、為替差損益計算を理解しているかも問われます。
さらに、ファイナンスリース取引の会計についての理解を問う問題も出題されます。ファイナンスリースは、ユーザー(借手)が選んだものをリース会社(貸手)が購入し賃貸する取引のことです。リース取引とは、特定の物件の所有者であるリース会社が、該当する物件のユーザーに対してあらかじめ決められた期間内に物件を使用収益する権利を与えて、一方でユーザーが合意された使用量をリース会社に支払う取引を指しています。
第3問(50点満点)
第3問では、決算整理前残高試算表を基に、決算整理後残高試算表を作成する計算問題
期中の取引終了後に決算整理前残高計算表を作成し、決算整理仕訳を経て作成する残高試算表を「決算整理後残高試算表」といいます。決まった方法で計算すれば正しい答えを導き出すことができ、最後に数字が合っていることが確認できるので、間違いに気づきやすいのが特徴です。
より詳しい試験問題については、国税庁ホームページの「税理士試験」内でも公開されています。問題の中でも第3問は配点が高いので、落ち着いて計算をして得点を取りたいところです。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
「簿記論」と「簿記検定」は別物
「簿記論」と「簿記検定」は別物なので注意しましょう。「簿記論」は国税庁の国税審議会が実施する税理士試験の科目の一つです。一方「簿記検定」は、以下の団体や組織で実施される資格試験です。
●日本商工会議所:日商簿記
●全国経理教育協会:全経簿記
●全国商業高等学校協会:全商簿記
このうち日商簿記は、税理士試験の簿記論と出題範囲が重なる部分が多いです。簿記2級では約60%、簿記1級では90%が共通するとされています。ただし、簿記と簿記論とでは出題方法が異なるため、それぞれ学習が必要です。
日商簿記1級があれば税理士試験の受験資格を得られる
日商簿記1級があれば税理士試験の税法科目の受験資格を得られます。簿記検定に受験資格はないものの、税理士試験は原則として学識・資格・職歴、いずれかの資格を満たさなければ受験できません(※)。
| 学識 | 大学などを卒業した者で社会科学に属する科目を1科目以上履修した者など |
| 資格 | 日商簿記1級を取得していることなど |
| 職歴 | 税理士事務所などで補助業務に2年以上従事した者など |
このため学識や職歴を満たしていない場合、誰でも受けられる日商簿記で1級を取得し、税理士試験を受験するのも一つの手段です。
なお、日商簿記1級を取得したからといって税理士試験の簿記論が免除になるわけではないため注意しましょう。
※参考:国税庁「税理士試験受験資格の概要」(参照 2024-11-13)
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
税理士試験の簿記論の合格基準と合格率
税理士試験の簿記論の合格基準は、満点の60%以上とされています(※)。
合格率は年度によって変化しますが、近年では約16~23%と、令和元年以前と比べると上昇傾向にあります。直近の合格率は以下の通りです(※)。
| 受験年度 | 合格率 |
| 令和5年 | 17.4% |
| 令和4年 | 23.0% |
| 令和3年 | 16.5% |
| 令和2年 | 22.6% |
| 令和1年 | 17.4% |
なお、令和元年以前の合格率は12~14%程度でした。年度により受験者数や試験の出題内容に差があるため、一概には言い切れないものの、数値だけ見ると近年は合格しやすくなっていると考えられます。
※参考:国税庁「税理士試験の概要」(参照 2024-11-13)
※参考:国税庁「税理士試験」(参照 2024-11-13)
簿記論の難易度
税理士試験科目の中でも合格率だけ見れば、簿記論の難易度はそれほど高い方ではありません。しかし、一般的な資格試験と比べれば、十分難易度は高いといえるでしょう。例えば、同程度の合格率の試験にはファイナンシャル・プランニング技能検定1級(7~18%)、宅地建物取引士資格試験(15~18%)、貸金業務取扱主任者資格試験(25~33%)などの難関資格があります。
簿記論は計算問題が中心となり、制限時間内には回答し切れないほどの問題が出題されます。そのため計算能力が求められるだけでなく、難問を捨てるとっさの判断力や、基礎問題を落とさない解答テクニックも必要です。
日商簿記1級と簿記論はどちらが難しいか
簿記論と日商簿記1級はどちらの方が難しいのか、比較対象として挙げられることが多いものの、一概に言い切ることはできません。例えば合格率だけを見ると、日商簿記1級が10~16%なのに対し、簿記論は16~23%程度です。
これだけ見ると、日商簿記1級の方が難易度が高いように思えます。しかし、受験者の属性や受験者数、資格を取る目的に違いがあるため、単純に比較できるものではありません。
問題の傾向としては、日商簿記1級では工業簿記の難易度が高く、原価計算も含まれます。一方、商業簿記では簿記論の方が難易度は高く、容易に回答を導き出せないような問題も含まれています。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
簿記論合格に必要な学習時間
簿記論合格に必要な学習時間は300~1,000時間程度とされています。必要な学習時間に大きな開きがある理由には、受験者によってこれまでの学習経験や職歴などに大きな違いがあるためです。学習計画を立てるときは、現在の自分がどの程度簿記論の学習に役立つ知識を持っているかを確認しましょう。
簿記初学者は1,000時間程度
今まで簿記の学習をしたこともなければ、事務や経理の仕事もしたことがない全くの初学者の場合は、1,000時間程度かそれ以上の学習時間を見積もった方が良いでしょう。一日3時間程度勉強するとして、1年近くかかる計算です。まずは簿記の基礎知識から身に付け、徐々に中・上級者向けの内容を覚えましょう。
簿記1級経験者は300~450時間程度
これまでに簿記1級を取得していたり、税理士事務所など会計業界で業務経験があったりする場合は300~450時間程度の学習時間を見積もっておきましょう。一日3時間の学習で、5カ月程度です。すでに簿記論の知識はある程度そろっていると考えられるため、知識の補足をしたり過去問を解いたりといった対策が中心となります。
簿記論は独学でも学習可能!ただし合格は難しい
税理士になるために簿記論を学習しようとする人の中には、独学でも合格できるか気になる人もいるかもしれません。簿記論を含む税理士試験の科目を、全て独学で習得すること自体は可能です。ただし、難易度は高いでしょう。
税理士試験の勉強は専門学校や予備校に通ったり、通信教育を利用したりして進めるのが一般的です。税理士試験は独学用の教材が少なく、選択肢が限られます。さらに、学習を進める中で分からないことがあっても、全て自力で解決する必要があります。
簿記や会計などの専門性の高い学習では、何が分からないのかを判断できないことも少なくありません。このため簿記論1科目だけであっても、独学で合格ラインまで学習を進めるとなれば、相当な努力と時間が必要です。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
簿記論独学のメリット・デメリット
簿記論の独学は難しいとはいえ、メリットもあります。独学を考えているなら、メリットとデメリットを比較した上で、合格できる自信があればチャレンジするのも良いでしょう。
メリット
簿記論を独学するメリットは以下の通りです。
●試験勉強の費用を節約できる
●仕事や家庭と両立しやすい
●粘り強く考える力を養える
独学の大きなメリットは、試験勉強の費用を節約できる点です。予備校で税理士試験5科目全てを学ぶとなれば、80万~100万円程度の費用がかかります。ある程度知識があるなら、簿記論や財務諸表論を独学するだけでも、予備校費用の節約につながります。
独学であれば、仕事や家事・育児と両立しやすい点もメリットです。予備校に通うなら、その分のまとまった時間を確保しなければなりません。独学であれば、仕事の昼休憩の時間や家事が終わった後の深夜など、好きな時間に学習を進められます。
さらに、独学を通して粘り強く考える力を養えることもメリットです。独学では自分で課題を発見し解決する「自己解決力」や「問題解決能力」がなければ進められません。これらの力は税理士になっても求められるため、早くから実践的な力を身に付けておくことで後々の役に立つでしょう。
デメリット
簿記論を独学するデメリットは以下の通りです。
●モチベーションの維持が困難
●答えの導き方が正しいか分からない
独学では講師の指導がなく、勉強のスケジュール管理を全て自分で行わなければなりません。また、高額の出費もないため気が緩みやすく、簿記論に合格するには強い意志が必要です。
さらに、簿記論は計算問題が中心であるため、正解にたどり着いても解法が間違っている可能性があります。独学では答えに至る過程を正しく確認することが困難なため、誤った解法のまま長期間勉強を続けてしまうリスクがあります。
簿記論の勉強方法を解説
簿記論の試験に向けて、具体的にどのような対策をすれば良いのでしょうか。ここでは簿記論の勉強方法について解説します。
参考テキスト・問題集・過去問を中心に勉強する
試験問題はほぼ全てが計算問題なので、問題演習を中心に勉強しましょう。計算が苦手な方はできるだけ問題を多く解くのが理想です。独学で問題集を使った勉強が苦手な場合は、学校に通ったり通信講座を利用したりすると良いでしょう。
過去問を解く際には、試験と同じ時間内に解く練習をおすすめします。普段の勉強から本番と同じように練習すれば、緊張しにくくなります。
過去問・問題集の問題は採点する
試験対策に有効な勉強方法は、とにかく実践です。個別問題だけでなく総合問題も何度も繰り返し解きましょう。演習により解答のスピードを上げることができます。
解いた問題は採点して、間違った問題は解答を読んで解法を理解し、もう一度解き直してください。同じ間違いを繰り返さないように、しっかりと理解するようにしましょう。
財務諸表と関連付けながら勉強する
財務諸表とは、企業が株主や取引先などの利害関係者に対して、自社の一定期間の経営成績や財務状態を報告するための書類のことです。経営戦略を立てる際にも財務諸表を参考にします。どれくらいの利益や損失を出しているのか詳細な内訳を見ることができる資料です。
会計学に属する2科目「簿記論」「財務諸表論」が必須となっているので、関連付けながら勉強すると良いでしょう。
なお財務諸表論の問題は、計算と理論です。先に簿記論で計算を得意としておけば、次に財務諸表論の試験勉強に挑むときは理論の勉強だけで済みます。簿記論に合格しておけば、自信を持って財務諸表論試験を受けることができるでしょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
簿記が苦手な人が簿記論を勉強するときのポイント
簿記論に合格するためには、計算問題をスムーズに解いていくことが重要なポイントになります。まずは問題の解き方を身に付け、計算速度を上げる練習をしましょう。
問題の解き方を身に付ける
まずは過去問や問題集の解答を確認して、問題の解き方や計算の方法を身に付けましょう。計算方法があいまいだと、素早く問題を解くことはできません。分からない問題は、解答を確認して解き方を徹底的に覚えましょう。
計算速度を上げる練習をする
ある程度問題の解き方が身に付いたら、簿記論の個別問題など、簡単な問題をどんどん解きましょう。簿記が苦手な人の多くは、特に仕訳につまずく傾向にあります。仕訳のような基本的な問題は、問題集だけでなくWebサイトやスマートフォン向けアプリなどを使った対策もできます。隙間時間も活用し毎日取り組み、慣れるようにしましょう。
簿記論の試験当日に気を付けること
簿記論の試験当日はどのような点に気を付ければ良いのでしょうか。ここでは試験当日の注意点や、問題を解く際のポイントを解説します。
遅刻厳禁!余裕を持って会場入りする
税理士試験では、試験開始の15分前から試験の説明があります。その後、試験官から試験開始の合図がされ、それ以降は原則入場できません。どれだけ勉強しても遅刻をすれば、来年の税理士試験に持ち越しとなります。
簿記論は試験1日目の9時開始です。税理士試験は平日に行われるため、交通機関の混雑も予想されます。事前に会場までの道のりを下見するなど、遅刻しないように準備を徹底しましょう。
問題の取捨選択をする
簿記論では、制限時間内にはとても回答し切れない量の問題が出題されます。中には極端な難問も混ざっているため、試験が開始されたら試験問題をざっと一読しましょう。
その上で、問題を基本問題・応用問題・難問に分類します。簿記論では基本問題を落とさず、応用問題でもなるべく得点を稼ぎ、難問は捨てるといった、取捨選択が必要です。
時間配分を決める
第一問20分、第二問20分、第三問50分のように、それぞれの問題にかける時間を配分します。これは、模擬試験のときから自分に合った配分を見つけておくと良いでしょう。
基本問題から順に解いていき、あらかじめ決めた制限時間が来たら、解き終わっていなくても次の問題に移ることが大切です。制限時間を設けることで、難問に必要以上にとらわれず、基礎問題を落とさない解き方につながります。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
税理士試験の簿記論合格は就職・転職に有利
税理士試験の簿記論に合格していれば、会計業界・一般企業を問わず、就職・転職に有利です。特に税理士事務所では、税理士試験の科目合格数に応じた基本給の優遇を行っていることもあります。
税理士試験のうち1~2科目に合格しているだけでも、転職市場では大きな価値があります。また、会計業界への就職を考えているなら、税理士を目指していなくても、簿記論や財務諸表論は取得するのがおすすめです。税理士試験の会計科目は2023年より受験資格が撤廃されたため、誰でも受験できます。
会計業界を目指すなら、税理士試験の簿記論は取得する価値あり!
簿記論は税理士試験の試験科目の中でも、必須科目の一つです。合格率16~23%の難関試験ではあるものの、一度取得すれば生涯有効で、就職・転職どちらにも役立ちます。会計業界を目指しているなら、取得しておいて損はありません。
会計士・税理士事務所の求人・転職サイト「会計求人プラス」では、会計業界に特化した求人を取り扱っています。税理士を目指す人はもちろん、簿記論など税理士試験科目を就職に役立てたい方は、ぜひ登録の上、求人探しにご活用ください。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
投稿者情報

- 税理士や公認会計士、会計業界に関する記事を専門に扱うライター。会計業界での執筆歴は3年。自身でも業界についての勉強を進めながら執筆しているため、初心者の方が良く疑問に思う点についてもわかりやすくお伝えすることができます。特に業界未経験の方に向けた記事を得意としています。
最新の投稿
 税理士の仕事2026.01.18会計と税務の違いを解説!会計業界で働くなら知っておきたい基礎知識
税理士の仕事2026.01.18会計と税務の違いを解説!会計業界で働くなら知っておきたい基礎知識 会計士の仕事2025.10.19公認会計士にMBAは必要?取得のメリット・デメリットと将来性を解説
会計士の仕事2025.10.19公認会計士にMBAは必要?取得のメリット・デメリットと将来性を解説 税理士2025.10.03税理士の仕事内容とは?主な就職先、魅力・やりがいについても解説
税理士2025.10.03税理士の仕事内容とは?主な就職先、魅力・やりがいについても解説 転職市場動向2025.08.18簿記3級の合格率はどれくらい?年度ごとの推移と合格者の傾向を徹底解説
転職市場動向2025.08.18簿記3級の合格率はどれくらい?年度ごとの推移と合格者の傾向を徹底解説