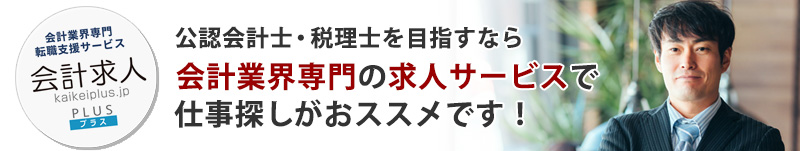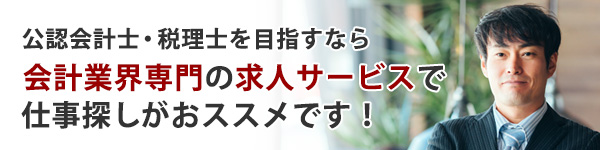会計の仕事内容とは?経理・財務・税務との違いから役立つ資格まで解説
会計事務は企業におけるお金の出入りを記録・記載・管理する仕事です。
会計事務の仕事内容について大まかな仕事内容はイメージできても、具体的な業務内容を知らない人も少なくありません。「財務会計」と「管理会計」の2つに分かれ、日次・月次・年次で業務を行います。当記事では、経理・財務・税務の仕事と比較しながら会計事務の仕事内容を紹介するとともに、会計事務の仕事に役立つ資格を解説します。
■□■□会計業界へ効率的に無駄のない転職活動をするなら専門転職サイト「会計求人プラス」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□
コンテンツ目次
会計の仕事とは
会計事務は企業や公的機関などの日々の収支を記録し管理する職種です。注意点として会計と似た仕事に「税務」や「経理」があります。仕事内容が異なるため混同しないようにしましょう。ここでは参考に、会計事務と財務、経理、税務のそれぞれの違いについて説明します。
会計と経理の違い
経理業務では、企業において日常的に発生した収支を管轄し通常は経理部の経理職担当者が経理処理・対応を行い、仕訳を切ります。毎日の売上や税金の処理、給与などのお金の流れの詳細を管理し会計基準に従って適切な勘定科目を利用し会計帳簿・総勘定元帳に集計し、記帳しまとめることが主な会計事務の仕事内容です。経理が行った業務をもとに決算書作成が行われます。
会計と財務の違い
会計事務の役割は、企業の収支を記録し、財政状態や経営成績を利害関係者に報告することです。対照的に、財務はその会計情報を活用して、「スムーズな経済活動を進めるために、資金計画を練りどのように資金調達すべきか」を見極めることが主な目的です。現金出納帳・預金出納帳などを利用します。
会計と税務の違い
税務は、納税すべき金額を算出し申告する業務で、主に法人税に関する申告書を作成します。税務では、法人税の申告を行うことを目的としますが、会計事務は最終的に社外に情報を公表することが目的です。
会計の仕事の種類
会計事務の仕事は、主に「財務会計」と「管理会計」の2種類に分類されます。それぞれ役割が異なるので、正しく把握しておくことが大切です。
財務会計
財務会計は、投資家や金融機関、税務署、取引先など、企業と利害関係にある外部に対して、財政状態や経営成績などを開示するための業務です。財政状態とは、所有している資産や負債の状況、経営成績は、会計期間においてどの程度の利益があるかということを意味します。
投資家は、財務会計で報告された情報を踏まえて、株式の売買を検討します。これらの情報は、金融機関にとっても融資の判断をするうえで大切な情報です。外部との関係を円滑にし、公正な取引を行うためにも、正確な財務会計が重要視されます。
管理会計
管理会計は、企業の業績を把握するための業務です。外部に対して情報を開示する財務会計とは異なり、経営者や管理者など企業内部の利害関係者に対して経済状況について資料を作成して報告し、会社経営に役立てます。内部で活用するための情報・データであり、法的な決まりはありません。各企業が、自社の経済状況を明確に把握するために、独自のルールを設けるケースが一般的です。予算管理などが実施されます。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
会計の仕事内容
前述した「財務会計」、「管理会計」によって仕事内容が異なります。それぞれの仕事内容について確認しておきましょう。
管理会計の仕事内容
管理会計では、主に予算の管理や原価管理を行います。予算の管理は、年度ごとに行われるだけでなく、中長期的なスパンで全体目標を立て、各部門に対して予算を振り分けたり、分析を行ったりする業務であり、経営管理に役立てます。
また原価管理は、商品やサービスにかかる費用を具体的に把握し、原価の最適化をおこなうための業務です。主に製造業で導入される業務であり、原材料費や人件費、設備費などの原価計算を、可視化します。業務効率を見直して効率化し、無駄が発生する理由を特定して削減し、目標として設定した原価と現状の差を踏まえて、適正な原価を導くためにも原価管理は大切な作業です。
財務会計の仕事内容
財務会計には主に「情報提供機能」と「利害調整機能」があります。企業は、投資家や金融機関など利害関係のある外部に対して、投資や融資を行う際に的確な判断をするための情報を提供しなければなりません。財務会計の情報提供がなければ、企業の経営状況が分からないため、投資や融資を受けるのは難しいでしょう。適正な財務会計を行い、情報の信用度を上げることが大切です。
また、外部との利害に関して問題や対立が発生した場合にも、財務会計は調整役として活躍します。例えば、株主は、投資したお金が適切に使われることによって、企業が成長し、株の値上がりや配当金が増えることに期待を寄せています。しかし、企業の財務状況の情報を開示しなければ株主に不信感を与えることになるでしょう。財務会計によって、適切に管理された財務情報を開示できれば、トラブルを回避でき、スムーズに利害調整を行えます。
会計業務の流れ
会計業務には、基本的に「日々の業務」、「月次業務」、「年次業務」の3つの業務があります。ここでは、会計業務の具体的な手続きを、企業会計を例にして3つの業務ごとに解説します。
日次業務
企業では、日々の経済活動において、様々な取引が行われています。こうした取引や動き、金銭の入金・出金の処理が、会計で行う日々の業務です。業務内容は業種によって異なりますが、一般的に、領収書に基づく売上や仕入れの他、消耗品費や旅費交通費、雑費などの経費精算や伝票理や帳簿付け・帳簿作成を行います。通常はPCで会計ソフトを使用し、仕訳入力を行うことで日々の処理を実行します。ある程度社内で手間や無駄を省き、自動化されているのが通常です。当たり前のポイントではありますが、業務フローを見直し、効率的にミスなく実施することが重要です。
月次業務
月次業務では、給与計算や月締めで請求書を発行した売上の処理などを行います。また、買掛金や売掛金に関する処理や、従業員が立て替えて支払った経費の精算と支払い、減価償却費の計上なども月次で行う作業です。また、企業によっては、帳簿を月ごとに締め、決算書を作成する「月次決算」を実施するケースもあります。月次決算を行うことで、経営状況を細かく確認できるため、早い段階で事業戦略を練りやすくなるのがメリットです。
年次業務
年次業務では、年末調整に関する事務や財務諸表、税務申告書類の作成などを行い年次決算を組みます。年次業務で作成する決算書は、月次決算とは異なり、株式会社は必ず行わなければなりません。日々の業務や月次業務によって会計処理された1年間の取引内容をチェックし、税法に則った書式で決算書を作成します。そのうえで、法人税や消費税といった各税金の納付額の計算、税務申告を行うのも年次業務の1つです。
会計事務の業務に興味がある人は、求人案件を探してみてはいかがでしょうか。会計求人プラスは、会計業界に特化した求人サイトです。経験者・未経験者を問わず、希望にマッチする案件をご紹介しています。また、会計業界に長けたエージェントが在籍しており、初めて転職を検討するという人でも安心です。簡単に登録できます。詳しくは下記のページをご覧ください。
会計の仕事に向いている人
会計の仕事に向いているのは以下の人が挙げられます。
- 自ら最新の情報を調べられる人
- コツコツと勉強をすることが苦ではない人
- パソコン操作が得意な人
- 責任感がある人
- 仕事を抱え込まず、疑問点があれば周囲に助けを求められる人
会計事務の仕事は、簿記や税金、労務、金融など様々なジャンルの知識が必要です。これらの情報は法律の改定で変化することがあるため、自ら最新の情報を調べられる人や、自身の知識のアップデートのためにコツコツと勉強ができる人は会計の仕事に向いています。また、会計業務は、パソコンを使って行われるケースがほとんどであり、パソコン操作に長けている人にもおすすめです。
加えて、会計は金銭の管理だけでなく、決算書の作成や報告を行う必要があり、企業の経営に大きく関わる業務も行います。そのため、責任感があり、分からないことをそのままにしない姿勢も重要です。
会計の仕事に役立つ資格
簿記検定
日商簿記は、商工会議所が主催する検定試験で、経理関連の中で非常に有名な資格のひとつです。難易度は初級から1級までの4つに分かれており、試験内容には営業活動の記録や計算、整理など、経理の基礎知識が集約されています。
通常、企業が必要とする知識が身につくのは2級レベルからであり、この資格を取得することで主に中小企業から高い評価を受けることができます。一方で、1級レベルに進むと合格率が1割を下回り、資格取得のハードルが高まりますが、より専門性に特化した知識を身につけることができ、将来のキャリアアップに大いに役立つでしょう。
特に、複雑な損益計算書や貸借対照表について理解するために、日商簿記検定3級程度の知識が必要です。また、経営を分析する管理会計では、日商簿記2級程度の知識があると業務で活かせます。
現場で業務をこなしながら覚えるのも1つの方法ですが、日商簿記の資格を得ておくと転職時にも役立つため、早い段階でチャレンジしておくと良いでしょう。
FP(ファイナンシャルプランナー)
ファイナンシャルプランナー(FP)には、国家資格の「FP技能士」や日本の民間資格である「AFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)」、国際資格のCFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)の3つの種類があります。FP技能士は有効期限がなく、一度合格すれば更新の必要がないため、非常に人気があります。FP技能士には3級、2級、1級のランクがあり、通常は2級以上が評価されます。2級FP技能士は、おおよそ100時間の勉強で合格することができ、独学でも取得できる可能性が高いです。2級FP技能士に合格すれば、日本FP協会が提供する研修を受講し登録するだけでAFPの取得も可能です。
税理士
税理士は、国税庁が主催する国家資格検定であり、受験資格には学歴や実務経験などさまざまな条件が設けられています。ただし、簿記1級を取得している場合は、条件にかかわらず受験が可能です。試験内容は、会計学に関する2科目と税法に関する7科目から3科目を選んだ計5科目からなります。
試験は1年に1回の開催で、最大5科目まで受験ができます。ただし、各科目の合格率は10%前後と低いため、多くの受験者は1科目ずつ受験し、長期的に合格を目指します。そのため、社会人になっても目指す人が多いのが特徴で30代で5科目合格し税理士として登録できたとしても若手と見られることが多い資格でもあります。
公認会計士
公認会計士は、金融庁の公認会計士・監査審査会が主催する国家資格であり、日本国内の資格の中でも最も難しいとされている専門家資格の一つです。資格取得には通常2年から4年の勉強時間が必要であることがデメリットですがメリットも大きいです。試験内容は原則として、財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の4科目に関する短答式試験と、会計学・企業法・監査論・租税法の必須科目、経営学・経済学・民法・統計学から1科目を選ぶ論文式試験の2部構成です。
会社法で資本金5億円以上の大企業などは会計監査を受けることが義務付けられているため非常にニーズの高い資格です。
また、公認会計士は平均年収も高く、コンサルティングなどの業務にもつきやすい資格ですから将来性が高いのも特徴です。
会計業界で働くなら会計求人プラスに登録
会計事務は、企業がスムーズに経営をすすめるための指標となる大切な業務です。日々の業務はコツコツと丁寧に行う必要があり、根気がいる作業といえるでしょう。しかし、最終目的である決算書の作成や利害関係者への報告は、企業において重要な業務であり、業務を遂行した後はやりがいを感じられます。
会計事務に興味があっても、知識やスキルがないため転職を悩んでいる人も多いでしょう。会計事務に関する知識は、仕事をしながら経験を積んで学ぶことも可能です。そのためには、働きながら学べる環境が整った転職先を探さなければなりません。
会計求人プラスは、会計業界に特化した求人サイトであり、働きながら学べる求人案件も多数あります。また、会計業界に特化したエージェントが無料で丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
投稿者情報

- 税理士や公認会計士、会計業界に関する記事を専門に扱うライター。会計業界での執筆歴は3年。自身でも業界についての勉強を進めながら執筆しているため、初心者の方が良く疑問に思う点についてもわかりやすくお伝えすることができます。特に業界未経験の方に向けた記事を得意としています。
最新の投稿
 公認会計士2025.06.29監査法人の就職は難しい?難易度・就活対策・Big4の特徴を徹底解説
公認会計士2025.06.29監査法人の就職は難しい?難易度・就活対策・Big4の特徴を徹底解説 経理2025.06.24日商簿記2級・3級の正式名称とは?履歴書に記載するポイントを解説
経理2025.06.24日商簿記2級・3級の正式名称とは?履歴書に記載するポイントを解説 税理士試験2025.04.04税理士試験に合格後のキャリアパスとは?選択肢とそれぞれの特徴を解説
税理士試験2025.04.04税理士試験に合格後のキャリアパスとは?選択肢とそれぞれの特徴を解説 転職ハウツー2025.03.12簿記1級を取っても就職できない?「やめとけ」といわれる理由とは?
転職ハウツー2025.03.12簿記1級を取っても就職できない?「やめとけ」といわれる理由とは?