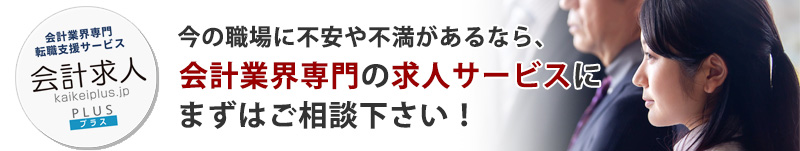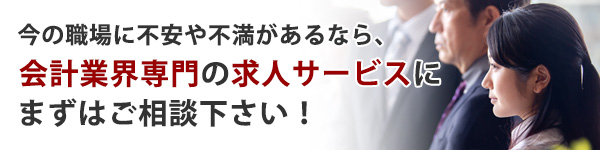公認会計士とは?仕事内容や試験、魅力についてを解説
2024/12/15
公認会計士は、いわゆる「士業」に分類され、日本国内でも最難関の資格の1つとされています。華やかなイメージがある一方で、「激務」や「将来的に廃れる」という噂を耳にし、不安を感じている方も多いかもしれません。
この記事では、公認会計士に興味を持っている方に向けて、公認会計士の業務内容や主な勤務先について基本的な情報をお伝えします。また、公認会計士の将来性や収入など、気になる働き方についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
■□■□会計業界へ効率的に転職活動を進めるなら専門転職サイト「会計求人プラス」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□
コンテンツ目次
公認会計士とは
公認会計士は、監査や会計の専門職であり、財務に関する高度な知識を活用して、法定監査や税務、会計業務など、資金管理や資金調達に関連する業務を担当する専門家です。
公認会計士の仕事内容
公認会計士の主な業務は、監査、税務、コンサルティング、会計の4つに分類されます。各分野で公認会計士がどのような役割を果たすかについて解説します。
監査って
監査は公認会計士の主要な業務であり、他の資格では行えない公認会計士の独占業務です。簡単に言えば、決算書や財務諸表が正確かどうかを確認する作業です。
上場企業は投資家向けに財務情報を公開していますが、経営者自身がその正確性を証明することはできません。そこで、第三者である公認会計士が財務内容を検証し、その信頼性を保証するのが監査の役割です。監査には「法定監査」と「任意監査」があります。
法定監査は、法律に基づき義務付けられている監査です。たとえば、会社法により資本金が5億円以上、または負債額が200億円以上の株式会社は法定監査を受ける必要があります。
任意監査は、法律に基づかない監査で、法定監査の対象外の会社や、海外支店の監査などがこれに該当します。
監査業務は、数人のチームで分担し、書類の整合性や計算の正確さを確認して進められます。
公認会計士試験合格後は、まず監査法人で経験を積むのが一般的です。監査業務が公認会計士の基本的な業務となるため、試験に合格した多くの人が監査法人で働き始めます。国内には約250の監査法人があり、企業や法人の監査を担っています。
税務
公認会計士は、税務代行や税務に関する相談を行います。税務代行業務では、中小企業の経営者や個人事業主に代わり、税務申告をサポートします。税務相談業務では、法人税、所得税、相続税などに関する悩みや疑問に対してアドバイスを提供します。
税務代行業務では、消費税や法人税などの申告書を中小企業や個人事業主の代わりに作成します。そのため、適切な会計処理や関連法の知識が求められます。税務相談では、記帳の方法がわからない場合や節税対策を行いたい場合など、税務に関する悩みに対して適切な助言をします。
【公認会計士は税理士としても登録可能】
公認会計士は、財務省令で定められた税法に関する研修を実務補習で修了すれば、税理士として登録することが可能です。つまり、税理士試験を受けずに税理士登録の要件を満たすことができます。
コンサルティング
公認会計士は、経営課題の解決を支援するコンサルティング業務を担当することもあります。具体的には、以下のような幅広い経営に関する問題に対してサポートを提供し、解決策を模索します。
【公認会計士によるコンサルティング業務の例】
・企業の経営戦略や長期計画の立案
・組織再編に関する助言
・企業再生計画の策定および検証
・株価や知的財産の評価
コンサルティング業務は、独立を目指しやすく、一定の収入を得ながら自身のスキルを活かして幅広く活躍できる可能性があります。
組織内会計士
企業や組織によっては、財務や会計部門を設置している場合があります。公認会計士は、以下のような企業や組織内で会計の専門家として活躍することが可能です。
【公認会計士が活動する企業や組織の一例】
・一般企業
・教育機関
・地方自治体
・非営利団体
働き方を改善したいなら
「会計求人プラス」
「残業が多い」「テレワーク対応した職場で働きたい」と思っていませんか? 会計事務所・税理士事務所で働き方を変えたいなら、専門の転職・求人サイト「会計求人プラス」がおすすめです。
公認会計士が活躍できる求人をご紹介!
公認会計士の4つの魅力とは
公認会計士の魅力は、安定した収入にとどまりません。多岐にわたる分野で活躍できることや、仕事とプライベートのバランスが取りやすい点も魅力の一つです。
将来性があり安定している
公認会計士の強みは、将来性と安定した需要にあります。先述したように、経済活動がある限り、会計業務は必須です。経済が続く限り、公認会計士の仕事が消えることはなく、将来的にも安定した需要が見込まれます。これに
働き方を改善したいなら
「会計求人プラス」
「残業が多い」「テレワーク対応した職場で働きたい」と思っていませんか? 会計事務所・税理士事務所で働き方を変えたいなら、専門の転職・求人サイト「会計求人プラス」がおすすめです。
より、長期間にわたって活躍できると考えられます。
さらに、公認会計士業界では高齢化とニーズの拡大が課題となっています。今後多くの退職者が出ることで人手不足が懸念されています。その一方で、会計業務の重要性が社会で再認識され、ニーズはますます高まっています。
こうした背景を考えると、現状では公認会計士の需要が将来にわたって減少するとは考えにくいです。
平均収入が高い
「2.公認会計士の主な仕事は「監査」「税務」「コンサルティング」「会計」でも述べたように、公認会計士はさまざまな分野で活躍できるため、働き方次第では年収2,000万円や3,000万円を目指すことも可能です。
性別関係なく活躍できる
公認会計士の職業においては、男女間での不平等は存在しません。年収差がほとんどなく、実力や経験に応じて公平に評価されます。
以前は男女間に差がありましたが、女性の公認会計士試験受験者が増加したことや、女性でも業務を遂行できる環境が整ったことで、男女平等が実現しました。
最近では、独立した女性公認会計士も増加しており、男性と女性の年収差はほとんどないと言えるでしょう。
社会的な信頼度が高い
三つ目の魅力は、公認会計士の社会的地位の高さです。冒頭でも触れたように、公認会計士は医師や弁護士と並ぶ三大国家資格の一つとされています。医師は医療行為を、弁護士は裁判に関連する業務を独占的に行う一方で、公認会計士は監査業務において独占的な権限を持っています。
公認会計士には他の資格では得られない特別な権限が与えられ、経済界では最高の国家資格と見なされています。そのため、公認会計士と名乗るだけで「信頼性」や「安心感」を醸し出すことができます。このような社会的地位により、
・責任ある業務を任される
・高い報酬を得られる
などの点で、報酬や地位において有利に立つ可能性があります。
働き方を改善したいなら
「会計求人プラス」
「残業が多い」「テレワーク対応した職場で働きたい」と思っていませんか? 会計事務所・税理士事務所で働き方を変えたいなら、専門の転職・求人サイト「会計求人プラス」がおすすめです。
公認会計士が活躍できる求人をご紹介!
公認会計士試験を受ける条件と難易度
公認会計士試験は誰でも受験可能
公認会計士になるためには、国家試験である公認会計士試験に合格することが必要です。この試験は、短答式試験(財務会計論、管理会計論、監査論、企業法)と、論文式試験(必須の4科目:会計学、監査論、企業法、租税法と、選択科目1科目:経営学、経済学、民法、統計学の中から選ぶ)という2つの段階から構成されています。
受験資格に特別な制限はなく、国籍や年齢、性別にかかわらず誰でも受験できます。また、3年間の実務経験を積み、原則として3年間の実務補修所で必要な単位を取得し、修了考査に合格することで、日本公認会計士協会に公認会計士として登録されることが可能になります。
試験の難易度は非常に高い
公認会計士試験の難易度は、近年7〜9%程度で推移しています。例えば、令和5年度の合格率は7.6%です。公認会計士試験は、税理士試験とは異なり、科目ごとに分けて受験することはできず、1年以内に5科目全てを受験し、合格する必要があります。
そのため、公認会計士試験に合格するためには、まとまった時間を試験勉強に充てるか、効率的に学ぶ方法を見つけることが重要です。
合格に必要な勉強時間
公認会計士になるためには、約3000時間の学習が必要とされています。もし1年で合格を目指すのであれば、1日あたり約10時間の勉強をする必要があります。
合格者の半数が学生であるのは、社会人と比較して勉強に集中できる時間を確保しやすいためかもしれません。
公認会計士が活躍できる求人をご紹介!
公認会計士試験に合格した後の活躍の場
監査法人
監査法人での主要な業務は、企業の財務諸表の監査です。また、内部統制の監査やIFRS(国際財務報告基準)の導入支援も行っています。「数字の詳細な確認が得意」「国際的な業務に興味がある」と感じる方に適しています。
会計事務所
税理士法人や会計事務所では、税務申告や税務相談、経営コンサルティングなど多岐にわたる業務に携わります。「詳細な法律や規制を理解し、それを活かしてクライアントを支援することに興味がある」という方に適しています。
コンサルティングファーム
コンサルティングファームでは、経営戦略などに関して、公認会計士としての専門知識を活かした助言を提供します。「新たな課題に対して創造的な解決策を見出すのが得意で、変化を楽しむことができる」という方に向いています。
公認会計士が行う意外な仕事内容
・株式上場支援業務 (IPO): 企業の新規株式公開(IPO)に向けた準備を支援します。具体的には、上場基準の適合性を確認し、内部統制を強化し、財務諸表の正確性を確保することが含まれます。公認会計士は、企業が円滑に上場できるよう、多方面でサポートを提供します。
・財務デューデリジェンス: 財務デューデリジェンスは、財務や会計に関する専門的な知識と技術が必要とされるプロセスであり、通常、公認会計士に依頼されることが多いです。ここでは、財務デューデリジェンスにおける公認会計士の専門知識とスキルの重要な役割についてまとめます。
・M&A支援:M&Aにおける公認会計士の役割と業務の中で最初に挙げられるのは、企業価値評価の算定です。売却する企業の適切な企業価値を評価するために、M&Aの初期段階で実施されます。
評価方法は複数存在し、財務状況や関連業界のトレンド、技術やノウハウなどを考慮して最適な方法を選択する必要があります。算定された企業価値は、売却企業と買収企業の交渉の基盤となるため、公認会計士による信頼性の高いデータが求められます。
働き方を改善したいなら
「会計求人プラス」
「残業が多い」「テレワーク対応した職場で働きたい」と思っていませんか? 会計事務所・税理士事務所で働き方を変えたいなら、専門の転職・求人サイト「会計求人プラス」がおすすめです。
公認会計士が活躍できる求人をご紹介!
公認会計士はAIによって消える職業?
会計業界でもAIは普及していく
公認会計士の業務がAIに置き換わる可能性は80%以上とされています。これは、AI(人工知能)やロボット、RPAツールを活用することで、効率的かつ低コストで行える作業において、人件費の削減が避けられないと考えられているためです。
公認会計士が完全に不要とはならない
製造業では、ロボットを積極的に導入することで業務の効率化が進んでおり、GPT技術を基にしたAIツールの発展により、さまざまな業界で変革が始まっています。しかし、業務が高度で複雑な場合や、人間の柔軟な意思決定が求められる場面、感情に関する領域などについては、AIによる代替の可能性が低くなります。
したがって、現行の業務体制や対応業務の将来性を考える際には、AI技術との親和性に注目することが重要です。
会計の最高峰!公認会計士を目指ざそう
公認会計士は、監査の専門性を通じて社会経済活動全体の機能性を保証する重要な職業です。公認会計士試験は非常に難易度が高く、合格率も低いため、合格するには 相当の努力が求められます。しかし、公認会計士として働くようになると、高い収入と幅広いキャリアの選択肢が得られることも事実です。
監査法人で昇進を果たすことや、コンサルティングファームでクライアントのニーズを最大限に引き出すこと、またはベンチャー企業を立ち上げて経営者に転身するなど、多様な可能性が広がっています。このように、公認会計士は「現状に満足せず、さらなるハイレベルなビジネスチャンスを追求したい」という方に非常におすすめの職業です。受験勉強は厳しいものですが、それを超えるリターンが待っているので、興味がある方はぜひ挑戦してみてください。
「会計求人プラス」では、公認会計士を目指す人の転職も手厚くサポートしています。
働き方を改善したいなら
「会計求人プラス」
「残業が多い」「テレワーク対応した職場で働きたい」と思っていませんか? 会計事務所・税理士事務所で働き方を変えたいなら、専門の転職・求人サイト「会計求人プラス」がおすすめです。
公認会計士が活躍できる求人をご紹介!
投稿者情報

- 現役公認会計士・税理士
- 公認会計士資格を取得しており、現役で公認会計士として仕事をしています。税理士資格も持っていますので、財務、会計、税務、監査などの専門的な業務経験も豊富にあります。ライターとして5年以上執筆しており、専門的でリアルな内容が好評いただいています。
最新の投稿
 公認会計士試験2025.06.02社会人から公認会計士を目指す!勉強法やメリットを解説
公認会計士試験2025.06.02社会人から公認会計士を目指す!勉強法やメリットを解説 転職ハウツー2025.06.02経営コンサルタントに必要な資格とは?おすすめの資格と必要性を解説
転職ハウツー2025.06.02経営コンサルタントに必要な資格とは?おすすめの資格と必要性を解説 公認会計士2025.02.03会計士にITスキルは必要か?ITを活かした業務とキャリアアップ
公認会計士2025.02.03会計士にITスキルは必要か?ITを活かした業務とキャリアアップ 経理2024.12.23経理の転職で求められる年齢別のスキルとは!20代と30代を比較
経理2024.12.23経理の転職で求められる年齢別のスキルとは!20代と30代を比較