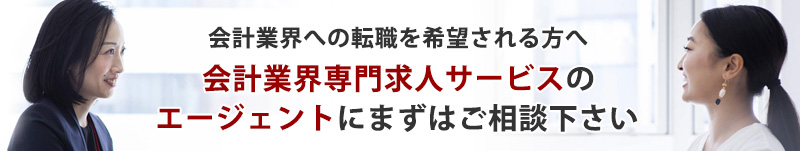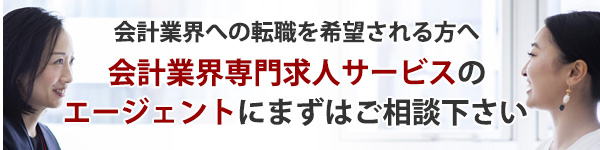行政書士の資格を活かした転職先、就職先を探す重要なポイントとは
2023/10/27
行政書士とは、「街の法律家」ともいわれることがある行政書士法に基づく国家資格です。
主な仕事としては行政機関に提出する許認可申請(事業をはじめる場合の届出や登録など)に必要な書類の作成および提出を、依頼者に代わって行います。
他にも、各種行政手続きに関する相談やアドバイスなども行っています。行政書士は国家資格ですが、年齢・学歴を問わず誰でも受験できるため、毎年多くの受験者がチャレンジしています。
この記事では
- 行政書士に合格するための勉強法が知りたい
- 合格後の資格を活かせる就職先を知りたい
- 自分に合った就職先を見つけるポイントを知りたい
という方に向けて解説します。これを読めば、行政書士になるための勉強法や、就職先を探すコツが分かります。これから行政書士を目指す方や、資格を取得して、就職先を探している方はぜひ最後までご覧ください。
会計事務所や経理へ転職をするなら会計業界専門の転職サイト「会計求人プラス」が最適!
完全無料の会員登録はこちらから
コンテンツ目次
行政書士の資格を活かせる転職・就職先
行政書士は、総務省が管轄する国家資格で、国民と行政とのパイプ役を担う「法律の専門家」です。
行政書士が担う仕事には、主に
- 国や地方公共団体に提出する書類作成(建設業許可・会社設立・帰化申請など)
- 許認可申請の代理(作成した書類を依頼主に代わって官公署に提出)
- 上記の種類作成に関する相談業務
の3つがあります。
国民には理解が難しい行政手続きを代理で行ってくれるので「街の法律家」とも言われています。職域が幅広い上に、資格があれば年齢に関係なく長く続けられることから、毎年40,000名以上がチャレンジする人気の資格です。ところで、行政書士の資格を活かせる就職先には、どのようなところがあるのでしょうか。
参照元:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和3年度行政書士試験実施結果の概要」
行政書士事務所
代表的な就職先のひとつに行政書士事務所があります。事務所で働く行政書士を「使用人行政書士」と言い、事務所で勤務するには、行政書士連合会に登録をする必要があります。
開業した行政書士のもとで働きますので、将来的に自分も独立したいと考えるなら、実務業務をこなしながら、独立するためのノウハウも身に付けられます。行政書士事務所では、主に許認可申請、会社設立、帰化申請などの手続きに必要な書類の作成や提出代行などの業務を行います。
弁護士事務所
弁護士事務所で「パラリーガル」として働く方法もあります。パラリーガルとは、弁護士の指示のもと、法律に関する業務を行うアシスタントのことを言います。医者に看護婦が必要であるように、弁護士にはこのパラリーガルの存在が欠かせません。主な仕事には、事件に関係する法令や凡例の調査、契約書や書証などの法律文書の作成・校閲などがあります。
企業の法務部
企業での法律に関わる問題を処理する「法務部」で働くこともできます。特に建設業や不動産業では、建物を作ったり土地の売買をしたりする上で、行政に提出する必要がある書類がたくさん存在するため、このような時に行政書士の資格が活かせます。

行政書士合格に向けた勉強法
行政書士は、毎年40,000名もの方々が受験している人気の資格です。資格を取得すれば、年齢に関係なく長く働くことができる魅力があります。しかし、その合格率は10%前後と合格までの道のりは近いとは言えません。では、行政書士に合格するには、どのように勉強をすれば良いのでしょうか。ここでは、合格に向けた勉強法について紹介します。
合格に向けた勉強法とは
行政書士になるには、毎年1回行われる「行政書士試験」に合格しなければなりません。「行政書士の業務に関する法令」と「行政書士の業務に関する一般知識」に問題が分けられ、全部で60問に回答します。
一朝一夕で合格できるほど甘くはありませんので、毎日時間を確保して、継続的に勉強する必要があります。合格するには、600~700時間は必要と言われており、期間にすると半年から1年くらいになります。試験時期までの長くて1年、短くても半年のスケジュールを立てる必要があります。
行政書士が活躍できる求人をご紹介!
スケジュールの立て方
スケジュールはどのように立てたら良いのでしょうか。上手なスケジュールの立て方は(1)6ヶ月(2)月(3)時間と細分化することです。ここでは、勉強期間を「半年」と設定し、どのタイミングで何の勉強をするのか具体例を紹介します。
(1)半年スケジュール
●1ヶ月目 : 憲法/民法
●2~3ヶ月目 : 民法/行政法
●4ヶ月目 : 商法/会社法/過去問
●5ヶ月目 : 一般知識/過去問/記述対策
●6ヶ月目 : 模擬試験/過去問/本試験
まず、上記のように半年間のおおまかなスケジュールを立てます。本試験から逆算してスケジュール組みをすることが大切です。半年間のスケジュールを決めたら、次に1ヶ月目のスケジュールに落とし込みます。
(2)1ヶ月のスケジュール
●1ヶ月目
・1日(月): 憲法
・2日(火): 憲法
・3日(水): 憲法
・4日(木): 憲法
・5日(金): 憲法
・6日(土): 憲法
・7日(日): 憲法
…
・31日(水): 民法
そして最後に1日ごとのスケジュールを立てます。
(3)1ヶ月のスケジュール
●1日(月)
・憲法の勉強:テキスト読み(30分)/過去問の確認(30分)/憲法のテキスト読み込み(30分)/過去問の確認(30分)など
次に2日(火)、3日(水)と日ごとの勉強時間を決めていきます。このように、試験月から逆算しておおまかなスケジュールを立て、細分化して計画すると、いつ、何をすればいいのか明確になり、計画的に勉強をしやすくなります。
しかし、中には働きながら試験にチャレンジする方もいるでしょう。働きながら勉強する時間を作らなければなりませんので、そのような場合は、まず自分の1日の行動を書き出し、空いている時間を勉強にあてましょう。電車での移動時間も勉強時間に使えます。スマホを活用したeラーニングや、過去問を持ち歩き勉強する方法など、スキマ時間を有効活用しましょう。
努力の甲斐が実り、晴れて合格すれば、上記で紹介したように行政書士事務所、弁護士事務所、企業の法務部などの就職への道が開けます。次に行政書士としての就職先を選ぶ上でのポイントを紹介します。

行政書士の転職・就職先を選ぶ上でのポイント
行政書士として活躍したい分野で選ぶ
転職・就職先を選ぶ上でのポイントは、まず、「行政書士として活躍したい分野」で選ぶことです。行政書士は独立開業する人も多いことから、将来的に独立したいなら、実務経験を積むことも大切ですが、独立に向けたキャリアをどの分野で積めば良いのかを計画的に考える必要があります。行政事務所と一口に言っても、以下のように業務内容は多岐に渡ります。
<行政書士事務所が行う主な業務内容>
- 許認可申請…建設業、飲食店の開業などに必要な許認可申請書類の作成
- 遺言、相続…遺言書や遺言分割協議書の作成
- 国際関係業務…日本国籍の取得希望者の帰化申請に必要な書類の作成
- 民亊法務…特定商取引法などで定めるクーリングオフの手続きにかかる資料作成
- 会社設立…会社設立における定款作成など
- 知的財産権…著作権登録の申請サポート 他
行政事務所によっても、それぞれ得意分野がありますので、将来独立するなら、どの分野にチャレンジしたいのか、そのためにはどんなキャリアが必要なのかを考えた職場選びを行いましょう。
代表者との相性(ビジョン・考え方)で選ぶ
行政事務所の多くは個人が経営し、所属する人数も少ないケースが多いです。自分の将来的なキャリア形成に合った事務所を探すことも大切ですが、そもそも長く働ける「職場環境」であるかどうかが最も肝心です。個人経営者が多いからこそ、事務所が掲げるビジョンや、代表者の考え方、人柄などの「相性」とマッチするかどうかがポイントです。
せっかく就職が決まっても、事務所のリサーチ不足のため、「思っていた環境と違っていた…」というミスマッチは、雇用する側・される側のお互いにとっても喜ばしいことではありません。自分に合った事務所選びのためにも、代表者との相性も考慮しましょう。
行政書士が活躍できる求人をご紹介!
ノウハウが知りたいなら
「会計求人プラス」
転職成功のポイントを押さえて、理想のキャリアを築きませんか?会計業界に特化した「会計求人プラス」の転職エージェントがあなたの希望に合った求人を見つけ、成功へのステップをサポートします。
行政書士の求人事情
上記では行政書士の転職・就職先を紹介しましたが、実際の求人状況はどうなのでしょうか。ここでは、行政書士の転職・就職事情について、「一般企業」と「行政書士事務所」とに分けて紹介します。
一般企業
どのような企業でも商品開発や販売において、官公署への商品認可や販売許可などの行政手続きが必要になります。手続きに必要な書類の作成や提出方法は、一般的にはなかなか理解し難いため、行政書士のスキルが活かせられます。
このような場合、行政書士の有資格者の求人が出ることがあります。また、小規模な企業では、正社員としてではなく、パート勤務としての募集を行っているところがあるので、子育て中の女性や介護中の主婦の方に向いている求人がされることがあります。
求人情報では性別を特定することがありませんから、詳細を確認し希望職種に行政書士が含まれていること、勤務条件がパート系であること、女性の入社実績があることなどを確認しましょう。
行政書士事務所
行政書士事務所では、クライアントへのスピーディーな対応が必要になりますので、即戦力となる人材が求められます。ただし、全体的には求人数は、地域によってバラつきが見られます。というのも、行政書士の求人は会社数の多いエリアに集まるため、地方よりも都市部の方が多い傾向にあります。
行政書士の転職・就職の難易度は?
行政書士の資格を取ること自体、転職・就職するにあたって有利にはなります。しかし、応募する人に対する求人数が、そもそも少ない傾向にあるため、資格を持っていれば、誰でも就職ができるかと言えばそうとは言い切れません。
行政事務所は個人経営が多いため、募集がはじまると有資格者を中心に応募が集中しますので、すぐに締め切りになってしまいます。
多くのスタッフが雇える大規模な事務所も少ないので、すぐに就職ができるとは言い難い実情もあります。一般企業においても、総務部や法務部でのニーズはあるものの、行政書士は独立志向の方が取得する傾向にあるため、「雇用しても将来的に独立されるのでは」という懸念もあり、積極採用になりにくい側面もあります。
前述でもお伝えしましたが、求人情報の探す範囲を広げるというのも非常に有効な手段です。
会計事務所の求人で行政書士の求人を掲載しているケースも多く見受けられます。
会計業界も人手不足が深刻化していること、これまでの一般的な業務だけではなく多角的に業務を行っている事務所が多いことなどから、行政書士しゃ社労士などの国家資格を有している人材を募集することも増えているのです。
特に、その他士業の資格をもっている実務経験者を会計事務所が雇用するのは難しいこともあり、会計業界未経験者であっても採用される可能性が高まっています。
行政書士が活躍できる求人をご紹介!
行政書士が転職・就職活動で注意すべきこと
最後に転職・就職にあたっての注意点を紹介します。せっかく難易度の高い国家資格を取得をしたのですから、資格を活かして希望している転職・就職ができるよう、以下のポイントに注意しましょう。
●履歴書の書き方
履歴書は、転職・就職希望先とのファーストコンタクトとなる大切な書類です。誤字・脱字に注意することは当たり前ですが、中でも最も注力すべきは「志望動機」です。ここで注意しなければならないのは、一方的な自己アピールにならないことです。相手側の企業ビジョンや経営方針に合わせて、志望動機を組み立てることが得策です。
そのためには、相手企業がどんな人材を欲しているのかをしっかりリサーチしておきましょう。行政書士としてのスキルは最低限持っていること、相手側が求める人材であることをアピールする志望動機にするのがポイントです。
●面接の受け方
書類選考を通過したら、次は面接です。面接では面接官から質問されることに適切に答えられるように、想定される質問を洗い出しておきましょう。当然、志望動機についても尋ねられますので、履歴書で書いた志望動機をさらに深掘りした答えを準備しておきましょう。
まとめ
これまでの記事で行政書士の転職・就職事情についてご理解いただけたかと思います。
行政書士は独占業務もあり、「官公署に提出する書類および事実証明・権利義務に関する書類の作成代理」となっています。
実際に行政書士が取り扱える書類の数はかなりの数があります。許認可申請・権利義務関係・事実証明・などなど多岐にわたるのです。多くの分野に関わることができることは行政書士の強みと言えるでしょう。
とはいっても、他の士業、例えば税理士や、司法書士、社労士(社会保険労務士)などで定められている独占業務については、行政書士の資格を有していても行うことができません。
本来、もっとも行政書士の国家資格が活かせることになるのは、他の国家資格とのダブルライセンスを取得していることでしょう。
業務の幅が大きく広がり、それぞれの実務経験を有していれば、転職する際にも非常に有利になりますし、年収アップも十分に狙えるでしょう。
行政書士事務所で堅実に年収をあげていくこともいいのですが、異業種などへ目を向けてキャリアアップを図ることも視野にいれて転職・就職活動をするといいでしょう。
もし、具体的にどのように求人を探せば良いのか迷ってしまっていたり、業務の都合で企業分析を細かくする時間を割けないなどのご事情がある場合は、転職エージェントに相談されるのも有効です。
貴方の現在のスキル、キャリアを分析してくれて、細かな条件などを伝えれば適した求人を紹介してくれます。
転職エージェントが紹介してくれるのは、一般的に公開されていない非公開求人ばかりですので、条件があえば書類選考が通る可能性はグッとあがります。
特に行政書士事務所以外の異業種への就職・転職を希望される場合は、会計業界専門の転職エージェントがおすすめです。
会計事務所や一般企業のバックオフィス系に特化している求人を扱っているので、行政書士の資格を有していることが有利になりますし、会計業界での実務経験がない未経験の人であれば、業界のことを詳しく教えてくれます。
転職エージェントは貴方の最適な転職・就職先を探すことが仕事ですから、非常に親身になって対応してくれるでしょう。
会計求人プラスでは、会計業界専門の公開求人情報をあつかっている転職・就職サイトと、非公開求人のみを扱っている転職エージェントの2つのサービスで、貴方の転職・就職を全力でバックアップします。
ご相談は完全に無料ですので、まずは個別転職相談会で相談してみませんか?
⇒個別転職相談会はこちら
から
ノウハウが知りたいなら
「会計求人プラス」
転職成功のポイントを押さえて、理想のキャリアを築きませんか?会計業界に特化した「会計求人プラス」の転職エージェントがあなたの希望に合った求人を見つけ、成功へのステップをサポートします。
投稿者情報

-
会計事務所や税理士事務所、一般企業の経理職など会計業界の求人情報が豊富な「会計求人プラス」を運営し、多くの求職者の方、会計事務所の採用ご担当者とお話をさせていただいています転職エージェントです。
異業種から会計業界へ転職を希望している方をはじめ、これから税理士や公認会計士を目指す未経験の方や、今までの税務・会計の知識・経験を活かして年収アップやスキルアップしたい方などを全力で支援しています。
その一環として、会計業界でお役に立つ情報をお届けするために10年以上記事を書いています。是非、会計業界で働く人が楽しく、知識を得られるような情報をお伝えできればと思います。
最新の投稿
 転職ハウツー2025.06.29経理に転職したい会計事務所勤務者必見!成功のポイントと注意点を解説
転職ハウツー2025.06.29経理に転職したい会計事務所勤務者必見!成功のポイントと注意点を解説 士業2025.06.25不動産鑑定士試験の難易度はどのくらい?難しすぎると言われる理由を解説
士業2025.06.25不動産鑑定士試験の難易度はどのくらい?難しすぎると言われる理由を解説 経理2025.06.02経理の転職に役立つ資格はこれ!キャリアアップにおすすめ資格を解説
経理2025.06.02経理の転職に役立つ資格はこれ!キャリアアップにおすすめ資格を解説 税理士2025.06.02生成AIを活用して税理士の働き方が変わる?税理士業務への影響を解説
税理士2025.06.02生成AIを活用して税理士の働き方が変わる?税理士業務への影響を解説