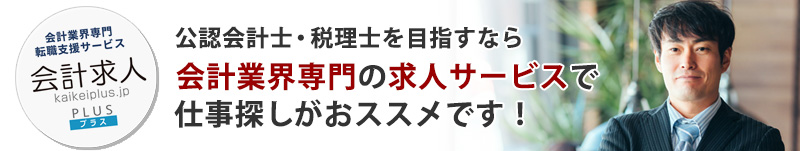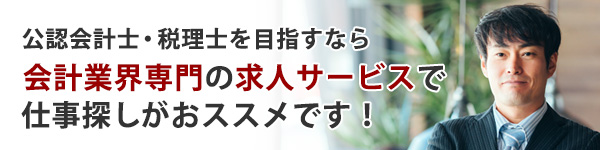社労士はなぜ難しい?難易度から他資格との比較、キャリアパスまで紹介
社労士試験の難易度について合格率や学習時間、受験資格などの観点から、よく比較される行政書士試験や宅建試験などとの違いを含めて解説していきます。
社労士試験の学習を始める際には、特に難易度が高い部分をポイントとして事前に把握しておくことが、効果的な勉強計画・勉強方法・学習スケジュールを立てるために非常に重要です。モチベーションの維持にも役立つでしょう。
確実に合格を目指すために、ぜひこれらの情報を参考にしていただくことをおすすめします。
コンテンツ目次
社労士(社会保険労務士)とは?
社会保険労務士(社労士)は社会保険労務士法に基づく国家資格であり、その試験内容として、労働者が企業に入社してから退職するまでの人事や労務に関する広範な知識が問われます。この資格を取得するためには、労働基準法をはじめとした各種法令に関する深い理解が求められます。社労士は、こうした専門的な知識を駆使して、書類作成や必要な手続きを実務で行います。
社労士試験の難易度
過去5年間の社会保険労務士試験の合格率は5.3%から7.9%の間で変動しています。最も高い合格率は2021年度の7.9%で、最も低い合格率は2022年度の5.3%でした。
受験者数合格者数の推移は以下の通りです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 43,174人 | 2,974人 | 6.90% |
| 2023年度 | 42,741人 | 2,720人 | 6.40% |
| 2022年度 | 40,633人 | 2,134人 | 5.30% |
| 2021年度 | 37,306人 | 2,937人 | 7.90% |
| 2020年度 | 34,845人 | 2,237人 | 6.40% |
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
社労士が活躍できる求人をご紹介!
社労士試験が難しい理由
社会保険労務士試験が「難関」とされるのはなぜでしょうか。ここでは、その難易度の高さが語られる背景について、詳しく見ていきましょう。
受験科目が多い、試験範囲が広い
社会保険労務士試験の難しさの一因として、試験範囲の広さが挙げられます。「労働法」と一言で言ってもその中には労働基準法や労災保険法など多岐にわたる法律があり、それぞれ内容や手続きに違いがあります。合格を目指すためにはこうした各法律について十分に理解し、対策することが求められます。
さらに、出題範囲は労働法だけにとどまらず健康保険法や国民年金法などの社会保険関連法も含まれています。労務に関連する一般常識も試験対象となるため習得すべき知識量は非常に多く、学習負担が大きい点が特徴です。
科目ごとの合格基準が設定されている
社労士試験の合否は全体の得点で判断されるわけではありません。実際には各科目別に「合格基準点」が設定されており、これがいわば細かな足切りラインとして作用します。
たとえ総合得点が高かったとしても、どれか1科目でも基準点に達していなければ不合格となります。合格した科目について翌年に成績を持ち越せる制度もないため、再受験の際には再び全科目を受験する必要があります。
このように幅広い分野を網羅する力に加え、各科目で安定して得点できる実力が求められることが社労士試験が難関とされる大きな要因の一つです。
独学でも合格できないわけではないでしょうが、予備校の講座や通信講座を利用するのが通常であると言えます。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
社労士が活躍できる求人をご紹介!
社労士試験と他資格を比較
社労士試験と行政書士試験の難易度を比較
社会保険労務士試験と行政書士試験を比較した場合、一般的に社会保険労務士試験のほうが難易度は高いとされています。
【合格率の違い】
合格率を見ると社会保険労務士試験は例年5〜7%前後で推移している一方、行政書士試験はおおむね10%程度の合格率となっています。この数値からも、社労士試験の方が合格のハードルが高いと言えるでしょう。
【合格基準の違い】
試験制度の面では社労士試験は各科目に個別の基準点が設けられており、1科目でも基準点に届かなければ不合格になります。行政書士試験にはそのような科目ごとの足切りはなく、他の科目で得点を補うことが可能です。
この違いからも社労士試験の方が厳格な合格基準を採用していることがわかります。
【試験範囲の違い】
出題範囲に関しては、社労士試験は労働関係法や社会保険に関する法律など、特定分野に絞って深く出題される傾向があります。行政書士試験はより幅広い分野から出題されますが、一つひとつの深掘り度合いは比較的浅めです。
つまり、社労士試験は専門性が高い知識が求められるのが特徴です。
【法改正の影響】
社労士試験では頻繁に行われる法改正や最新の統計情報が反映されるため、それらへの対応も欠かせません。試験実施年の4月までの法改正内容が試験に含まれるため、直前期まで最新情報への対応が求められます。
それに対し、行政書士試験では法改正の影響は比較的軽微であることが多いとされています。
これらの点を総合的に見ると、社会保険労務士試験の方が難易度が高いと判断されやすい理由が理解できるでしょう。
社労士試験と税理士試験の難易度を比較
税理士とは、税務に関わる各種手続きの代理などをおこなうことが認められた専門資格です。税理士資格を取得すれば、納税に関する申告業務や確定申告の代理も行うことが可能になります。
税理士試験では会計分野および税法分野に関連した科目が出題され、全部で11科目あるうち5科目に合格することで資格を得られます。試験では計算力を要する実践的な問題や論理的な思考力を試される内容が多いため、難関資格の一つとされています。
税理士が税務を専門とするのに対し、社会保険労務士(社労士)は労働・社会保険手続きなど労務分野に特化した資格です。社労士試験でも労働者に関連する税に関する知識が一部問われる可能性はありますが、あくまで限定的です。
社労士試験は主に法律の知識や条文の理解・記憶が求められる試験であり、その点で税理士試験と比べると難易度はやや低めといえるでしょう。
社労士試験と中小企業診断士の難易度を比較
中小企業診断士試験は、一般的に社会保険労務士(社労士)試験よりもやや難易度が高いとされています。
合格率はおおよそ5%前後、必要な学習時間も約1,000時間と社労士試験とほぼ同じ程度ですが、中小企業診断士試験には「口述試験」がある点が特徴です。この口述試験では知識の有無だけではなく受験者のプレゼン能力や対話力など実務的な対応力が問われるため、難易度が高い要因のひとつとなっています。
さらに、この試験では経営全般に関する広い知識が求められます。経営戦略・財務・マーケティング・人事管理など幅広い分野をカバーしており、学習量も非常に多くなります。
加えて実際に企画・財務・マネジメントなどの実務を担いながら受験を目指す人が多いため、試験のレベル自体も高く受験者の質も比較的高いと言われています。
社労士試験と宅建士試験の難易度を比較
【合格率の比較】
合格率の面から見ると社会保険労務士試験は毎年5〜7%程度で推移しているのに対し、宅建試験はおおよそ15〜17%前後の合格率となっています。この数字からも分かる通り、社労士試験の方が宅建試験よりも合格が難しいと判断できます。
【試験科目の比較】
社会保険労務士試験では労働関連法規や社会保険制度など、10科目にわたる広範な知識が求められます。
宅建試験は「権利関係」「宅建業法」「法令制限」「税・その他(免除科目)」の4分野に分かれており、出題範囲も比較的コンパクトで日常生活に関わる内容が多いため学習しやすいという面があります。
この点を踏まえると、社労士試験の方が試験範囲の広さや専門性において難易度が高いと言えるでしょう。
【出題傾向の比較】
出題内容の違いにも注目すると、社会保険労務士試験はその年の4月までに行われた法改正や最新の統計情報に関する問題が含まれる場合があり、常に最新の情報に対応した学習が求められます。そのため過去問だけでは不十分なことも多く、幅広い対策が必要です。
対照的に宅建試験は過去問の傾向を踏襲した問題が多く出題されるため、過去問対策を徹底すれば比較的合格しやすい傾向があります。
このように出題形式や内容から比較しても、社会保険労務士試験は宅建試験に比べて難易度が高いといえるでしょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
社労士が活躍できる求人をご紹介!
社労士試験の概要
受験資格
社会保険労務士(社労士)の試験を受けるためには、いくつかある受験資格のうちいずれか一つを満たしている必要があります。主に受験資格は次の3つに分類されます。
まず一つ目は「学歴要件」です。これは、短期大学や高等専門学校、あるいはそれ以上の学歴を持っていることが条件となります。
次に二つ目は「実務経験」による受験資格です。指定された業種において通算3年以上の実務経験が必要です。たとえば、公務員としての勤務や弁護士法人での事務職などが該当します。
最後に三つ目は「国家試験等の合格」です。厚生労働大臣が認めた国家試験に合格していることが条件であり、たとえば司法試験予備試験や行政書士試験などの合格がこれに含まれます。
試験科目と配点
■選択式試験/試験時間:80分
【出題科目および配点】
| 科目 | 出題数(配点) |
|---|---|
| 労働基準法・労働安全衛生法 | 合計5問(労働基準法3問・3点、労働安全衛生法2問・2点) |
| 雇用保険法 | 5問(5点) |
| 労務管理および労働に関する一般常識 | 5問(5点) |
| 社会保険に関する一般常識 | 5問(5点) |
| 健康保険法 | 5問(5点) |
| 厚生年金保険法 | 5問(5点) |
| 国民年金法 | 5問(5点) |
| 合計 | 40問(40点) |
※「労働基準法」と「労働安全衛生法」は一体化した形式での出題(混合問題)となります。
■択一式試験/試験時間:210分
【出題科目および配点】
| 科目 | 出題数(配点) |
|---|---|
| 労働基準法・労働安全衛生法 | 合計10問(労働基準法7問・7点、労働安全衛生法3問・3点) |
| 労災保険法・労働保険料徴収法 | 合計10問(労災保険法7問・7点、労働保険料徴収法3問・3点) |
| 雇用保険法・労働保険料徴収法 | 合計10問(雇用保険法7問・7点、労働保険料徴収法3問・3点) |
| 労務管理および労働に関する一般常識 | 5問(5点) |
| 社会保険に関する一般常識 | 5問(5点) |
| 健康保険法 | 10問(10点) |
| 厚生年金保険法 | 10問(10点) |
| 国民年金法 | 10問(10点) |
| 合計 | 70問(70点) |
合格基準
社労士試験では選択式と択一式の試験の総得点に加えて科目ごとにも合格基準点が設定されており、全体で6〜7割の得点を達成する必要があります。
「救済措置」と呼ばれる合格基準点の調整が行われる場合もありますが、最初からその救済措置に頼ることなくすべての科目で均等に得点を取れるように備えることが大切です。
調整は年度ごとに行われ選択式では40%以上、択一式では60%以上の得点が求められ、さらに各科目で合格基準点をクリアすることが求められます。
試験日程
社会保険労務士試験は、毎年8月の第4日曜日に行われます。
社労士試験に合格するための勉強時間
この試験を受けるには、最低でも約800時間から1000時間の学習時間が必要だと言われています。
仕事をしながら勉強を進める場合、1日の勉強時間の目安を見てみましょう。
平日2時間、休日(2日)5時間ずつの場合 ⇒ 1年ほどかかる計算です
平日3時間、休日(2日)7.5時間ずつの場合 ⇒ 約8ヶ月かかる計算です
平日5時間、休日(2日)10時間ずつの場合 ⇒ 約6ヶ月かかる計算です
社労士の年収やキャリアパス
高い年収が期待できる
社労士の年収は500万円から700万円の範囲と言われており、勤務年数や業務内容によって幅があるため具体的な金額を一概に算出するのは難しいです。ただし、医師や弁護士などのような難関国家資格を除けば社労士はかなり高い年収が期待できる資格と言えるでしょう。
また、社労士には「開業」と「勤務」の2つの働き方があり、資格取得後にどちらを選択するかの自由度があります。
社労士の平均年収を見ると、その資格が社会的にどれだけ重視されているかが分かります。高い平均年収は社労士資格の人気が長年続いている理由の一つと言えるでしょう。
キャリアパス
・社労士事務所
個人や企業の人事に関する課題を解決する社労士事務所は、社労士にとって最も一般的な職場の一つです。
社労士事務所では社会保険や労務相談など専門的な業務に特化しているため、社労士としての経験をしっかりと積みたい方や将来独立して社労士事務所を開業したい方に最適な職場です。
ただし、社労士事務所では即戦力を求めることが多いため、実務未経験で社労士試験に合格した方が転職を考える際は特定の条件にこだわりすぎず、幅広い求人に応募することを心に留めておきましょう。
・一般企業
社労士試験に合格すると、人事や総務を中心としたバックオフィス業務の広範な範囲を担当できるようになります。一般企業で働く場合、社労士として専門的な業務を行うというよりも主に人事部門や総務部門に所属して自社の労務関連業務を担当することが一般的です。
一般企業で働くメリットとしては、企業数が社労士事務所よりも多いため求人数も相対的に増え、希望の条件での勤務がしやすい点が挙げられます。また、収入面でも安定性が高いことが魅力的です。
ただし、一般企業で働く場合は社労士業務以外の業務も兼務することが多いため、社労士としての実務経験を積みたい方が一般企業に転職を検討する際は業務内容を十分に確認することが重要です。
・コンサルティング会社
コンサルティング会社では採用コストの見直しや法改正に対応するなど、人事に関するさまざまな相談を受ける役割を担っています。
中には社労士事務所を併設しているコンサルティング会社もあります。このような環境で働くと社労士としての経験を積むだけでなく、クライアントの経営に関わる機会も得られるという特徴があります。
計画的な学習と明確なキャリアプランで社労士を目指す
社労士試験は毎年合格率が6~7%と非常に低く、勉強時間もおおよそ800~1000時間と中程度の時間を要するため難関国家試験の一つとして位置付けられています。したがって、社労士試験に合格することは非常に素晴らしい成果と言えるでしょう。
ただし、社労士試験は決して合格不可能な試験ではありません。
数年を見越した学習計画を立て、計画的に勉強を進め、効率的にテキストや講義を活用すれば十分に合格の可能性があります。
ぜひ、将来性のある社労士試験の合格を目指して挑戦してみてください。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
社労士が活躍できる求人をご紹介!
投稿者情報

-
会計事務所や税理士事務所、一般企業の経理職など会計業界の求人情報が豊富な「会計求人プラス」を運営し、多くの求職者の方、会計事務所の採用ご担当者とお話をさせていただいています転職エージェントです。
異業種から会計業界へ転職を希望している方をはじめ、これから税理士や公認会計士を目指す未経験の方や、今までの税務・会計の知識・経験を活かして年収アップやスキルアップしたい方などを全力で支援しています。
その一環として、会計業界でお役に立つ情報をお届けするために10年以上記事を書いています。是非、会計業界で働く人が楽しく、知識を得られるような情報をお伝えできればと思います。
最新の投稿
 転職ハウツー2026.01.20会計事務所は未経験でも目指せる?仕事内容・資格・年齢別の成功ポイントとは
転職ハウツー2026.01.20会計事務所は未経験でも目指せる?仕事内容・資格・年齢別の成功ポイントとは 公認会計士2026.01.19もう限界…監査法人を辞めたい人が知っておくべき転職戦略と準備のすべて
公認会計士2026.01.19もう限界…監査法人を辞めたい人が知っておくべき転職戦略と準備のすべて 経理2026.01.19経理にMOS資格は必要?現場の声と転職成功の秘訣を紹介
経理2026.01.19経理にMOS資格は必要?現場の声と転職成功の秘訣を紹介 成功者インタビュー2025.12.11朝日税理士法人 城南支社 成功者インタビュー 2025年度
成功者インタビュー2025.12.11朝日税理士法人 城南支社 成功者インタビュー 2025年度