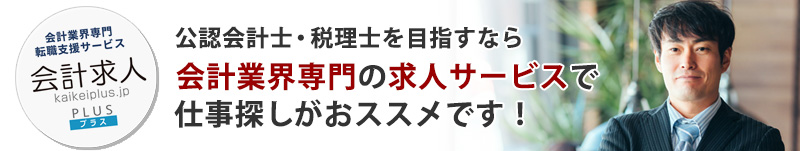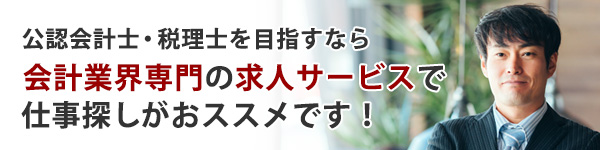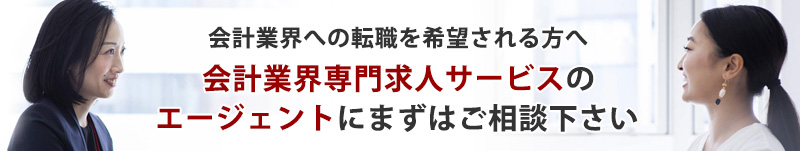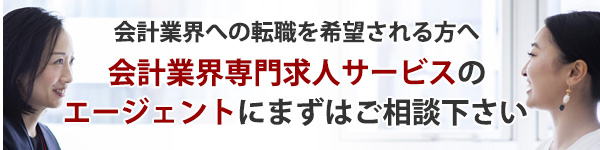税理士の転職は何歳まで?年齢よりも重視されるものとは
税理士試験は非常に難易度が高く、長時間の学習が必要なため、合格するまでに何年もかかり、税理士登録できるのは30代を超えることが多いです。しかし、そこで気になるのが「税理士資格を取得した後の転職活動で、年齢が不利に働くことはないのか」というポイントについてです。
一般的な会社では転職35歳限界説という話を耳にしたことがある人も多いと思います。実際の税理士や会計事務所でははいかがなのでしょうか。
そこで今回は、税理士の転職が何歳まで可能かという転職事情について、この記事で情報を 徹底解説します。
■□■□会計業界へ効率的に転職活動を進めるなら専門転職サイト「会計求人プラス」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□
コンテンツ目次
税理士の転職は何歳まで可能なのか
税理士業界において、転職に年齢の制限は存在するのでしょうか?結論として、「年齢が理由で転職できない」ということはほとんどありません。
転職先は「スキル」「実績」「人柄」「給与」など、採用条件に合うかどうかで判断するため、必要なスキルを持っていれば年齢に関係なく採用されることが多いです。ただし、年齢が上がるにつれて年齢別に求められるスキルや経験のレベルも高くなるのは事実です。
20代の転職

例えば、25歳前後ではポテンシャルが重視されるため、業界未経験者でも税理士試験の勉強中や1科目合格などで採用される可能性があります。25~30歳も税理士業界では「若手」に分類されますが、できれば1~2科目合格者であることや実務に役立つ資格はメリットとなります。
20代前半で税理士資格を取得できている人は稀で、貴重な存在となります。税理士試験は受験資格があることが取得年齢をお仕上げている要因でもありますが、2024年現在では一部は受験資格が撤廃されたりと、若年層でも資格取得を目指しやすい環境になりつつあります。
30代の転職
30歳でも税理士業界では「かなり若手」に入ります。異業種からの転職や未経験でもチャンスはありますが、理想的には会計事務所での経験や経理の経験、複数科目の合格、税理士試験合格、税理士資格があればより望ましいです。また、社会人としてのマナーや礼儀も重要視されます。
35歳を超えても税理士業界ではまだ若手です。しかし、この年齢になると、実務経験と税務知識の両方が求められ、さらにマネジメント能力が期待されます。優れたプレイヤーであるだけでなく、チームとの協力やリーダーシップも必要になります。この段階で要求は高くなりますが、スキルを積んできた人には転職のチャンスがあり、年収アップの可能性もあります。
40代の転職
さらに、40歳代や50代以上でも、税務知識や人間力、実務経験が豊富であれば、採用される可能性は十分あります。ただし、この年代では「ITツールを使いこなせるか」「デジタルトランスフォーメーション(DX)に対応できるか」が問われるようになります。「パソコンやスマホが苦手」「チャットツールやクラウドサービスに不慣れ」といった点があると、転職は難しくなるでしょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
税理士が活躍できる求人をご紹介!
税理士の転職に年齢が関係ない理由
資格取得までに時間がかかる
税理士資格は、取得までに長い時間を要する資格です。税理士試験に合格するためには、「会計学」に属する簿記論と財務諸表論の2科目に加え、「税法」に関連する科目(所得税法、法人税法、消費税法、酒税法、相続税法、国税徴収法、固定資産税、住民税、事業税)の中から3科目を選び、合計5科目の試験に合格する必要があります。簿記論と財務諸表論は必修で、税法の中では所得税法か法人税法のどちらかが必須となっています。
一般的には、税理士資格を取得するには約4,000時間の勉強が必要とされています。大学で税務に関する勉強をしていた人は、少し勉強時間を短縮できる場合もありますが、それでも数年にわたる努力が必要です。多くの場合、昼間は税理士事務所や企業で働きながら、少しずつ勉強を進める形になります。
税理士試験では、全ての科目を一度に合格する必要はなく、1科目ずつ合格を積み重ね、5科目がそろった時点で最終的に合格とみなされます。この科目合格制度が、資格取得に時間がかかる理由の一つでもあります。
試験合格までに年単位の時間がかかるため、税理士の平均年齢は自然と高くなります。日本税理士会のデータによると、登録税理士の中で最も多いのは60代で、30代や40代でも「若手」とされるのが現状です。このため、30代や40代、さらには50代の年齢層の転職も、税理士業界では珍しいことではありません。
税理士の平均年齢が高い
1つ目の理由は、「税理士業界全体の平均年齢が高いため、年齢が大きな障害にはならない」という点です。平均年齢が高い背景として、「定年後に税務署OBが税理士登録するケースが多い」「社会人になってから税理士試験に挑戦する人が大多数を占めている」「試験科目が永久に有効で、官報合格までに長期間かかることがある」といった要因が挙げられます。
その結果、税理士業界では40代でも若手と見なされることが多く、35歳を過ぎても年齢を理由に敬遠されることはほとんどないのです。
税務の知識と経験が重要
税理士の仕事で重要なのは、税務に関する知識と実務経験です。税制改正に対応する能力はもちろん、「各税法の趣旨を理解しているか」「その知識を正しく帳簿や申告に反映できるか」「クライアントにわかりやすく丁寧に説明できるか」など、現場での対応力も重視されます。つまり、年齢が高くても、豊富な経験があれば高く評価されるのです。
また、効率的な仕事の進め方や丁寧な顧客対応は税理士業界に限らず、他の業界でも求められるスキルです。そのため、異業種からの転職でも、現場で培った対応力があれば、採用のチャンスがあります。
ノウハウが知りたいなら
「会計求人プラス」
転職成功のポイントを押さえて、理想のキャリアを築きませんか?会計業界に特化した「会計求人プラス」の転職エージェントがあなたの希望に合った求人を見つけ、成功へのステップをサポートします。
税理士が活躍できる求人をご紹介!
税理士は何歳までなれるのか
税理士は、年齢に関係なく目指せる職業です。一般的には、未経験の方の場合、26〜27歳までに税理士試験に合格することが理想とされています。
税理士試験の合格者の中には、最年少で19歳や20代前半の人がいますが、最年長は60歳を超えることもあり、70歳以上で合格する方も時折います。また、年度によっては、41歳以上の合格者が最も多いことも頻繁に見られます。
例えば、国税庁が発表した令和3年度の税理士試験結果では、41歳以上の合格者が最も多い割合を占めていました。30代や40代で挑戦しようと考えている方も、試験会場で若い世代が多いことに気後れすることや年齢を理由に諦める必要はありません。
実際に、長年働き、家庭を持ちながら税理士試験に合格する人もいますし、定年退職後に挑戦する方もいるほどです。これらのことから、税理士はどの年齢からでも目指すことができ、挑戦できる職業であるとされています。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
税理士は何歳まで働けるのか

税理士の転職において、年齢が大きな障害になることはほとんどありません。それでは、税理士は実際に何歳まで働くことができるのでしょうか。
実際のところ、税理士の平均年齢は65歳以上とされており、独立していれば定年という概念はほぼ存在しません。健康である限り、働き続けることが可能です。
また、税理士としての働き方によって年齢の違いも見られます。そこで、2つの異なるケースに分けて詳しく見ていきましょう。
勤務税理士の場合
大手や中小の税理士法人・税理士事務所に勤務する場合、定年制度が適用されるため、一定の年齢で退職することが一般的です。しかし、近年では定年後の再雇用制度が広がりつつあり、税理士業務の特性上、業務を継続するケースが増加しています。特に、事務所が人手不足の状況であれば、定年後も長期間にわたって税理士として働き続けることが可能になるでしょう。
開業税理士の場合
一方、独立して開業した税理士にとっては、定年制度が存在しないため、高齢になっても年齢に関係なく働き続けることができます。特に、顧客との信頼関係が深まると、可能な限り顧問を続けることが一般的です。つまり、税理士としてのキャリアには年齢による制限がないということです。
制限がないため、税理士の高齢化が歯止めが聞かない状況が続いており、開業税理士として税理士事務所を運営していても常に後継者問題に行き当たるでしょう。
ノウハウが知りたいなら
「会計求人プラス」
転職成功のポイントを押さえて、理想のキャリアを築きませんか?会計業界に特化した「会計求人プラス」の転職エージェントがあなたの希望に合った求人を見つけ、成功へのステップをサポートします。
税理士が活躍できる求人をご紹介!
年齢に関係なく税理士の転職に有利となるスキル
コミュニケーション能力
コミュニケーション能力は、税理士にとって欠かせないスキルのひとつです。税理士はクライアントと密接に関わりながら業務を進めるため、信頼を得るためには一定のコミュニケーション能力が求められます。
例えば、税務相談や税金対策のアドバイスを行う際には、相手にわかりやすく、簡潔に説明できる力が重要です。論理的な思考を持っていても、うまく伝えられなければ業務がスムーズに進まず、場合によっては契約を失うリスクもあります。
また、クライアントによっては経営者や役員など、上級の担当者とやり取りすることも少なくないため、ビジネスマナーを備えたコミュニケーション能力は不可欠です。
税務や会計に関するアドバイスだけでなく、付随するサポートを提供した経験があれば、積極的にアピールすることが大切です。
もし自身のコミュニケーション能力に不安があるなら、どのように向上させるかを考え、実践することが重要です。自信がある方は、その点をしっかりと強調して伝えると良いでしょう。
英語
近年では、企業のグローバル化により、税理士にも語学力が求められることがあります。ただし、企業が国際的に展開していない場合は、語学スキルが直接的に必要とされるわけではありません。
しかし、語学力を持っていると、税理士としての強みができるため選択肢が広がります。例えば、現在はグローバル展開していない事務所や企業への転職でも、語学スキルがあれば評価される可能性があります。将来的に海外との取引が発生する場合にも、頼りにされることがあり、語学習得のために努力してきた姿勢が評価されるでしょう。
専門性
キャリアプランを考える際には、法人向けや個人向けの業務に分けることも重要ですが、それに加えて、コンサルティングやアドバイザリー業務のように両方の要素が組み合わさった業務も存在します。さらに、語学力やマーケティングの知識、システムに関する知識が求められるケースもあります。
税理士が関わる高度な業務の中には、株式公開支援、事業承継、組織再編、M&A関連の業務があります。これらの分野では、オーナーの個人資産に関する知識や、法人系の税制についての専門知識が必要です。また、税務だけでなく、会計や財務に関する深い理解も求められます。
さらに、国際展開している企業や外資系企業との取引に対応する場合、高い語学力や現地の税法・会計に関する知識が必要です。加えて、ストラクチャードファイナンスなどの金融分野のサービスを提供するには、税務知識に加えて金融の知識も不可欠です。
自身が磨きたいスキルや進みたい方向性に応じて、どの追加要素が必要かを意識しながらキャリアプランを策定することが大切です。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
年齢ごとに求められるスキルの違いを理解して転職準備を
税理士業界では、30代でも「若手」とされ、50代や60代の方が現役で活躍しているのが一般的です。一般的なビジネス界では「転職は35歳まで」と言われることもありますが、税理士の場合は35歳を過ぎても問題なく転職可能です。ただし、年齢に関係なく、税理士としてのスキルや経験が重要視されます。
転職を考える際は、自分の税理士としての経歴や実績を整理し、応募先の事務所や企業に効果的にアピールできるよう方法を考え、入念に準備することが大切です。
もし、これまでの税理士としてのキャリアや経験を正しく評価してほしい、または税理士を目指して税理士資格の勉強しながら働くなら、会計事務所、経理専門の転職支援サービス「会計求人プラス」をご利用ください。経験者であれば会計事務所特有の細かな条件で求人を探すことができますし、未経験可などの検索条件で会計求人プラスの求人情報を検索すれば多くの求人が未経験者でも待っていることがわかります。
また、どういう事務所が自分に適しているのかがわからない、未経験だから会計業界のことがわからないなど求人情報の探し方で迷ったりしている場合は会計求人プラスの転職エージェントをご利用がおすすめです。
キャリアアドバイザーが貴方のご希望やこれまでのご経験やスキルを詳しくヒアリングさせていただき、最適な非公開求人をご紹介します。
会計・税理士事務所や経理完全特化の会計求人プラスは求人サイトと転職エージェントの2つのサービスで貴方の転職活動を全力で支援します。
ノウハウが知りたいなら
「会計求人プラス」
転職成功のポイントを押さえて、理想のキャリアを築きませんか?会計業界に特化した「会計求人プラス」の転職エージェントがあなたの希望に合った求人を見つけ、成功へのステップをサポートします。
税理士が活躍できる求人をご紹介!
投稿者情報

- 現役の税理士として10年以上、会計事務所に勤務しているかたわら、会計・税務・事業承継・転職活動などの記事を得意として執筆活動を5年以上しています。実体験をもとにしたリアルな記事を執筆することで、皆さんに親近感をもって読んでいただけるように心がけています。
最新の投稿
 税理士2025.06.29独学で税理士試験合格はできる?合格を勝ち取るポイントを解説
税理士2025.06.29独学で税理士試験合格はできる?合格を勝ち取るポイントを解説 税理士2025.06.22税理士の平均年収の現実とは?税理士の給料を年齢別や働き方別に解説!
税理士2025.06.22税理士の平均年収の現実とは?税理士の給料を年齢別や働き方別に解説! 税理士の仕事2025.05.29税理士の独立開業は厳しい?業界事情や開業に失敗する原因、成功のポイントをご紹介
税理士の仕事2025.05.29税理士の独立開業は厳しい?業界事情や開業に失敗する原因、成功のポイントをご紹介 税理士試験2025.05.21実務経験なしから税理士になるには?税理士登録に必要な要件や経験を積める場所を解説
税理士試験2025.05.21実務経験なしから税理士になるには?税理士登録に必要な要件や経験を積める場所を解説