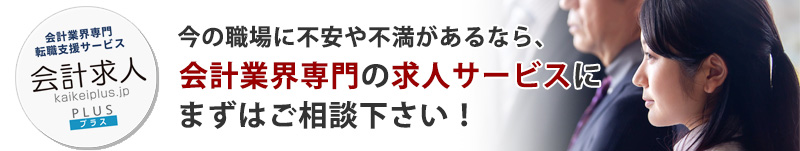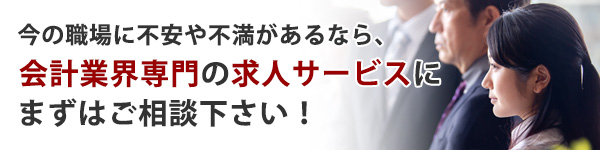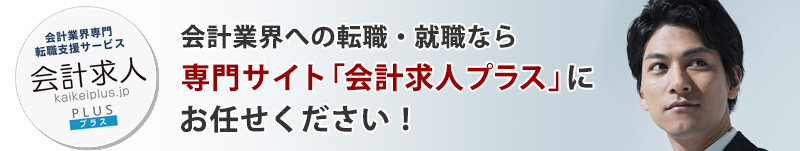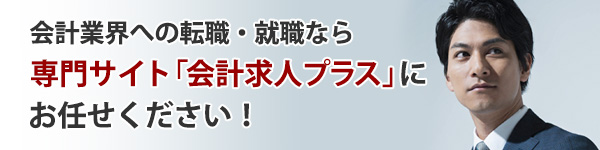簿記3級の合格率はどれくらい?年度ごとの推移と合格者の傾向を徹底解説
簿記は1級・2級・3級・初級(旧4級)の4つに区分されており、3級は初級の一つ上です。より高度なスキルや知識を求められる1や2級に比べると難易度は低くなりますが、実際の合格率はどの程度なのでしょうか。
本記事では、簿記3級の取得を目指す方に向けて簿記3級の試験概要や合格率の推移、簿記3級そのものの世間的な評価や取得するメリット、簿記3級取得後のステップについて解説します。
これから簿記を学びたいという方や、ゆくゆくは税理士や会計士などの士業を目指したいという方はぜひ参考にしてください。
■□■□会計事務所や経理職の確実な転職活動を進めるなら会計業界専門転職サイト「会計求人プラス」が安心!ご利用は完全無料の会員登録はこちらから■
コンテンツ目次
簿記3級とは?試験概要と合格率の推移

簿記3級は、業種や職種に関係なく、あらゆるビジネスパーソンが習得しておくべき基本的な知識とされる資格です。
小規模な企業の会計実務や日々の経理処理を正しく行えるスキルがあることを証明できます。帳簿の記入などの、実務に役立つ知識が身につくのも大きなメリットです。
また、簿記の基本用語や複式簿記の仕組みなどの理解度を測る初級に比べると、簿記3級では株式会社における会計処理に関する出題も加わるため、簿記へのより深い理解が求められます。そのため実務に生かせる会計の基本をしっかり学びたい人にとって、非常に有用な資格です。
試験概要
簿記3級の試験概要は以下の通りです。
| 試験科目 | 商業簿記(3題以内) |
| 試験時間 | 60分 |
| 試験科目 | 商業簿記(3題以内) |
| 合格基準 | 70%以上 |
| 試験形式 | 統一試験・団体試験・ネット試験 |
| 受験資格 | なし |
| 試験日程 | 統一試験:6月、11月、2月団体試験:企業・学校との調整の上、随時ネット試験:試験会場ごとに随時 |
| 出題範囲 | 商業簿記、商業簿記標準・許容勘定科目表 |
| 受験料(税込) | 3,300円 |
簿記3級の場合、パソコンで解答し、その場で試験の合否が分かるネット試験の受験も可能です。会場で受験する統一試験は年に3回しか実施されず、合格発表までにも日数を要しますが、ネット試験ならほぼ毎日(統一試験前後の施行休止期間を除く)試験を実施している会場もある上、試験終了後、直ちに合否を確認できるというメリットがあります。
どの試験形式で受験しても出題範囲などに変わりはないため、受験しやすい方を選びましょう。
合格率の推移
簿記3級の合格率とその推移は以下の通りです(※)。
【統一試験】
| 回 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 169回(2025年2月23日) | 2万1,026名 | 6,041名 | 28.7% |
| 168回(2024年11月17日) | 1万9,588名 | 5,785名 | 28.7% |
| 167回(2024年6月9日) | 2万927名 | 8,520名 | 40.7% |
| 166回(2024年2月25日) | 2万3,977名 | 8,706名 | 36.3% |
| 165回(2023年11月19日) | 2万5,727名 | 8,653名 | 33.6% |
【ネット試験】
| 回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月~2024年12月 | 17万1,038名 | 6万6,863名 | 39.1% |
| 2023年4月~2024年3月 | 23万8,155名 | 8万8,264名 | 37.1% |
| 2022年4月~2023年3月 | 20万7,423名 | 8万5,378名 | 41.2% |
合格率は年度によってばらつきがありますが、おおむね3~4割程度であることが分かります。なお、上記を見る限りではネット試験の方がやや合格率が高い傾向にあるようです。
前述の通り、統一試験とネット試験は試験範囲や難易度に差はないといわれていますが、ネット試験は随時受験できるため、自分にとってベストなタイミングで受験可能であること、また、不合格になってもその場ですぐに修正点や改善点を見直しやすいことなどが高い合格率につながっていると考えられます。
ただし、全ての人にネット試験が適しているというわけではありません。パソコンに不慣れな方は、操作にもたついて解答に遅れが生じ、本来の力を発揮できない恐れがあるからです。パソコン操作に慣れていない場合は、無理をせず統一試験や団体試験で受験することをおすすめします。
※参考:日本商工会議所・各地商工会議所.「受験者データ」(参照2025-04-16).
働き方を改善したいなら
「会計求人プラス」
「残業が多い」「テレワーク対応した職場で働きたい」と思っていませんか? 会計事務所・税理士事務所で働き方を変えたいなら、専門の転職・求人サイト「会計求人プラス」がおすすめです。
簿記3級は取得しても意味がない?受験前の不安

簿記はビジネスパーソンにとって必須の基礎知識とされていますが、一方でインターネット上では「3級は取得しても意味がない」「就活で役に立たない」という声も見受けられます。
なぜ簿記3級を取っても「意味がない」という声が散見されるのでしょうか。ここではその理由を探ってみました。
誰でも合格できると思われている
簿記3級は内容・合格率を見ても難易度が高いとはいえません。例えば、商業高校などに通う高校生であれば多くの人が在学中に取得しているようです。高校生のうちに取得できるレベルの資格となると、社会人として持つ資格としてはあまり評価されないため、意味がないと考えられているようです。
履歴書に書いても評価されない
一般的に、就職・転職活動で資格として評価されるのは簿記2級以上といわれています。そのため履歴書に簿記3級を書いたところでプラス評価とならないため、意味がないと考えられているようです。
実務で戦力とならない
簿記3級の知識であれば、経理実務を少し経験すれば覚えられる内容です。資格を持っているからといってそれほど実務に有利に働くというわけではなく、持っていなければ困るほどのことはないため、意味がないと考えられているようです。
簿記3級を取る意味とメリット

前章で簿記3級が「意味ない」といわれる理由を説明しましたが、実際にはまったく役に立たないわけではありません。学ぶ人の動機や目的によっては、簿記3級は有意義な資格だといえます。
ここでは簿記3級を取るメリットや意味について解説します。
会計業界への適性判断に役立つ
簿記3級の勉強をすることによって、自分は会計業界への適性があるのか知ることができます。例えばこんな人が当てはまります。
●会計業界に興味がある
●これから経理に就職する人
●将来に悩んでいる人
簿記3級は受験コスト(勉強期間、費用など)のハードルが低いため、トライしやすい資格です。「会計とはこういうものだ」という触りの部分を知る上で内容がよくまとめられた試験のため、自分に会計業界への適性があるのか判断するためであれば意味があるといえます。
上位資格への足がかりになる
簿記3級を上位資格への足がかりとして取得するのであれば、意味があるといえます。上位資格として、例えば次のものがあります。
●簿記1級
●簿記2級
●建設業経理士1級
●公認会計士
●米国公認会計士(USCPA)
●税理士
など
簿記1、2級は、簿記3級よりも専門的で、実務に即した知識やスキルが問われます。そのため、企業の経理・財務担当として働きたい場合、2級以上の資格を取得していれば自己PRに役立ちます。
また、建設業経理士や公認会計士、税理士などの士業の資格を取得するには、経理や財務、会計などに関する専門的な知識や実践的なスキルが必要不可欠です。
簿記3級は、こうした難関資格に挑戦する前の基礎固めとしても役立てられる資格だといえるでしょう。
経理補助として働ける
会計事務所や一般企業の経理部では補助的な仕事をしてもらうためにパート・アルバイトを募集します。この募集条件に「簿記3級程度」といった記載がされていることが多いです。補助的な仕事とはいえ最低限の会計知識はあった方が良いため、それを証明するのに簿記3級を持っていれば意味があるといえます。
日常での資産管理に役立てられる
経理の仕事をしなくても、例えば投資・ビジネス・確定申告・家計簿など簿記はさまざまなシーンに活用できます。簿記3級では体系的に会計の勉強ができるため、自分自身の知識・教養として生かすことができれば意味があるといえます。
働き方を改善したいなら
「会計求人プラス」
「残業が多い」「テレワーク対応した職場で働きたい」と思っていませんか? 会計事務所・税理士事務所で働き方を変えたいなら、専門の転職・求人サイト「会計求人プラス」がおすすめです。
簿記3級合格までに必要な勉強時間と学習法
簿記3級は1級や2級といった上位級に比べると難易度は低めですが、だからといって無計画に受験して合格するほど簡単な試験でもありません。簿記3級に一発合格するためには、十分な勉強時間の確保と適切なやり方での学習が不可欠です。
ここでは簿記3級合格に必要な勉強時間の目安と、主な学習方法について解説します。
簿記3級合格に必要な勉強時間の目安
簿記3級合格のために必要な勉強時間は、約100時間とされています。
例えば、平日は仕事や学校の前後に1日2時間、休日には5時間ずつ勉強した場合、1週間で合計20時間の学習ができます。このペースで進めると、約5週間で合計100時間に達し、合格ラインに届く見込みです。ネット試験であればいつでも受験できるため、勉強開始から約1カ月半での合格も視野に入るでしょう。
一方、統一試験での受験を予定している場合は、例えば、7月から勉強を始めて11月の試験に備えると、約4カ月間を勉強に使えます。この場合、1日当たり50分ほどのペースでコツコツ勉強に取り組めば、無理なく合格を目指せるでしょう。
もちろん、勉強時間を毎日確保するのが難しいという場合はこの限りではありません。ライフスタイルや学習ペースは個人差が大きく「休日にしか勉強できない」「毎日勉強するのはきつい」という方も多いでしょう。
そのため、学習計画を立てる際は、まず受験の日程を決め、そこから逆算して1日あるいは1週間にどのくらい勉強すれば良いのかを割り出すところからスタートします。1日あるいは1週間の勉強時間が分かったら、自分のライフスタイルや学習ペースに照らし合わせ、何曜日に何分(何時間)の勉強を行えば良いか考えると、適切な学習計画を作成できるでしょう。
簿記3級の学習方法
簿記に限らず、資格試験の学習法は独学・通学・通信の3つに分類されます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、どの学習方法が自分に合っているか慎重に見極めましょう。
独学
簿記3級なら、自分で購入した参考書やテキストを用いた独学でも十分合格を狙えます。費用はテキスト代だけで済むため、3つの方法の中で最もコストを節約できるのが利点です。
ただし、分からないところがあっても自力で解かなければならないため、勉強につまずいた時に問題を解決できるのかどうかが大きな課題となります。また、独学だとモチベーションの維持が難しく、途中で挫折しやすいところもネックです。
通信
簿記3級の取得を目指す通信講座を受講する方法です。資格試験のプロが考案したカリキュラムに基づき、専用のテキストを用いて勉強するため、独学よりも効率的に勉強できる点がメリットです。
勉強は自宅などで行いますが、分からない部分や解けない部分については電話やメール、チャットなどを通じてサポートを受けられるため、勉強でつまずく心配もないでしょう。
ただし、独学と同じく勉強は個人で進める必要があるため、モチベーションの維持が課題になりやすいです。
通学
資格試験対策に特化したスクールに通って勉強する方法もおすすめです。専門の講師から直接指導を受けられるため、分からないことや疑問点があってもその場で解決することができます。また、同じ目標を持った人たちと一緒に学習するため、モチベーションを維持しやすいという点も通学ならではの利点でしょう。
一方で、受講日時があらかじめ決まっており、自分のペースで学習を進めにくいというデメリットがあります。費用面についても他の方法より高額になる場合が多いため、コストを節約したい場合は独学や通信を検討した方が良いでしょう。
働き方を改善したいなら
「会計求人プラス」
「残業が多い」「テレワーク対応した職場で働きたい」と思っていませんか? 会計事務所・税理士事務所で働き方を変えたいなら、専門の転職・求人サイト「会計求人プラス」がおすすめです。
独学で簿記3級の合格を目指すためのポイント
通信や通学に頼らず、独学で簿記3級の取得を目指す場合に押さえておきたい学習のポイントを紹介します。
参考書・テキストをよく読み込む
独学の基本は、参考書やテキストをしっかり読み込むことです。ただし、一回目に関してはあまり細かい部分にこだわらず、短期間で通読してしまいましょう。テキスト内の練習問題にも、初回は「正解できなくても仕方ない」くらいの気持ちで取り組み、間違えた部分は参考書やテキストの解説をしっかり確認することが大切です。
2回目以降は間違えたところを中心に復習し、最終的には全ての問題に正解することを目標にします。初回から根を詰め過ぎると挫折しやすいため、繰り返し読み込んで徐々に理解度を上げていくのがポイントです。
過去問を何度も解く
参考書やテキストを一通り読み解いたら、次は過去問演習に取り組みましょう。過去に出題された内容がそのまま出るとは限りませんが、出題傾向や問題の形式、難易度を把握するために非常に役立ちます。
過去問も参考書やテキストと同じく、繰り返し学習することが大切です。最初は全体をざっと解いてみて、自分がどの問題でつまずくのかを確認しましょう。その後、間違えた問題をしっかり見直し、同じ過去問を2回、3回と繰り返し解くことで理解が深まります。
その際、ストップウォッチなどを使って試験本番と同じ制限時間で取り組むと良いでしょう。時間を計測せずに問題を解くと、時間配分の感覚をつかみにくくなり、本番での時間切れのリスクが高くなるためです。
なお、過去問は最新のものに加え、最低でも過去2~3年分に取り組むことをおすすめします。複数年分に触れることで、より幅広い出題傾向に対応できるようになります。
最適な求人を探すなら
「会計求人プラス」
会計求人プラスは、「会計事務所、経理専門の求人・転職サイト」です。会計業界に関連する求人のみを扱っているため、知りたい情報、希望する条件に合った求人が見つかります!
簿記3級の受験当日のポイントと対策
簿記3級の受験当日の対策ポイントを2つに分けて解説します。
持ち物の確認
簿記3級の試験には以下のものが必要です。
●受験票
●身分証明書
●筆記用具
●計算器具
身分証明書は氏名、生年月日、顔写真の全てを確認できるもので、運転免許証やパスポート、社員証、学生証などがこれに該当します。
筆記用具はHBまたはBの黒鉛筆やシャープペン、消しゴムのみが使用できます。色鉛筆やラインマーカー、定規などは使用できないため持ち込まないようにしましょう。
また簿記3級には、そろばんまたは電卓のいずれか1つを持ち込み可能です。ただし、持ち込める電卓は四則演算機能のみのものに限られます。印刷機能やメロディー機能、プログラム機能、辞書機能などが搭載されているものはNGとなるため注意しましょう。
分からない問題は飛ばす
簿記3級の試験時間は60分と決まっており、時間内に全ての問題に取り組まなければなりません。解けない問題に時間を割き過ぎると、その先にある問題に着手する時間がなくなってしまい、時間切れになってしまう可能性があります。
問題文を読んでみて、すぐに解けそうにないと思ったら、いったん飛ばして次の問題に取りかかりましょう。そうして最後まで解いた後、飛ばした問題に戻って再度着手すれば「後半の問題をほとんど解けなかった」というリスクを回避できます。
最適な求人を探すなら
「会計求人プラス」
会計求人プラスは、「会計事務所、経理専門の求人・転職サイト」です。会計業界に関連する求人のみを扱っているため、知りたい情報、希望する条件に合った求人が見つかります!
まとめ:簿記3級の合格率を上げるためには計画を立てて取り組むことが大切
簿記3級は、上位資格である1級や2級に比べると難易度は比較的易しく、合格率は全体の3~4割程度です。ただし、基礎をしっかり固めていなければ合格は難しいため、独学で勉強する場合は参考書やテキスト、過去問を繰り返し学習することが大切です。
また、効率良く学習するためにも、受験日から逆算して1日どのくらいの勉強時間を確保すれば良いのか、きちんと計画を立てて取り組みましょう。
簿記3級は、簿記1級や2級などの上位資格や、公認会計士・税理士といった難関試験への足がかりになる資格でもあるため、上位資格取得や士業を目指している方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
会計業界への転職をお考えの際は、会計求人プラスをご活用ください。未経験でも応募できる求人を多数掲載しています。
働き方を改善したいなら
「会計求人プラス」
「残業が多い」「テレワーク対応した職場で働きたい」と思っていませんか? 会計事務所・税理士事務所で働き方を変えたいなら、専門の転職・求人サイト「会計求人プラス」がおすすめです。
投稿者情報

- 税理士や公認会計士、会計業界に関する記事を専門に扱うライター。会計業界での執筆歴は3年。自身でも業界についての勉強を進めながら執筆しているため、初心者の方が良く疑問に思う点についてもわかりやすくお伝えすることができます。特に業界未経験の方に向けた記事を得意としています。
最新の投稿
 税理士の仕事2026.01.18会計と税務の違いを解説!会計業界で働くなら知っておきたい基礎知識
税理士の仕事2026.01.18会計と税務の違いを解説!会計業界で働くなら知っておきたい基礎知識 会計士の仕事2025.10.19公認会計士にMBAは必要?取得のメリット・デメリットと将来性を解説
会計士の仕事2025.10.19公認会計士にMBAは必要?取得のメリット・デメリットと将来性を解説 税理士2025.10.03税理士の仕事内容とは?主な就職先、魅力・やりがいについても解説
税理士2025.10.03税理士の仕事内容とは?主な就職先、魅力・やりがいについても解説 転職市場動向2025.08.18簿記3級の合格率はどれくらい?年度ごとの推移と合格者の傾向を徹底解説
転職市場動向2025.08.18簿記3級の合格率はどれくらい?年度ごとの推移と合格者の傾向を徹底解説