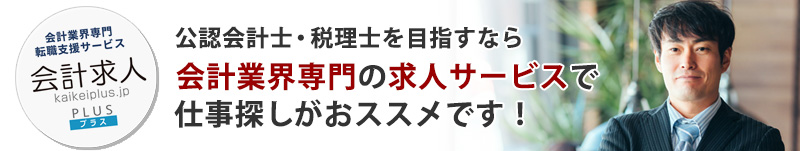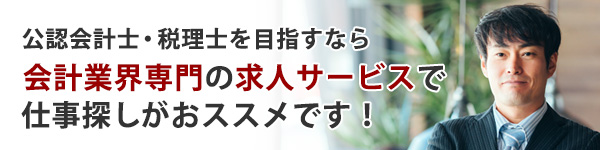実務経験なしから税理士になるには?税理士登録に必要な要件や経験を積める場所を解説
税理士として活躍するためには、一定の実務経験を積む必要があります。実務経験を積むには複数の方法があるため、自身の今後のキャリアプランや要望に合わせて適したものを選択しましょう。
本記事では、税理士になるために必要な実務経験の要件や、実務経験を詰める場所、実務経験なしで税理士として転職するために必要な準備などについて解説します。
実務経験なしの状態から税理士への転職を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
■□■□会計業界へ効率的に転職活動を進めるなら専門転職サイト「会計求人プラス」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□
コンテンツ目次
税理士登録に必要な実務経験の要件
税理士として第一線で活躍するには、税理士試験に合格した上で、さらに2年間の実務経験が必要です。
税理士試験に合格しただけでは税理士として働くことはできないため、税理士試験の勉強と並行して実務経験を積んでいる方も多くいます。
ここでは税理士登録に必要な実務経験について、詳しく解説します。
実務経験の要件
税理士法第3条において、税理士資格を取得するために必要な実務経験の要件は「租税に関する事務または会計に関する事務で、政令に定めるものに従事した期間が通算して2年以上あること」と規定されています(※)。
税理士資格の取得に当たって、実務経験が免除されるのは弁護士または公認会計士の資格を有する人のみです。税理士試験に合格した人や、同法第7条または8条の規定によって税理士試験を免除された人に関しては、通算2年以上の実務経験が必要です。
※参考:e-GOV法令検索.「税理士法」.“第三条, 第七条, 第八条”.,(参照2025-03-24).
実務経験として認められる業務
税理士法第3条で定められている租税あるいは会計に関する事務とは、税務官公署における事務や、その他の官公署・民間企業などにおける税務または会計に関する業務を指します。具体的な業務内容は以下の通りです(※)。
- 事業所が行った全ての取引を簿記の原則に従って仕訳をする事務
- 仕訳帳などから各勘定に転記する事務
- 元帳の整理と日計表・月計票を作成し、その記録の成否を判断する事務
- 決算手続き
- 財務諸表の作成
- 帳簿組織の立案または原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務
税理士試験の合格と併せて、上記いずれかの事務に携わっている期間が通算2年以上あれば、税理士の登録を行えるようになります。
なお、上記の事務に携わっているなら、働く場所に関する制限はありません。税理士事務所や会計事務所だけでなく、民間企業で経理・会計担当として従事したり、銀行や保険会社で税務・会計関連の業務に携わったりした場合も認められます。
また、実務経験を積む際の雇用形態についても、特に制限は設けられていません。正社員はもちろん、契約社員や派遣社員として働いたり、パートやアルバイトなど時間単位で勤務したりしても問題ないため、人によっては学生のうちから実務経験を積んでいるケースもあります。
ただし、税理士登録時に提出する書類に若干の違いがあるため、登録申請の際は注意しましょう。実務経験を証明する書類の詳細は、後述します。
※参考:国税庁.「第2条《税理士業務》関係」.“(特別な判断を要しない機械的事務に該当しない事務)”.,(参照2025-03-24).
実務経験と認められない業務
ここまで税理士になるために必要な実務経験について説明しましたが、一方で実務経験にカウントされない業務も存在します。
例えば、税理士法施行令第1条の3で規定されている、特別の判断を要しない機械的事務(簿記会計に関する知識なしでも可能な単純事務)はいくら従事しても実務経験にカウントされません(※)。
例えば、パソコンなどを使って行うデータの入出力などは特別な知識やスキルがなくても行える業務と見なされるため、実務経験からは除外されます。
なお、税理士事務所や会計事務所に転職したとしても、税務または会計に関する業務に携わっていない場合は必要な実務経験を積めません。そのため、従事する業務についてあらかじめ問い合わせておくことをおすすめします。
※参考:e-Gov法令検索.「税理士法施行令」(参照2025-3-24).
実務経験の期間の計算方法
税理士資格に必要な実務をこなす場合、必ずしも同じ場所で連続して経験を積む必要はありません。
例えば、以下の条件の場合、合計で2年の実務経験を積んだことになるため、税理士資格取得の条件を満たせます。
- 民間企業の経理事務として1年の経験を積む
- しばらくのブランクを経て税理士事務所に転職し、会計や税務関連の業務に1年携わる
実務経験の期間を証明するための書類
税理士の登録申請に当たっては、確実に実務経験を積んだことを客観的に証明する書類が必要です。
具体的には、実務経験を積んだ職場が交付する在職証明書の提出が必須となるため、複数の場所で実務経験を積んだ場合は、勤務先ごとに在職証明書を発行してもらわなければなりません。
特に実務経験の証明につながる勤務先が複数ある場合や、ブランクが空いてしまう場合は、書類の管理をきちんと行うようにしましょう。在職証明書は通常、勤務先の人事部や総務部に申し出れば発行してもらえます。
なお、雇用状況や雇用形態によっては在職証明書の他に勤務時間の積上げ計算書や職務概要説明書の提出が求められる場合があります。
勤務時間の積上げ計算書は、パートやアルバイトなど時間単位で勤務した場合に必要となる書類で、常勤・非常勤や勤務期間、当該機関における勤務日、当該勤務日における勤務時間などの記載が必要です。
一方、職務概要説明書は、一般の民間企業で会計・税務に関する事務業務に携わった場合に必要となる書類です。職務概要説明書には、当該業務に従事した期間や所属部署・担当業務の他に、担当業務における会計業務の割合について記載する項目があります。税務・会計業務以外の業務に従事していた場合は、客観的な割合も算出しておきましょう(例えば会計業務7、営業3など)。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
会計業界未経験OKの求人をご紹介!
税理士の実務経験を積める場所とそれぞれの特徴
税理士の実務経験は、さまざまな場所で積むことが可能です。それぞれにメリット・デメリットがあるため、どの場所で実務経験を積めばよいか、慎重に検討しましょう。
ここからは、税理士の実務経験を積める主な場所とそれぞれの特徴をご紹介します。
税理士・会計事務所
一般的なパターンは、税理士・会計事務所で実務経験を積むことです。ただし、同じ税理士・会計事務所でも、事業所の規模によってメリットやデメリットに違いがあります。
個人事務所や小規模・中規模の事務所の場合、従業員の数が少ないため専任の部署やチームが決まっておらず、部署や部門の垣根を越えてさまざまな業務を任せられるケースが多いです。幅広い知識やスキルを身に付けやすいところが利点ですが、広く浅い経験になりがちで、特定の分野に特化した知識・スキルを習得しにくいというデメリットもあります。
一方、大規模な事務所は専任の部署やチームに分かれていることが多いため、特定分野について深い知識やノウハウを習得しやすいです。ただし、担当する部署・部門以外の業務に触れる機会が減るため、つぶしが利きにくいというデメリットがあります。
以上のことから、多種多様な業務をこなせるようになりたい場合は個人事務所や小・中規模な事務所、特定の分野のプロフェッショナルになりたい場合は大規模な事務所を選ぶとよいでしょう。
もちろん事務所ごとに経営方針や理念、社風などに違いがあるため、事業規模はあくまで判断基準の一つと考え、総合的に判断することが大切です。
一般事業会社
一般事業会社の経理・会計部門などで実務経験を積む方法もあります。
一般事業会社は本来、税理士・会計事務所にとって顧客に当たる存在です。そこで経理・会計業務に従事すれば、会社の内情や経理・会計の実態に詳しくなり、実際に税理士になったときにクライアント目線でのアドバイスやサポートを提供しやすくなります。そのため、将来独立開業を目指している方や、コンサルティングファームへの就職を希望している方にとって有用な選択肢となるでしょう。
ただし、実際に携わる業務は勤め先の経理・会計事務の範囲にとどまるため、他社の内情を知る機会はほとんどありません。
また、小規模事業所の中には、経理や会計部門を置かず、一人の従業員が経理から営業まで幅広い業務をこなしているケースもあります。
実務経験としてカウントされるのは特別な判断を必要とする租税関連の事務に限定されるため、雑多な業務を任される場合、必要な実務経験を積むために長い期間を要してしまうかもしれません。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
実務経験なしで税理士・会計事務所に転職するために行っておきたい準備
税理士・会計事務所の中には、未経験可の求人を出しているところもあるため、実務経験なしでも税理士・会計事務所への転職は可能です。ただし、採用されるためには現場で即戦力となり得るスキルやポテンシャルがあることをアピールする必要があります。
そこで、実務経験なしで税理士・会計事務所へ転職するために行っておきたい準備をご紹介します。
簿記2級を取得する
簿記2級とは、高度な商業簿記・工業簿記を修得し、企業活動や会計実務を踏まえた適切な処理・分析を行うために必要なスキルを有していることを証明できる資格です。
簿記2級の資格を取得していれば、未経験でも即戦力があると見なされやすくなります。
なお、簿記2級の試験は、税理士試験の会計学に関する科目の一つである簿記論と学習範囲が重複しています。そのため、これから税理士試験にチャレンジする場合、税理士試験の勉強にもなって一石二鳥です。
Excelや会計ソフトのスキルを習得しておく
実務経験なしの人が税理士・会計事務所で働く場合、以下に挙げるような業務を任せられることが多いです。
- 請求書や領収書
- 現金出納の仕訳
- 会計ソフトへの入出力
- 決算書の作成
- 顧客の給与・年末調整
これらの業務にはExcelまたは会計ソフトを使用するため、これらのツールやソフトを問題なく使いこなせるスキルが求められます。
基本的なスキルであれば、書籍やオンラインで公開されている学習サイトなどを活用すればある程度習得できるため、転職活動に向けてスキルアップを図りましょう。
なお、Excelを含むMicrosoft Office全般に関する知識やスキルを証明できる、MOS(Microsoft Office Specialist)の資格を取得するのも一つの方法です。
自己分析やキャリアプランを明確にする
税理士としての実務経験を積める場所は複数ありますが、「経験を積めればどこでも構わない」という考えで転職活動をすると、採用側の担当者に対して「うちの事務所である必要はないのでは?」とマイナスの印象を抱かせてしまいかねません。
また、実務経験は通算2年と長い上、勤務先によって習得できるスキルや経験にも差が出てくるため、今後のキャリアパスに大きな影響を及ぼす可能性があります。
転職先を検討する際は、まず自己分析を行い、どの事務所が自分に適しているか、どのようなキャリアプランを築きたいかを明確にするところからスタートしましょう。
自己分析やキャリアプランがはっきりすれば、志望動機や自己PRもより具体的な内容になり、その志望先を選んだ理由や働く意欲をしっかりアピールできるでしょう。
まとめ:自分に合った方法で実務経験を積み、税理士転職を目指そう
税理士として活躍するには、税理士試験に合格し、かつ通算2年以上の実務経験を経て登録申請を行わなければなりません。
実務経験は租税に関する業務に携われる場所であれば、場所や雇用形態に制限はありません。しかし勤務先によって、習得できる知識やスキル、経験などに違いがあるため、自身の希望や今後のキャリアプランなどに応じて慎重に選ぶことが大切です。
なお、税理士・会計事務所の中には、未経験OKの求人を出しているところもあります。ただし、実務経験なしの人は経験ありの人に比べてやや不利になるため、資格取得やスキルアップ、自己分析などの下準備をしっかり行っておきましょう。特に自己分析やキャリアプランを明確にすると、どこで実務経験を積むのが適しているのか判断基準にもなるため、志望先を絞り込みやすくなります。
「自己分析やキャリアプランの作成方法が分からない」「どこで実務経験を積むべきか悩んでいる」といった悩みを抱えている方は、会計士・税理士事務所専門の求人・転職サイトである会計求人プラスのご利用がおすすめです。
会計求人プラスでは、勤務地や雇用形態、事務所区分、働き方など、さまざまな条件で求人を検索可能です。また、会計業界に精通したエージェントが、一人ひとりに適した求人探しから転職後のアフターフォローまで、徹底したサポートを行います。
実務経験なしから税理士を目指したい方は、ぜひ会計求人プラスのサービス利用をご検討ください。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
投稿者情報

- 現役の税理士として10年以上、会計事務所に勤務しているかたわら、会計・税務・事業承継・転職活動などの記事を得意として執筆活動を5年以上しています。実体験をもとにしたリアルな記事を執筆することで、皆さんに親近感をもって読んでいただけるように心がけています。
最新の投稿
 税理士の仕事2026.01.20税理士補助ってどんな人が向いている?特徴や働き方をわかりやすく解説!
税理士の仕事2026.01.20税理士補助ってどんな人が向いている?特徴や働き方をわかりやすく解説! 経理2026.01.20経理の仕事内容とは?業務の全体像・必要なスキルや資格などを解説
経理2026.01.20経理の仕事内容とは?業務の全体像・必要なスキルや資格などを解説 税理士2026.01.19税理士の必要性とは?税理士の役割や依頼するメリットを解説
税理士2026.01.19税理士の必要性とは?税理士の役割や依頼するメリットを解説 税理士試験2025.12.02税理士試験の科目合格で年収は上がるのか?評価される科目と転職タイミング
税理士試験2025.12.02税理士試験の科目合格で年収は上がるのか?評価される科目と転職タイミング