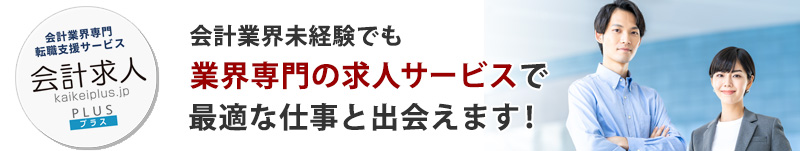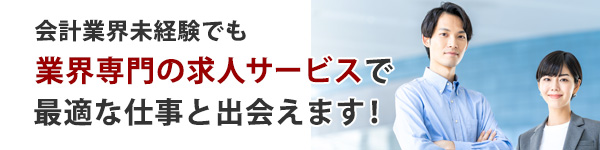高卒で税理士になるには?緩和された受験資格などポイントを徹底解説します
税理士は弁護士や司法書士などと同様に士業といわれる国家資格であり、その資格がないとできない独占業務もあります。
税理士試験は難易度の高い超難関試験であり、高卒で挑むには難しく大卒の人が税理士試験に挑んでいるイメージが強いのではないでしょうか。
よく税理士や公認会計士のような国家資格の難易度を偏差値に置き換えて解説している記事を目にしたことはありませんか。
高い偏差値がついていると、やっぱり学歴が必要なのかと不安になってしまう人もいるかと思います。
しかし、実際には高卒で税理士を目指して努力している人は多く、難関試験を突破して税理士になったケースも少なくありません。
高卒で税理士を目指している人の中には、「学歴が足りないから難しいのでは」と不安に感じていたりしませんか?
ご安心ください、近年は税理士試験の受験資格が緩和され、高卒の方も挑戦しやすい環境に変わってきています。
この記事では、税理士を目指すのは学歴や偏差値など関係なく、高卒でも税理士を目指せるポイントや方法、必要な資格について解説していきます。
高卒で税理士を目指している人におすすめしたい内容となっていますので、ぜひご覧ください。
■□■□税理士を目指して会計業界へ効率的に転職活動をするなら専門転職サイト「会計求人プラス」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□
コンテンツ目次
税理士に高卒でなることは可能なのか?
結論からいえば、高卒で税理士になることは可能です。税理士になるのに学歴や偏差値は関係ありません。
まずは、高卒で税理士を目指す人の実情を紹介していきます。
税理士における高卒者の割合
国税庁による「税理士試験の受験資格の検証」では税理士の試験において、受験者の中の高卒者が占める割合は7.0%という結果が示されています。(※1)税理士試験の受験者のほとんどが大卒者というデータがありますが、高卒者も一定数いることがわかります。
大卒・高卒に限らず、税理士になるためには、まず税理士試験に合格しなければなりません。税理士試験は数千時間という勉強時間を必要とし、1度の試験で必要科目である5科目全てに合格する人はほとんどいません。
そのため、何年もかけて1科目ずつ受験する人が多く、合格するまでに数年間かかる場合がほとんどで、途中で挫折する人も多いです。相当な勉強量が必要となる狭き門ではありますが、高卒者でも税理士を目指すことができます。
高卒者の税理士試験合格率は高い
最新である令和4年度の税理士試験における結果を見ると、全体の合格者のうち、高卒者の割合は22.1%となっています。
大学に在学中の人の割合は31.1%という高い数字を出していますが、大卒者の割合は29.8%となっています。(※2)もちろん、受験者数の母数が違うことは考慮しなければなりませんが、令和4年度にいたっては高卒者よりも大卒者の合格率が高い結果だったということがわかりますが、年度によっては高卒者の合格率のが高くなったりと僅差であることがわかります。
大学在学中の割合が高いのは、勉強時間を確保しやすい環境であるということが要因だと考えられます。
税理士試験は「量」の難易度が高いといわれるほど、多くの勉強時間を必要としますし、1度の試験で5科目合格を目指すのは限りなくゼロに近い確率だと言えます。
そのため、大学在学中であればまとまった時間を勉強時間に当てることが可能な場合が多いので在学中に5科目取得を目指す人が多いのです。
この数値からも、税理士試験を受けるにあたって、必ずしも大学を卒業する必要はないということがわかるでしょう。高卒だからといって不安に感じる必要はありません。
高卒でも年収は変わらない
正社員として企業に就職すると、一般的に高卒者より大卒者の年収が高い傾向にあります。一方で、税理士の場合は学歴が年収に影響することはありません。税理士にとって大切なのは資格です。
そもそも税理士は独占業務であり、資格があるからこそできる職業です。そのため、税理士自体が希少価値の高い資格であり、学歴に関係なく年収が高い職種ともいえます。つまり、受験資格を満たすことで、大卒者と同じスタートラインに立つことができるということです。これは、一般的な企業に就職した場合と大きく異なる点です。

税理士試験の受験資格を高卒で得る方法
「高卒者でも税理士を目指せる」ことを紹介できたところで、税理士試験の受験資格について解説していきます。
税理士試験は受験資格が無く誰でも受験することができる公認会計士試験と違い、誰でも受験できるものではありません。明確な受験資格が設けられており、その条件をクリアすることでようやく受験資格が得られます。
受験資格を得る主な条件は、以下の通りです。
- 学歴要件を満たす
- 職歴を通して受験資格を得る
- 資格要件を満たす
学歴要件を満たす
学歴を基準としてみた場合、税理士試験を受けるためには、大学・短大・高等専門学校の経済学部や法学部、または商学部を卒業している必要があります。大学3年以上で法律や経済の学科を62単位以上取得している人も受験可能です。すなわち、高卒者の場合、そのままの状態では税理士試験を受ける資格がないということです。
ただし、税理士試験の受験資格には学歴以外の条件も設定されています。高卒者はひとまず受験資格を得ることが最初のステップといえるでしょう。
職歴を通して受験資格を得る
税理士試験の受験資格として学歴以外の条件は2つあります。1つ目が、実務経験を踏まえた職歴に関する条件です。具体的には、会計事務所や税理士事務所などで2年以上補助事務に従事すると、税理士試験を受けることができます。
その他、銀行や信託会社で貸付業務や運用に関わる業務を2年以上経験した場合、また法人や個人事業主の会計を2年以上経験した場合でも、税理士試験を受けることが可能です。それぞれの業務を従事した期間が短くても、トータルで2年以上となれば問題ありません。
職歴を通して受験資格を得る方法は、どうしても時間がかかってしまうのですが、高卒ということであれば若くして実務経験を積むことができますので、大卒者と比べてもイニシアチブがあると言えるでしょう。
資格要件を満たす
高卒で税理士を目指す人にとって、現実的な方法の1つが資格要件を満たすことです。
税理士試験の受験資格を得るために必要な資格は、日商簿記検定1級か全経簿記上級です。どちらの資格も取得難度が高い資格ではありますが、高卒者でも受けられる資格です。
特に、日商簿記1級試験の出題範囲は税理士試験の内容と大きく重なるため、税理士試験の勉強をする際にも有利に働くでしょう。一方、日商簿記1級を目指す方法は、勉強する傍らで働く形になるので、社会人としてのスキルアップが遅れるデメリットがあります。
高校を卒業後、会計とはまったく関係ない職種に就く人もいるでしょう。その後、しばらく働いた結果、やはり税理士を目指したいと考える人もいると思います。
たとえ、会計とはまったく違う職種に就いていたとしても、資格要件を満たすことができれば税理士試験を受けることができます。税理士試験の受験資格については、別ページでも紹介しているので、こちらをご覧ください。
参考記事:税理士試験を受けるには条件が必要!受験資格をしっかり確認しておこう
高卒者が税理士を目指す場合、まずは「税理士試験の受験資格をしっかり確認すること」、そして「どの方法で受験資格の取得を目指すか」の2点が重要です。とはいえ、高卒者が税理士を目指す場合、ほとんどが実務経験を積んで職歴条件を満たすことになります。
高卒でも実務経験を積めば受験可能

資格要件を満たす方法は、会計に関わる仕事に就きながら税理士を目指す方法がおすすめです。
この方法であれば税理士の具体的な内容を把握できるうえ、受験資格である実務経験を満たすこともできます。雇用形態がアルバイトやパートであっても受験資格の実務経験にはカウントされるので、正社員の立場にこだわる必要はありません。働きながら税理士試験の勉強を重ねれば、高卒者でも税理士を効率良く目指すことが可能です。
会計事務所で働く方法は?
会計事務所や税理士事務所、税理士法人で働くためには、会計に関する基礎的な知識が必要になります。簿記1級レベルの高いスキルが必ずしも求められているわけではなく、簿記2級や3級でも会計に関連する就職先の幅は広がります。
日商簿記には受験資格がありませんから、誰でも受験することが可能です。高校を卒業してすぐに会計事務所(税理士事務所や税理士法人)で働こうと考えているのであれば、簿記資格は取得しておくと良いでしょう。
税理士を目指す上でも、基礎を理解しておくという意味で無駄にはなりません。
会計事務所の求人には学歴不問のものも多く、若くして会計事務所へ就職は歓迎される傾向にありますので、まずは求人を探して応募してみるといいでしょう。
会計業界へ転職したいなら
「会計求人プラス」
未経験でも会計事務所で働くことは可能です。簿記資格を持っている、税理士を目指している・目指したことがあるなど、あなたの知識を活かせる職場をお探しします!
令和5年(2023年)より受験資格が大幅に緩和
令和5年度(第73回)の税理士試験より受験資格が大幅に緩和されることになりました。
会計科目(簿記論・財務諸表論)は受験資格が必要なくなり、誰でも受験することができるようになるのです。
このことにより、今後は高校生でも単位取得前の大学1年生であっても税理士試験を受験することが可能になります。
今後は高校在学中の人も含め、若年層の受験者が増加することが見込まれます。
詳しくは下記のような見直しがされることとなりました。
- 会計学に属する試験科目(簿記論・財務諸表論)の受験資格が不要となり、どなたでも受験が可能となります。
- 税法に属する試験科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)の受験資格のうち学識による受験資格が、下記の通り拡充されます。
- 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
- 大学3年次以上の学生で社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得した者
- 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上かつ課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
社会科学に属する科目とは
社会科学に属する科目には、見直し前(令和4年度の税理士試験以前)の「法律学又は経済学に属する科目」に該当していた科目のほか、社会学、政治学、行政学、政策学、ビジネス学、コミュニケーション学、教育学、福祉学、心理学、統計学等の科目が該当します。
この受験資格が緩和されることにより、高卒者であっても5科目合格できた年齢が大幅に下る可能性が高まったといえます。
大卒者よりも若くして5科目合格していれば、その後の就職活動や就職後のキャリアパスが描きやすくなりますので、税理士としての将来の選択肢が増えるでしょう。
2023年度から若年層の受験者数が増えることが予想されます。
詳しくは下記をご参照ください。
実績を積みながら合格を目指すメリット
以下では、税理士を目指すのに勉強しながら並行して会計事務所(税理士事務所、税理士法人)で働くメリットを紹介します。
無駄が省ける
会計事務所で働きながら税理士試験を目指すと、受験勉強と平行して実務経験が積めるため、時間的な無駄を省くことができます。例えば、簿記1級を取得してから税理士の試験を受けようと思えば、簿記を取得する段階で、すでに長い年月が経過してしまうでしょう。一方で、会計事務所で働けば税理士資格取得のために必要な2年の実務経験を得ながら受験勉強をすることができます。
また給与を得ながら学ぶことができる点も魅力です。簿記1級や税理士試験は非常にハードな試験のため、試験勉強中心の生活になります。現在の仕事を辞めて勉強に打ち込むという人も少なくありません。リスクが生じる方法ですが、会計事務所で働きながら学べば収入を得られるため、お金の心配をする必要も少なくなります。
また会計事務所は、繁忙期と閑散期がはっきりしているという特徴があります。そのため、短期アルバイトを募集していることが多いです。短期アルバイトであれば、仕事と勉強のスケジュールが立てやすくなります。また税理士の資格を取得するために勉強していると伝えれば、より配慮してもらえるでしょう。
知識を得やすい
会計事務所で働きながら税理士試験合格を目指す最大のメリットは、実務から知識を得られるということです。加えて、税理士や会計士など、会計のプロと一緒に仕事ができるため、わからないことを質問することも可能です。
疑問点を解消してもらうことはもちろん、税理士の先輩として、税理士を目指すうえでの効果的なアドバイスももらえるでしょう。
先輩たちの体験談やアドバイスは、試験勉強に励む際に大きな励みとなるものです。また税理士が行う実際の仕事を目の当たりにすれば、将来的なイメージもつかみやすく、かつ学んでいる内容も把握しやすくなるというメリットもあります。
テキスト上ではわからなかった問題も、実際の現場で体験することで、理解できる可能性も高まります。
高卒未経験の場合にまかされる仕事とは?
税理士をはじめとした士業に分類される仕事は、そのほとんどが独占業務です。そのため、未経験の高卒者が行う業務は、一般的に税理士補助からスタートすることになります。ここでいう補助とは、その名の通り税理士のサポートが主な業務となります。端的にいえば、税理士の助手やアシスタントという認識でも良いでしょう。
具体的な仕事内容としては、税務書類の作成代行補助、記帳代行、経理・人事業務の代行や巡回訪問などを行います。
書類作成や記帳代行など、会計の知識となる業務が多く、前項で紹介したように簿記の資格を取得しておくのが理想です。税理士の業務は独占業務のため直接的には行えませんが、税理士補助であっても税務や会計の実務経験を積むことが可能です。
この税理士補助の仕事内容については、別ページでも詳しく紹介していますので、こちらをご覧ください。
参考記事:会計事務所の税理士補助とは?年収と仕事内容、転職事情を一挙公開!
キャリアアップの流れは?
税理士補助として働く場合、アルバイトやパートから正社員を目指すこともできます。税理士補助の仕事は経験年数が重視されやすく、雇用形態にかかわらず、年数を重ねれば年収アップが期待できます。実務経験を重ねて税理士の受験資格を得た後は、税理士試験に挑戦して、合格を目指すことになります。
なお、税理士試験は複数の科目(全11科目)で構成されている試験ですが、1科目でも合格できれば、「科目一部合格者」として扱われます。科目合格者となれば、受け入れてくれる事務所の幅が広がり、給料や待遇も良くなることが多いので、科目合格してからステップアップの転職をするのも手です。
科目一部合格者の求人案件は以下のページでも詳しく紹介しているので、転職やキャリアアップを検討している方であれば、こちらもご覧ください。
参考記事:税理士科目一部合格者で活躍できる会計求人一覧|会計求人プラス
なお、繰り返しになりますが、税理士の業務は独占業務となります。したがって、税理士としてのキャリアアップをするためには、税理士試験の合格が登竜門となるのに変わりありません。「独立して事務所を持ちたい」「企業内税理士として働きたい」などの将来像を描いている方であれば、実務経験と試験対策を重ね、試験合格を目指すことをおすすめします。
税理士になるには学歴よりも実務経験が重要
これまでの解説で、税理士資格を取得するために学歴は関係ないということはご理解いただけたかと思います。
超難関試験としても有名な税理士試験ですが、高卒から勉強を始めていることは、税理士として登録できたときの年齢が若い傾向であるといえるでしょう。
若くして税理士として実務経験を積むことができれば、豊富な知識、実務経験を積むことができ貴方のキャリアの幅を広げてくれるのは間違いありません。
まずは、税理士試験に合格するため、戦略的に勉強方法を計画し、どのように勉強をすすめるべきかポイントを押さえて効率的にすすめることが必要です。
そういった税理士試験のノウハウやテクニックを得るために予備校に通う人が多いことも事実なのです。
税理士になるために学歴なんて関係ありません。今は税理士を目指して勉強することに集中し、合格を目指しましょう。
会計業界へ転職したいなら
「会計求人プラス」
未経験でも会計事務所で働くことは可能です。簿記資格を持っている、税理士を目指している・目指したことがあるなど、あなたの知識を活かせる職場をお探しします!
投稿者情報

- 税理士や公認会計士、会計業界に関する記事を専門に扱うライター。会計業界での執筆歴は3年。自身でも業界についての勉強を進めながら執筆しているため、初心者の方が良く疑問に思う点についてもわかりやすくお伝えすることができます。特に業界未経験の方に向けた記事を得意としています。
最新の投稿
 公認会計士2025.06.29監査法人の就職は難しい?難易度・就活対策・Big4の特徴を徹底解説
公認会計士2025.06.29監査法人の就職は難しい?難易度・就活対策・Big4の特徴を徹底解説 経理2025.06.24日商簿記2級・3級の正式名称とは?履歴書に記載するポイントを解説
経理2025.06.24日商簿記2級・3級の正式名称とは?履歴書に記載するポイントを解説 税理士試験2025.04.04税理士試験に合格後のキャリアパスとは?選択肢とそれぞれの特徴を解説
税理士試験2025.04.04税理士試験に合格後のキャリアパスとは?選択肢とそれぞれの特徴を解説 転職ハウツー2025.03.12簿記1級を取っても就職できない?「やめとけ」といわれる理由とは?
転職ハウツー2025.03.12簿記1級を取っても就職できない?「やめとけ」といわれる理由とは?