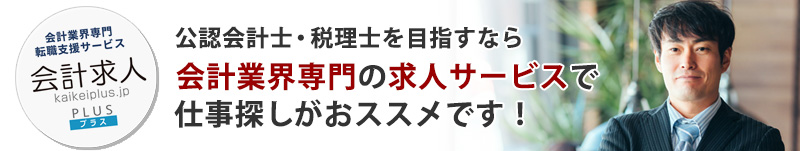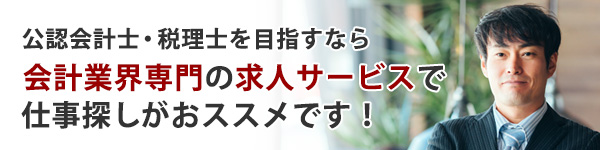公認会計士の実務経験はどこで積むべき?期間・勤務形態・注意点まとめ
公認会計士試験に合格した後、次に必要になるのが正式登録に向けた「実務経験の積み重ね」です。しかしどこで経験を積めばいいの?」「監査法人以外の選択肢はあるの?」といった疑問を抱く方も少なくないでしょう。
一般的に公認会計士が実務経験を積む場は監査法人ですが、それ以外にも会計事務所、一般企業の経理部門、コンサルティングファーム、金融機関、公務員など、多彩なキャリアパスを勘案することができます。
そこで本稿では、公認会計士としての実務経験を積める各フィールドについて詳しく解説します。ご自身のライフスタイルやキャリアプランに合った実務経験先を見つける参考にしてください。
コンテンツ目次
公認会計士になるために必要な実務経験とは
業務補助
「業務補助」とは、監査証明業務をサポートしながら、公認会計士として実践的かつ高度な知識や技術を身につける役割を指します。多くの場合、監査法人や公認会計士事務所で従事し、1年間に2社以上の監査証明業務を経験することが求められます。
法定監査および任意監査も業務補助に含まれますが、金融商品取引法で監査が義務付けられた法人や、会社法で会計監査人の設置が必要とされる資本金1億円超の株式会社については、例外的に年間1社の経験でも認められます。
さらに、大手企業での財務分析業務が補助対象になる場合もあります。ただし、専門知識を必要としない記帳業務や日常的な経理業務は含まれません。
実務従事
実務従事で得る経験は、公認会計士として独立して業務を遂行する力を養うことが目的です。
主たる業務は財務関連の監査であり、これに加え分析業務なども含まれます。業務補助と異なり、実務従事の対象業務は具体的に示されていますが、一律ではなく、公認会計士法施行令第2条に規定された業務を継続的に行っているかを個別に判断される点に注意が必要です。
主な対象業務には、国や地方公共団体の機関、一部法人や連結子会社に対する会計検査・監査、国税に関する調査・検査があります。次に、預金保険法で定められた金融機関や保険会社などを対象とする貸付・債務保証・類似の資金運用業務が挙げられます。
さらに、原価計算やその他の財務分析業務も、国・地方公共団体およびその他法人での実施が対象となります。
公認会計士の実務経験はどのくらい必要?
実務経験の要件は通算3年以上をクリアすることですが、この期間中に週何日以上働けばよいのでしょうか。業務補助の場合は、監査法人などの代表者が認めれば勤務日数に制限はありません。週あたりの出勤日数についての規定は設けられていません。
一方、実務従事では「常勤3年」が基準となり、非常勤などで出勤日数が少ない場合は常勤勤務日数と比較して期間が調整されます。たとえば、出勤日数が常勤の半分であれば、実務経験の期間も半分とみなされます。
実務経験を積む時期は、公認会計士試験合格の前でも後でも構いませんが、実際には合格後に経験を積む人が多いようです。
公認会計士の実務経験はどこで積む?
それぞれに実務従事として認められる条件があります。
監査法人
公認会計士の登録に必要な実務経験を積む場として、監査法人がもっとも一般的です。
ここでの主な業務は、公認会計士や監査法人を補助する「監査証明業務」で、「業務補助」に該当します。
多くの監査法人では、資格取得者向けの支援制度が整備されており、実務経験要件に該当する業務にも精通しています。働きながら資格取得を目指す方や、確実に実務経験を積みたい方に最適な職場といえるでしょう。
会計事務所・税理士法人
たとえ所属先の資本金が5億円未満でも、資本金5億円以上のクライアント向け業務に携わる場合は実務従事とみなされるため、小規模な会計事務所でも実務経験を積むことが可能です。この場合は「実務従事」に分類されます。
ただし、監査業務、または資本金5億円以上の顧客に対して原価計算などの財務分析業務を行っている必要があります。
同様に、税理士法人でも資本金5億円以上の法人を対象とした原価計算等の財務分析業務は実務従事として認められます。いずれの場合も、税務業務や単純な経理・記帳業務は実務従事には含まれません。
コンサルティング会社
コンサルティングファームで、資本金5億円以上の法人(開示会社およびその連結子会社を含む)を対象に原価計算や財務分析業務に従事した場合は、「実務従事」として認められます。所属会社の資本金が5億円未満でも問題ありません。
一般企業(事業会社)
事業会社の経理担当者が「実務従事」と認められる業務は多岐にわたります。要件としては、所属先の資本金が5億円以上、または所属先以外の資本金5億円以上の法人(上場企業やその連結子会社を含む)を対象とする業務であることが求められます。
ただし、税務申告などの税務業務や、日常的な経理事務・記帳業務は実務従事には該当しません。主な例は以下のとおりです。
<実務従事に該当する業務例>
- 資本金5億円以上の法人等向け原価計算・財務分析
- 財務報告に関わる内部監査
- 財務諸表を用いた内部統制評価
- 決算業務全般
- 予算策定・管理業務
- 工場会計業務
- 各種財務分析業務
- IPO準備業務など
金融機関や保険会社
銀行や保険会社などの金融機関では、融資業務や債務保証といった資金運用に関わる事務が「実務従事」として認められます。それ以外の部門に配属される場合は、実務経験要件を満たしません。
また、これとは別に、対象企業を上場企業およびその連結子会社、または資本金5億円以上の法人およびその連結子会社に限って「原価計算やその他の財務分析業務」も実務従事に含められるケースがあります。
<実務従事の例>
- 銀行での法人融資業務
- 保険会社での資産運用先企業の財務内容調査
- 保険会社における投融資審査、社内格付付与、業界レポート作成など
国税局などの公務員
国や地方公共団体の機関でも、実務従事に該当する業務があります。法人の税務申告は含まれませんが、税務調査は実務従事として認められます。
ただし、税務調査が対象になるのは次のいずれかに該当する場合に限ります。
- 特別法により設立された法人
- 資本金5億円以上の法人およびその連結子会社、または開示会社等とその連結子会社
なお、地方税の調査や、資本金5億円未満の法人・個人を対象とする国税調査・検査は対象外です。
<実務従事の例>
- 国税局での税務調査業務
- 県庁における市町村の財務監査や地方交付税検査
- 市役所での公営企業向け決算書類作成や財務諸表分析など
実務経験は正社員じゃなくても良い?
「業務補助を実務経験として認めてもらうには、監査業務の流れや手続きを3年以上にわたって修得したことを証明する『業務補助等証明書』が必要です。
非常勤の場合でも、3年間に定められた監査証明業務を経験していれば労働日数や時間の規定はなく、監査法人等の代表者が習得を認め証明書を発行すれば足ります。
一方、実務従事は原則として事業会社等で常勤として3年間勤務することが基準です。アルバイトやパートタイマーの場合は、実際の労働時間を基に、常勤比で相当と認められる期間を算出し、実務経験として認定されます。
| 勤務形態 | 所定労働時間 | 実務経験認定期間 |
|---|---|---|
| 常勤 | 週40時間(8h×5日) | 2年 |
| 非常勤 | 週20時間(4h×5日) | 1年 |
実務経験を積む上での注意点
実務内容によって実務経験にカウントされないことがある
実務経験対象の企業で勤務していても、該当業務に携わっていなければ実務経験として認められません。
次のような仕事は実務経験に該当しないため、要注意です。
- データ入力や書類整理などの単調な事務作業
- 監査・税務と無関係な総務や人事の業務
- 資本金5億円以上などの要件を満たさない法人での関連業務
たとえ監査法人に在籍していても、監査ではなく記帳や書類整理が主な業務であれば、実務経験とは見なされません。担当業務が実務経験として認定されるか、必ず確認しましょう。
パート、アルバイトはフルタイムの労働時間から算出する
公認会計士の実務経験は雇用形態を問いません。業務補助であれば、非常勤であっても監査業務を習得し証明書が発行されれば要件を満たします。
しかし、実務従事の場合は常勤勤務時間を基に短時間勤務分を換算する必要があるため注意が必要です。たとえば、フルタイムの1日8時間勤務に対し、1日4時間のアルバイトは0.5日として計算されます。
非常勤で実務従事を行う際は、この勤務時間換算法を踏まえて年数をカウントしましょう。
実務経験を証明する書類が必要になる
実務経験を認定してもらうには、「業務補助等報告書」を提出する必要があります。この報告書は、実務経験者の住所地を管轄する財務局へ送付します。提出が求められる書類は次のとおりです。
- 業務補助等報告書の正本1部および写し1部
- 業務補助等証明書
- 返信用封筒(長形3号、110円切手貼付、宛先・氏名記載)
- 提出者の日中連絡先
- 実務経験時の勤務先情報(電話番号・メールアドレス・担当者氏名) ※実務従事者のみ追加提出が必要な書類
- 従事先法人の概要資料(会社案内や組織図など)
- 担当業務を示す証拠資料(原価計算書等)
- 労働時間を証明する書類(非常勤の場合)
実務経験の期間は試験合格前後を問いませんが、報告書の提出自体は合格後に行います。
報告書を財務局および金融庁で確認・受理されると、「業務補助等の報告書受理番号通知書」が交付され、これが正式に実務経験の認定証明となります。
本通知書は、公認会計士として開業登録する際にも必要ですので、大切に保管してください。
実務経験を積む会社の探し方
4大監査法人
会計士試験に合格した人の多くは監査法人に就職し、その約8割が大手監査法人を選ぶと言われています。大手が支持される理由は主に2つです。
1つ目は、誰もが知る上場企業を多数クライアントに抱え、最先端の監査ノウハウを身につけられること。2つ目は、海外事務所とのネットワークがあり、将来のグローバルな活躍を見据えられることです。
なお、合格発表後の11月中旬から約2週間で、説明会から内定までが一気に決まる超短期戦でもあります。
その他の求人
実務経験を積める求人を探す方法には、以下の選択肢があります。特に、希望条件を満たしつつ理想の従事先を見つけたい場合は、転職エージェントの利用が最も確実です。
- 求人サイトで情報収集する
- 説明会(主にBig4主催)に参加する
- 転職エージェントに相談する
転職エージェントは、公認会計士の実務経験要件を熟知しており、キャリア設計に合致する職場を提案してくれるため安心です。効率よく、公認会計士登録に必要な3年の経験を得たい方は、ぜひご相談ください。
公認会計士の実務経験は計画的に
上記のように公認会計士になるには3年以上の実務経験が必須です。合格発表の前から準備を始めておくことをおすすめします。
実務経験を積む場は監査法人だけでなく、会計事務所や一般企業の経理部門、コンサルティングファーム、金融機関、公務員など、自分のライフスタイルや将来設計に合わせて選択できます。
どの業務が実務経験として認定されるかは「どこで」「何を行うか」によって変わります。一般的には資本金5億円以上の企業での財務分析や監査関連業務が該当しますが、アルバイトや非常勤勤務でも条件を満たせば認定されます。
監査法人は多様な業界知見を得られるうえ、キャリアの幅が広い点で魅力的です。一方、すでに明確なキャリアビジョンがある場合は、その方向性に合った職場で経験を重ねるのも有効でしょう。
実務経験先を選ぶ際には、単に「認定が得られるか」だけでなく、「将来のキャリアにどう活かせるか」という観点も重視してください。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
投稿者情報

-
会計事務所や税理士事務所、一般企業の経理職など会計業界の求人情報が豊富な「会計求人プラス」を運営し、多くの求職者の方、会計事務所の採用ご担当者とお話をさせていただいています転職エージェントです。
異業種から会計業界へ転職を希望している方をはじめ、これから税理士や公認会計士を目指す未経験の方や、今までの税務・会計の知識・経験を活かして年収アップやスキルアップしたい方などを全力で支援しています。
その一環として、会計業界でお役に立つ情報をお届けするために10年以上記事を書いています。是非、会計業界で働く人が楽しく、知識を得られるような情報をお伝えできればと思います。
最新の投稿
 転職ハウツー2026.01.20会計事務所は未経験でも目指せる?仕事内容・資格・年齢別の成功ポイントとは
転職ハウツー2026.01.20会計事務所は未経験でも目指せる?仕事内容・資格・年齢別の成功ポイントとは 公認会計士2026.01.19もう限界…監査法人を辞めたい人が知っておくべき転職戦略と準備のすべて
公認会計士2026.01.19もう限界…監査法人を辞めたい人が知っておくべき転職戦略と準備のすべて 経理2026.01.19経理にMOS資格は必要?現場の声と転職成功の秘訣を紹介
経理2026.01.19経理にMOS資格は必要?現場の声と転職成功の秘訣を紹介 成功者インタビュー2025.12.11朝日税理士法人 城南支社 成功者インタビュー 2025年度
成功者インタビュー2025.12.11朝日税理士法人 城南支社 成功者インタビュー 2025年度