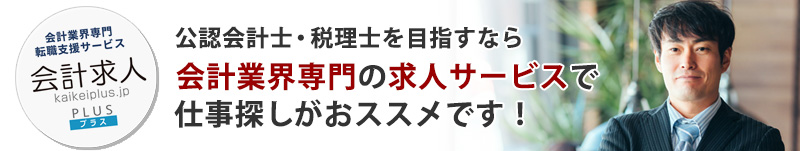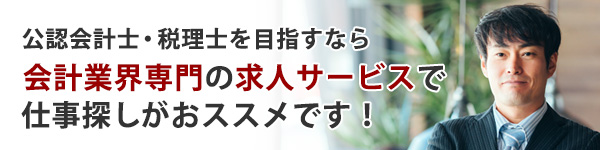働きながら税理士試験に合格できる!仕事と勉強の両立方法とは
働きながら税理士を目指すのは可能です。ただし、当然ながら相当な努力が必要となります。税理士は一度合格した科目の再受験が免除される「科目合格制」を採用しており、社会人でも取得を目指しやすい資格です。ただし、合格するには勉強と仕事の両立が不可欠であり、勉強時間を確保したいなら税理士試験への理解が深い事務所の方が、勉強と仕事の両立に適しています。
本記事では、働きながら税理士になるための勉強方法や、メリット・デメリット、税理士を目指しやすい会計事務所の特徴を紹介します。
コンテンツ目次
税理士になるための条件
税理士になるには、原則として税理士試験で所定の科目試験に合格した上で、通算2年以上の実務経験を積む必要があります。税理士試験の受験資格と、合格が必要な科目、実務の概要を解説します。
税理士の受験資格
税理士試験の受験資格は「学識」「資格」「職歴」の3つの区分があります(※)。
なお、令和5年度の税理士試験より、会計学科目の簿記論と財務諸表論は受験資格が緩和され、誰でも受けられるようになりました。
※参考:国税庁「税理士試験受験資格の概要」(2024-11-16)
1.学識による受験資格
学識による受験資格は以下の通りです。
●大学や短大、高等専門学校のいずれかを卒業した人で、法律学または経済学を1科目履修した人
●大学3年次以上で、法律学もしくは経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した人
●一定の専修学校の専門課程を修了した人で、法律学もしくは経済学を1科目以上履修した人
●司法試験に合格した人
●公認会計士試験の短答式試験に合格した人
2.資格による受験資格
資格による受験資格は以下の通りです。
●日商簿記検定1級合格者
●全経簿記検定上級合格者
3.職歴による受験資格
職歴による受験資格は以下の通りです。
●法人もしくは事業を行う個人の会計に関する実務経験が2年以上ある人
●銀行・信託会社・保険会社などで、資金の貸付・運用に関する実務経験が2年以上ある人
●税理士・弁護士・公認会計士などの補助事務を2年以上経験した人
税理士試験の科目合格
税理士試験は科目選択制度を採用しており、全11科目から必須科目を含む5科目に合格する必要があります。なお、一度合格した科目は永久に有効となる科目合格制度を導入しているため、一度に全ての試験に合格する必要はありません。何年かかっても5科目合格すれば税理士になれます(※)。
税理士試験の受験科目は、会計科目と税法科目に分けられます。
【会計科目】
簿記論と財務諸表論の2科目で構成されており、どちらも必須科目です。
【税法科目】
選択必須科目と選択科目に分かれます。
●選択必須科目:所得税法と法人税法のいずれかを合格する必要があります
●選択科目:相続税法、国税徴収法、固定資産税、消費税法または酒税法(いずれか一つ)、住民税または事業税(いずれか一つ)から選択することができます
各科目のボリュームや難易度、内容は異なります。得意な科目の選択や、受験科目の組み合わせをうまく選ぶことが、働きながら効率よく学習し合格するためのポイントです。
※参考:国税庁「税理士試験の概要」(2024-11-16)
2年以上の実務経験
税理士法では、税理士試験に合格した者または税理士試験を免除された者は、2年以上の実務経験が必要とされています(税理士法第3条)。税理士登録するためには、税理士試験に合格し、かつ、通算で2年以上の実務経験を積まなければなりません(※)。
実務経験とは「会計に関する事務」を指します。例えば、貸借対照表勘定と損益計算書を使用する経理事務などです。会計事務所に2年間勤務しても、数字の入力のような単純作業だけ行っていたなら実務経験に含まれないため注意しましょう。
※参考:国税庁「税理士の登録」(2024-11-16)
社会人が税理士になる4つの方法
社会人が税理士になるには以下の4つの方法があります(※)。
1.税理士試験合格+2年間の実務経験
2.大学院修了+税理士試験(一部免除)合格+2年間の実務経験
3.弁護士または公認会計士になる(有資格者を含む)
4.国税専門官として23年勤務する(10年勤務で一部科目免除)
一般的な方法は、税理士試験合格と2年間の実務経験を積むものです。
博士や修士を取得している人は税理士試験の科目が一部免除されます。そのため、社会人になってから大学院に進学し、税理士を目指す方法もあります。
また、弁護士や公認会計士の有資格者は各資格の登録をしていなくても、税理士会に登録できます。どちらかの資格を取得した上で税理士になるのも一つの方法です。
さらに、国税専門官で10年勤務すると税法3科目が免除されるため、会計2科目を取れば働きながら税理士になれます。また、23年勤務すると税法3科目と会計2科目の5科目が免除されるため、税理士試験を受けることなく税理士登録が可能です。これから働く人は、国税専門官を目指すルートもあります。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
税理士試験の勉強時間と合格率
働きながら税理士を目指すなら、各科目の標準的な勉強時間や合格率を確認し、5科目合格までの計画を立てると良いでしょう。本項では税理士試験の各科目に合格するために必要な勉強時間の目安や、合格率、平均合格年数についてご紹介します。
各科目の勉強時間の目安
各科目に合格するために必要な勉強時間の目安は以下の通りです。
| 科目名 | 勉強時間 |
| 簿記論 | 400時間 |
| 財務諸表論 | 450時間 |
| 所得税法 | 600時間 |
| 法人税法 | 600時間 |
| 相続税法 | 400時間 |
| 国税徴収法 | 150時間 |
| 固定資産税 | 200時間 |
| 消費税法 | 300時間 |
| 酒税法 | 300時間 |
| 住民税 | 300時間 |
| 事業税 | 200時間 |
ただし、これらの時間は目安であり、勉強時間だけで合格が保証されるわけではありません。
各科目の合格率
合格率の把握は、効率的な合格への道筋を立てる上で重要です。
以下はある年の各科目の合格率です。
| 受験者数 | 合格率 |
| 簿記論 | 23.0% |
| 財務諸表論 | 14.8% |
| 所得税法 | 14.1% |
| 法人税法 | 12.3% |
| 相続税法 | 14.2% |
| 消費税法 | 11.4% |
| 酒税法 | 13.2% |
| 国税徴収法 | 13.8% |
| 住民税 | 17.2% |
| 事業税 | 14.1% |
| 固定資産税 | 18.4% |
最も高い合格率でも簿記論の23.0%であり、合格率は低いことが分かります。5科目合格し税理士試験の関門を突破できるのはごくわずかな人のみです。
実際の受験では、合格率を考慮して科目を選ぶことはあまり一般的ではありません。科目のボリュームや実務での重要度を考慮して科目を選ぶことが大切です。
税理士試験の平均合格年数
税理士試験の勉強に専念できる人の方が平均合格年数は短いと思われがちですが、実際は働きながら勉強しても短期間で合格するケースは存在します。
就業の有無を問わず合格期間の目安は2~10年、平均8年程度とされています。ただし、10年以上かかることも珍しくありません。2年以内の合格は極めてまれです。
働かず税理士を目指すときの平均合格年数
大手専門学校では、1年間で2〜3科目の合格を目指すカリキュラムが採用されています。よって順調に合格していけば、2〜3年間で税理士試験に合格できる計画です。ただし、合格率が低いため、一般的にはカリキュラム通りとはいかず、さらに数年かかることが多いです。
働きながら税理士を目指すときの平均合格年数
働きながら受験する場合、多くの大手専門学校では1年で1科目の合格を目指すカリキュラムを採用しています。従って、就職後1年ごとに受験科目に合格すれば、通常は5年間で税理士試験に合格できるのです。
ただし、実際には1つの受験科目の合格には複数年を要することが一般的です。予定よりも合格までの年数が長くなることが多いでしょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
科目の選び方や傾向
働きながら税理士を目指す場合、勉強に充てられる時間は限られています。自分に合った科目や、一般的な科目の取り方を確認し、効率的に合格を勝ち取りましょう。
勉強時間の少なさだけで科目を選ばない
一般的には、酒税法や国税徴収法、事業税、住民税、固定資産税など勉強時間のボリュームが少ない科目を選びがちです。しかし、ボリュームが少ないからといって、合格が容易なわけではありません。税法を学ぶ際には、自身が興味を持てる科目を選ぶことが重要です。
まずは会計科目から取得する
税理士試験では、必須科目の「簿記論」と「財務諸表論」の2科目を先に取得するのが王道です。これらの科目は比較的学びやすいだけでなく、税法を学ぶときの基礎知識となるため、まずは会計科目攻略を目指しましょう。
理由1.会計科目は比較的合格しやすい
簿記論と財務諸表論の受験者の中には、税理士試験初心者が多くいます。実際には、「記念受験」と呼ばれる受験生も存在し、合格する可能性がほぼゼロの人もいます。税理士試験は競争試験とされるため、受験者全体のレベルが低い方が合格する可能性は高いでしょう。
理由2.会計科目は丸暗記が少ない
簿記論は100%計算問題から構成されています。財務諸表論は50%が計算問題、50%が理論問題です。一方、税法科目は基本的には50%が計算問題、50%が理論問題となっています。
財務諸表論の理論問題と税法科目の理論問題は、少し異なる性質を持っており、税法科目の理論問題に解答するには、税法条文の丸暗記が必要です。難解な税法条文を完全に丸暗記するには、膨大な時間と労力がいるため、初学者は挫折する可能性が高いです。
一方、財務諸表論の理論問題では、一言一句を丸暗記する必要はありません。重要なキーワードを盛り込んで自分の言葉で説明します。
税法は法人税・相続税・消費税の組み合わせが多い
税法は選択必須科目で利用頻度の高い法人税と、実務でよく使われる相続税・消費税の組み合わせが多いです。この組み合わせが学習のボリュームと、実用性のバランスが良いでしょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
働きながら税理士を目指すメリット
ここからは、働きながら税理士を目指す3つのメリットを紹介します。
メリット1.収入を確保しながら勉強できる
働きながら税理士を目指す大きなメリットは、収入源を確保できる点です。多くの人は予備校に通いながら税理士試験合格を目指すものの、授業料は5科目セットで80万~100万円程度かかります。さらに、この他に生活費も必要なため、親の援助や貯金などがないのであれば、働きながら税理士を目指した方が金銭的な心配は少なくなります。
メリット2.税理士に必要な実務経験を積める
会計事務所で税理士補助の仕事をしながら税理士を目指せば、勉強をしながら登録に必要な2年間の実務経験を積めます。試験合格後はすぐに税理士に登録でき、現場の感覚も養われているため独立も視野に入れやすいでしょう。
メリット3.職歴の空白期間を防げる
働きながら税理士を目指せば職歴に空白期間ができないため、就職・転職もしやすくなります。税理士試験は勉強すれば誰でも合格できるものではなく、諦めざるを得ないときもあります。もし予備校を卒業した後、税理士試験のみに専念して職歴に空白期間ができれば、そこから就職先を探すのは困難かもしれません。仕事をしていれば、万が一試験がうまくいかなかったときも職歴は保証されます。
働きながら税理士を目指すデメリット
続いては、働きながら税理士を目指す3つのデメリットも紹介します。
デメリット1.勉強時間の捻出が困難
昼休みや帰宅後の時間、休日など、働いていると勉強に充てられる時間は限られます。さらに、どうにか時間を捻出しようにも、業務内容や勤め先によっては残業や休日出勤が多く、勉強が進まないかもしれません。
デメリット2.モチベーションが下がりやすい
すでに仕事があり、一定の収入を得られる安心感から、税理士になるモチベーションが下がる恐れもあります。 また仕事の疲れにより、勉強にまで手が回らないことも考えられます。
働きながらモチベーションを維持したいなら、税理士を目指す人が多い職場を選ぶと良いでしょう。
デメリット3.家族の理解を得にくい
税理士試験に合格し転職や独立をしたいと考えていても、家族の理解を得られるとは限りません。仕事と税理士試験の勉強を両立するとなれば、家族との時間は犠牲になりがちです。
すでに家庭がある人は特に、いつまでに何科目に合格するなど、将来の見通しを立ててから挑戦すると良いでしょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
働きながら税理士試験に合格する方法
税理士試験は、社会人の受験生が非常に多い試験です。しかし、社会人は学生と比べて受験勉強に割ける時間が限られています。限られた時間を活用して効率的に勉強を進め、最終的に5科目に合格するためには、綿密な計画が重要です。
ここからは、働きながら税理士試験合格を目指す方法を紹介します。
勉強時間の確保と習慣化
勉強時間を確保するためには、日々のスケジュールを工夫する必要があります。合格の秘訣は日常の時間を確保し、忙しい中でも受験勉強を進めることです。例えば、通勤時間や昼休みなどの隙間時間には、参考書やアプリを使って理論暗記をすると良いでしょう。
また、数年にわたる受験勉強は意志の力だけではなかなか続けられないものです。自宅では勉強に集中できなかったり、気が緩んだりするなら、予備校の自習室やカフェなど、自分にとって集中しやすい環境を探すことも有効です。
予備校や専門学校の利用
予備校や専門学校の利用も考慮しましょう。急な飲み会や遊びの誘いなど、社会人には誘惑が多くあります。とはいえ、言い訳ばかりしていても受験勉強は進まず、税理士試験も待ってくれません。
予備校を利用すれば、学習ペースを維持する助けになるでしょう。受講料は数十万円かかるかもしれませんが、税理士になればすぐに回収できる投資です。自分自身への投資として、積極的に予備校の環境を活用しましょう。
1年で1科目の合格を目指す
1年で1科目の合格を目指し勉強を進めましょう。先述のように、税理士試験は1度合格した科目は受験を免除される「科目合格制度」を採用しているため、1年に1科目だけ受験しても問題ありません。
学生のように会計科目と税法科目を同時に学習するには時間が足りず、理解も追いつきません。一点集中で1科目ずつ攻略しましょう。
税理士試験を応援してくれる会計事務所に転職する
会計事務所の中には、税理士を目指す人を応援する制度や仕組みがある所もあります。働きながら税理士を目指すなら労働環境は特に重要なため、サポート制度の充実した事務所や会社に転職するのもおすすめです。
税理士試験に理解のある会社であれば、同じように税理士を志す同期も多く、情報交換ができ、モチベーションの維持にもつながります。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
働きながら税理士を目指しやすい会計事務所の特徴
勤務時間の調整や試験直前の有給付与など、資格取得のサポート制度が充実した会計事務所であれば、働きながら税理士を目指しやすいです。本項では、税理士の勉強と仕事の両立がしやすい会計事務所の特徴を解説します。
税理士を目指す人が働いており合格者も出ている
働きながら税理士を目指しやすい会計事務所を見極めるためにも、応募や面接の際には、実際に税理士を目指す人が働いているかを確認しましょう。会計事務所の中には資格取得の補助制度があっても、激務により勉強時間を確保できない事務所もあります。税理士を目指す人が働いており、科目合格者や税理士登録者が出ているなら、働きながら税理士を目指せる何よりの証拠です。
業務量を調整できる
残業のない働き方ができる、試験前は業務量を減らせるなど、業務量を柔軟に調整できると、仕事と勉強の両立が一気にしやすくなります。業務量の調整が難しければ、原則残業なしなど、定時で帰れる事務所でも良いでしょう。会計事務所の中には業務の効率化により、繁忙期でも残業がほとんど生じない事務所もあります。
勤務方法を選べる
勤務方法や勤務時間を選べることも重要です。時短勤務の他に、在宅勤務などを選べれば、本来通勤に充てていた時間も勉強に使えます。さらに、勤務する曜日や時間帯を調整できれば、予備校にも無理なく通えるでしょう。
資格取得を支える制度がある
会計事務所によっては、税理士資格の取得を支える制度を提供している場合があります。以下はその一例です。
●予備校代・授業料の全額または一部補助制度
●資格取得のための大学院費用補助制度
●オンライン動画教材導入
●税理士試験前日・当日休暇
●会議室の勉強スペースとしての貸し出し
●資格手当 など
複数の制度を導入し税理士試験をサポートしている事務所も多いため、求人情報を確認しましょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
仕事と勉強を両立するスケジュールの組み方
仕事と税理士試験の勉強を両立するためには、先にスケジュールを作成し、計画的に勉強を進めることが大切です。スケジュールの組み立て方の一例を紹介します。
1.一週間で確保できる学習時間を把握する
2.週の総合学習時間を元に長期目標を設定する
3.年間スケジュールを立てる
4.一日のスケジュールを立てる
5.週間スケジュールを立てる
1.一週間で確保できる学習時間を把握する
まずは、一週間でどの程度学習時間を確保できるか算出しましょう。なお、学習時間は理想値ではなく、現実的な値を想定してください。例えば「睡眠時間を4時間に削り平日5時間勉強する」など、無理な設定をすれば計画自体が破綻します。勉強できる日・できない日も含め、平均的に毎日どの程度時間を取れるかを確認し週の合計を出しましょう。
2.週の総合学習時間を元に長期目標を設定する
以下の1週間当たりの総学習時間を元に、長期目標を設定します。目安は以下の通りです。
●週10~15時間:1年で1科目の合格を目指す
●週15時間以上:1年で2科目の合格を目指す
1週間で10~15時間確保できれば、年間520~780時間勉強できます。よって1年に1科目の合格であれば、十分に目指せるでしょう。
1年に取得する科目数が決まったら、何年間でどのように科目を取り、税理士を目指すかプランを立てましょう。
【例】週10時間勉強できる場合
| 年数 | 取得科目 | 学習時間の目安 |
| 1年目 | 簿記論 | 400時間 |
| 2年目 | 財務諸表論 | 450時間 |
| 3年目 | 法人税法 | 600時間 |
| 4年目 | ||
| 5年目 | 相続税法 | 400時間 |
| 6年目 | 消費税法 | 300時間 |
3.年間スケジュールを立てる
税理士試験は例年、8月上旬の連続する3日間で行われます。年間スケジュールでは、試験日までの学習スケジュールや模試の日程などを記載しましょう。併せて、税理士試験の申込日や外せない私的な予定も記載すると、年間の動きが把握しやすくなります。
4.一日のスケジュールを立てる
一日の中で何時頃、どの程度勉強するかのスケジュールを立てましょう。作成するときは、仕事や睡眠など必要な時間から先に埋め、余った時間を勉強時間に設定します。
【例】平日の勉強時間
| 6:00 | 起床 |
| 6:00~8:00 | 勉強 |
| 8:00~9:00 | 出勤準備・出勤 |
| 9:00~18:00 | 仕事 |
| 18:00~19:00 | 退社・帰宅 |
| 19:00~21:00 | 予備校・夕食 |
| 21:00~22:00 | 入浴・自由時間 |
| 22:00~24:00 | 勉強 |
| 24:00~6:00 | 就寝 |
一日のスケジュールは平日と休日で異なるため、それぞれの分を作成します。
5.週間スケジュールを立てる
一日のスケジュールを元に、週間スケジュールを作成しましょう。週間スケジュールでは、具体的にどのような勉強をするか記載します。例えば「平日の朝の1時間は前日の復習をする」などです。
週間スケジュールは極限まで勉強時間を詰め込むのではなく、予定通りに進まなかったときに調整する「予備日」を設けるのがポイントです。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
未経験者が会計事務所に転職するには
最後に、業界経験者が会計事務所に転職する方法を紹介します。まずは経理業務の経験を積むか、日商簿記や税理士科目を取得するのがおすすめです。また、求人は「未経験者可」としているものを探しましょう。
経理業務を経験する
経理業務の実務経験を持つ人は評価される傾向にあります。金融機関などで決算書などの業務経験がある人は、より有利です。ただし、資格のように能力を客観的に証明できないため、どのような業務を担っていたか具体的に説明しましょう。
日商簿記を取得する
日商簿記があれば会計業界の就職には有利なものの、採用されやすい雇用形態が異なります。
●日商簿記3級:パート・アルバイト
●日商簿記2級:パート・アルバイト、一部の正社員
●日商簿記1級:正社員
正社員として活躍したいなら、2級以上の取得を目指しましょう。
税理士試験の科目に合格する
税理士試験の科目に合格している人は、高く評価される傾向にあります。例えば「簿記論」と「財務諸表論」の2科目に合格していれば、未経験者でも基礎知識を持っており、成長の余地があると判断されやすくなります。
会計事務所で働きながら税理士を目指そう!
働きながら税理士を目指すことは可能です。しかし、仕事と勉強を両立するなら、ある程度の勉強時間が確保できる労働環境が不可欠です。今の事務所では勉強時間を確保できないなら、転職を検討しても良いでしょう。
会計士・税理士事務所の求人・転職サイト「会計求人プラス」では、資格取得者を応援する制度が整った会計事務所の求人を数多く取り扱っています。働きながら税理士を目指している方は、ぜひ以下のリンクよりご登録の上、就職・転職活動にお役立てください。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
資格取得を支援してくれる求人をご紹介!
投稿者情報

- 現役の税理士として10年以上、会計事務所に勤務しているかたわら、会計・税務・事業承継・転職活動などの記事を得意として執筆活動を5年以上しています。実体験をもとにしたリアルな記事を執筆することで、皆さんに親近感をもって読んでいただけるように心がけています。
最新の投稿
 税理士2025.06.29独学で税理士試験合格はできる?合格を勝ち取るポイントを解説
税理士2025.06.29独学で税理士試験合格はできる?合格を勝ち取るポイントを解説 税理士2025.06.22税理士の平均年収の現実とは?税理士の給料を年齢別や働き方別に解説!
税理士2025.06.22税理士の平均年収の現実とは?税理士の給料を年齢別や働き方別に解説! 税理士の仕事2025.05.29税理士の独立開業は厳しい?業界事情や開業に失敗する原因、成功のポイントをご紹介
税理士の仕事2025.05.29税理士の独立開業は厳しい?業界事情や開業に失敗する原因、成功のポイントをご紹介 税理士試験2025.05.21実務経験なしから税理士になるには?税理士登録に必要な要件や経験を積める場所を解説
税理士試験2025.05.21実務経験なしから税理士になるには?税理士登録に必要な要件や経験を積める場所を解説