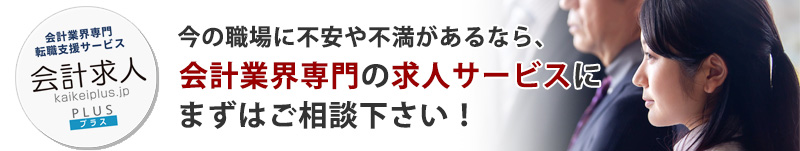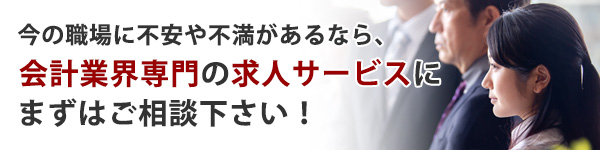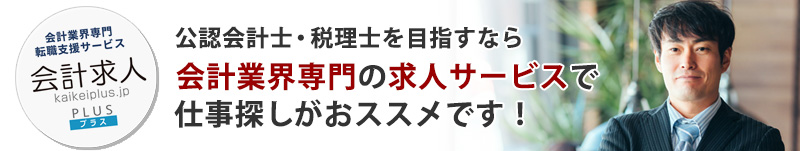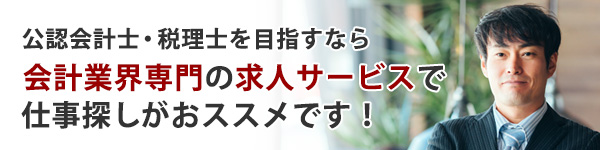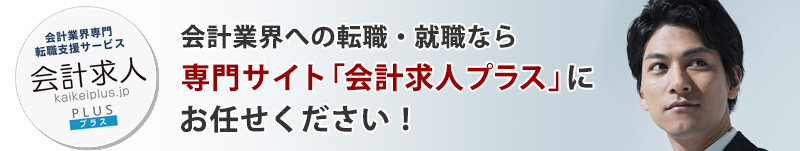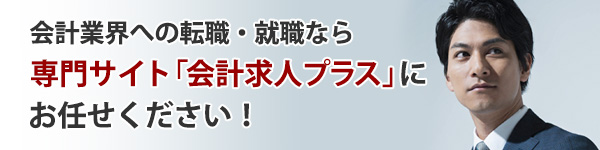税理士試験に合格後のキャリアパスとは?選択肢とそれぞれの特徴を解説
税理士試験合格後のキャリアパスには複数の選択肢があり、それぞれ特徴やメリットに違いがあります。自身の得意分野や特性、働き方で重視することなどを基に、慎重にキャリアパスを選択しましょう。
本記事では、税理士試験合格後のキャリアを考える重要性や、税理士になるために必要なステップ、主なキャリアパスとそれぞれのメリット・デメリット、キャリアパスを選ぶ際のポイントについて解説します。
■□■□会計業界へ効率的に転職活動を進めるなら専門転職サイト「会計求人プラス」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□
コンテンツ目次
税理士試験合格後のキャリアを考える重要性

難関である税理士試験に合格したことは非常に大きな強みです。しかし、試験合格はあくまでスタート地点のため、合格後はなるべく早めに今後のキャリアパスを考える必要があります。
なぜ合格後すぐに将来のキャリアを考える必要があるのか、その理由は大きく分けて2つあります。
1. キャリアパスが複数ある
税理士の資格を取得した後の主なキャリアパスは、開業税理士・社員税理士・所属税理士の3つに分類されます。それぞれ勤務場所や働き方、メリットなどに違いがあるため、どの道に進むべきなのか、早めに選択しなければなりません。
将来のキャリアを考えないまま「とりあえず所属税理士を目指そう」など曖昧な基準でキャリアを選択してしまった場合、後から「やっぱり社員税理士になりたい」「独立開業したい」と考えて進路変更を行う場合、必要以上に回り道をしてしまう可能性があります。
もちろん、他のキャリアパスを経ることで得られるものもありますが、最短距離で理想のキャリアを目指したいという場合は、合格後すぐに将来のキャリアについてじっくり考えた方が良いでしょう。
税理士のキャリアパスについて、詳しくは後述します。
2. 実務経験を積む場所の選択肢が豊富
税理士の資格を取得するには、試験への合格だけでなく、通算2年以上の実務経験を積まなければなりません。
ここでいう実務経験とは租税や会計に関する事務のことで、税務署や税理士事務所、会計の経理部門などの業務がこれに該当します。
どこで実務経験を積むかは自由ですが、それぞれ業務内容や得意分野に違いがあるため、どの場所で経験を積むかによって習得できる知識やスキルにも差が出てきます。
また実務経験を積んだ場所がそのまま税理士として勤める職場になるケースも少なくないため、早めに将来のキャリアを考え、どこで実務経験を積むのが理想なのか検討しておくことが大切です。
働き方を改善したいなら
「会計求人プラス」
「残業が多い」「テレワーク対応した職場で働きたい」と思っていませんか? 会計事務所・税理士事務所で働き方を変えたいなら、専門の転職・求人サイト「会計求人プラス」がおすすめです。
税理士になるには?試験合格後のステップを解説

税理士になるには、税理士試験に合格した後、実務経験を満たした上で所定の登録手続きを済ませる必要があります。試験合格=税理士の資格取得というわけではないため、合格後にやらなければならないことをきちんと把握しておきましょう。
ここでは試験合格後、税理士として働くために必要なステップを説明します。
実務経験を積む
前述した通り、税理士の資格を得るためには通算2年以上の実務経験を積む必要があります。この実務経験の内容は税理士法基本通達3-1にて、税務官公署における事務の他、その他の官公署および会社等における税務または会計に関する事務を指すと明記されています(※)。
上記の事務を通算2年(途中で職場が変わってもOK)以上行えば、税理士資格取得の要件を満たすことが可能です。
ただし、特別な判断を必要としない機械的な事務については、たとえ会計や経理業務の一環であっても実務経験とは見なされません。
具体的には、データ入力といった簿記会計に関する知識がなくても行える単純な業務は、特別な知識やスキルがなくてもこなせる単純作業に該当するため、税理士資格の実務経験にはカウントされません。
一方、以下のような事務は簿記会計に関する知識を要する業務と見なされるため、実務経験として累積されます。
●簿記の原則の下、簿記上の取引について行われる取引仕訳事務
●仕訳帳などから各勘定に転記する事務
●元帳を整理し、日計表または月計票を作成し、その記録が正確かどうかを判断する事務
●決算手続きに関する事務
●財務諸表の作成業務
●帳簿組織の立案や、原始記録と帳簿記入の事項を照合点検する事務
実務経験に該当するか否かは、申請に対して行われる税理士会の調査によって個別に判断されます。実務経験に該当するかどうか分からない場合は、お住まいの都道府県を管轄している税理士会に問い合わせてみましょう。
なお、実務経験を積むタイミングに明確な規定はなく、試験の合格前でもカウントされます。実際、実務経験を積みながら税理士試験の合格を目指す方も多くいます。
税理士試験合格後、すぐに税理士として働き始めたいのなら、合格前から計画的に実務経験を積んでみてはいかがでしょうか。
※参考:国税庁.「第2条《税理士業務》関係」. ,(参照2025-02-18).
税理士の登録申請を行う
実務経験を満たしたら、管轄の税理士会にて税理士の登録申請を行います。
申請手続きには以下の書類が必要です。
1.税理士登録申請署
2.登録免許税領収証書
3.写真
4.住民票の写し(本籍の記載がある世帯全員のもの)
5.身分証明書
6.資格を証する書類
7.履歴書
8.誓約書
9.税理士会会長宛の誓約書
10.直近2年分の確定申告書のコピー(確定申告をしていない場合は住民税の非課税所得証明書)
11.日本税理士会連合会所定のはがき
以上は申請手続きを行う全ての方が提出しなければならない書類です。
1、7~9の書類に関しては様式が決まっているため、税理士会の窓口か、あるいは税理士会の公式Webサイトからダウンロードして入手しましょう。
6の資格を証する書面とは、税理士試験合格証書(人によっては当区別税理士試験合格証書や税理士試験免除決定通知書)の写しのことです。
上記の書類に加え、実務経験の要件を満たしていることを確認する書類として、以下のものを提出します。
1.在職証明書
2.在職証明書に係る印鑑登録証明書
3.源泉徴収票または確定申告書の写し
4.税理士事務所と会計法人の関係に関する書類
5.職務概要説明書
6.勤務時間の積上げ計算書
7.大学院通学状況説明書
4~7は状況に応じて提出が必要となる書類です。
上記の他にも、無職期間の事情説明書や退職理由説明書などの書類の提出を求められることもあります。実際にどの書類を提出するかは申請内容や税理士会によって異なるため、申請手続きを行う前に、どのような書類が必要なのか管轄の税理士会に問い合わせておきましょう。
なお、税理士の登録には6万円の登録免許税と、5万円の登録手数料を納めなければなりません。前者は国税収納機関で納めて登録免許税領収証書を受け取り、後者は税理士会の指定する方法で納付することになります。
税理士の登録申請手続きには明確な期限がなく、好きなタイミングで手続きしてかまいません。
ただ、税理士登録には税理士会や日弁連による調査や審査を伴うため、手続きを行ってから実際に登録されるまでにはある程度の日数を要します。
申請手続きが遅れると、税理士登録される日も後ろ倒しになってしまうため、税理士としてすぐに働き始めたいのなら、登録の要件を満たした時点で早めに手続きを済ませましょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
税理士試験合格後の主要なキャリアパス3選
税理士試験に合格した後のキャリアパスには、主に開業税理士、社員税理士、所属税理士の3つがあります。それぞれの役割には特徴があり、個々の働き方や目指すキャリアに応じて選択することが重要です。
開業税理士
開業税理士は、自ら独立した税理士事務所を設立し、主宰者として業務を行う税理士です。個人事業主として認識され、税理士会に開業税理士として登録し、開業届を税務署に提出する必要があります。収入は事業所得として扱われます。開業税理士の特徴として、業務の全てを自主的に決定できることが挙げられます。営業時間、提供するサービス、事務所の場所、クライアントの選択などを自由に決めることができます。また、クライアントと直接契約し、対価を受け取ることが可能であり、事務職員や他の税理士を雇用して事業を拡大することもできます。
開業税理士のメリットとして、収入に上限がなく成功すれば高収入が期待できること、仕事の自由度が高くクライアントや専門分野を自由に選べること、事業を成長させ長期的なキャリアの安定を築くことができることがあります。一方で、収入が不安定で経営リスクを負うこと、開業資金や運営費用が必要で初期投資がかかること、長時間労働や業務の多様性に対応する必要があることがデメリットとして挙げられます。一般的に、小規模な事務所から始め、クライアントを増やしながら事業を拡大します。専門性を高めたり、他の税理士と協力して法人化したりすることでキャリアの発展が可能です。
社員税理士
社員税理士は、税理士法人のパートナーとして経営に関与する税理士を指します。税理士法人の設立に参加するか、既存の法人に加入して社員税理士となります。社員税理士は税理士法人の経営者として、事業運営と税務業務の両方に関与し、事務所の方針決定、クライアント獲得、業務管理などの責任を担います。
社員税理士のメリットとして、収入が比較的安定しながら法人の利益配分によって高収入も可能なこと、法人の資源を活用し大規模なクライアントへの対応ができること、経営に携わることで事務所の成長を実現できることが挙げられます。一方で、経営リスクを負い法人の業績に影響されること、経営やマネジメントの責任が重くなること、開業税理士ほどの独立性はないことがデメリットとなります。所属税理士として経験を積んだ後に社員税理士へ昇格するケースが多く、法人の業績に貢献し実績を積むことで経営層に加わる道が開けます。
所属税理士
所属税理士は、開業税理士や税理士法人に雇用され、税務業務に従事する税理士です。雇用契約のもとで業務を行い、事務所の方針に従って業務を遂行します。主に税務申告書の作成、税務相談、監査の補助などを担当し、事務所のチームの一員として上級税理士の指導を受けながらスキルを磨くことができます。
所属税理士のメリットとして、収入が安定しており生活設計がしやすいこと、研修制度や経験を通じて専門知識を深められること、事務所の経営リスクを負う必要がないことがあります。デメリットとしては、給与制のため収入に上限があること、独自の判断で業務を進める自由度が低いこと、事務所の方針に従う必要があり意思決定の裁量が少ないことが挙げられます。所属税理士として経験を積み、専門性を高めることで将来的に開業税理士や社員税理士へとキャリアアップすることが可能です。大規模事務所ではマネージャー職やパートナー昇進の道も開かれています。
最適な求人を探すなら
「会計求人プラス」
会計求人プラスは、「会計事務所、経理専門の求人・転職サイト」です。会計業界に関連する求人のみを扱っているため、知りたい情報、希望する条件に合った求人が見つかります!
税理士試験合格後は、進むべきキャリアパスについてきちんと考えよう
税理士試験に合格した後のキャリアパスには、開業税理士、社員税理士、所属税理士の3つがあります。
それぞれ、働き方や収入の安定性、業務内容などに違いがあるため、将来どのような税理士になりたいのか、税理士として何を重視するのかなどを基準に、自身の希望に合ったキャリアパスを選択することが大切です。
なお、社員税理士や勤務税理士の場合、所属する事務所によって習得できるスキルや働きやすさに差が出てくるため、職場選びも慎重に行いましょう。
会計士・税理士事務所の求人に特化した会計求人プラスでは、希望する勤務地や雇用形態、事務所区分、働き方などから求人情報を絞り込み検索することが可能です。
「自分の理想とする働き方が分からない」「設計したキャリアパスに適した職場を探したい」といった悩みや要望がある方は、ぜひ会計求人プラスをご利用ください。
最適な求人を探すなら
「会計求人プラス」
会計求人プラスは、「会計事務所、経理専門の求人・転職サイト」です。会計業界に関連する求人のみを扱っているため、知りたい情報、希望する条件に合った求人が見つかります!
投稿者情報

- 税理士や公認会計士、会計業界に関する記事を専門に扱うライター。会計業界での執筆歴は3年。自身でも業界についての勉強を進めながら執筆しているため、初心者の方が良く疑問に思う点についてもわかりやすくお伝えすることができます。特に業界未経験の方に向けた記事を得意としています。
最新の投稿
 税理士の仕事2026.01.18会計と税務の違いを解説!会計業界で働くなら知っておきたい基礎知識
税理士の仕事2026.01.18会計と税務の違いを解説!会計業界で働くなら知っておきたい基礎知識 会計士の仕事2025.10.19公認会計士にMBAは必要?取得のメリット・デメリットと将来性を解説
会計士の仕事2025.10.19公認会計士にMBAは必要?取得のメリット・デメリットと将来性を解説 税理士2025.10.03税理士の仕事内容とは?主な就職先、魅力・やりがいについても解説
税理士2025.10.03税理士の仕事内容とは?主な就職先、魅力・やりがいについても解説 転職市場動向2025.08.18簿記3級の合格率はどれくらい?年度ごとの推移と合格者の傾向を徹底解説
転職市場動向2025.08.18簿記3級の合格率はどれくらい?年度ごとの推移と合格者の傾向を徹底解説