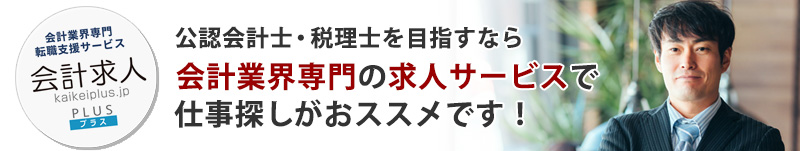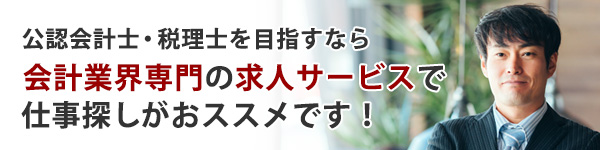公認会計士試験の合格率はどのくらい?難易度や合格者を各種別に徹底分析!
2024/02/02
公認会計士試験を受験したいと思っているけれど、合格率や取得の難しさ、そして資格取得の道のりについての不安や疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
公認会計士試験に挑むのは大学生が多いともいわれていますが、その理由はご存知ですか?
この記事では、公認会計士試験の取得難易度に焦点を当てて詳しく解説します。
さらに、実際にどのような受験者が合格しているのか年齢別や職業別など各種分類に分けて検証してみます。また社会人として働きながらの資格取得が実現可能かという点についても触れています。ぜひ、参考にしてください。
なお、公認会計士(CPA)と税理士の試験難易度の違いに関しては、以下の記事で詳しく比較し、必要な勉強時間やその他の情報もわかりやすく紹介しています。
⇒公認会計士試験の難易度はどれくらい?税理士試験との違いとは?必要な勉強時間もわかりやすく解説
■□■□会計業界へ効率的に転職活動を進めるなら専門転職サイト「会計求人プラス」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□
コンテンツ目次
公認会計士試験の合格率は?
公認会計士(CPA)は国家資格であり、その試験である公認会計士試験の突破には相当な努力が求められます。受験者は、試験の難易度や合格率を事前に確認し、効率的な学習スケジュールや勉強時間の計画を立てることが重要です。
以下は、好評された過去5年間の公認会計士試験の受験者数と合格者数及び合格率のデータを示す表です。
直近、5年館の出願者数は増加傾向にあり、令和5年(2023年)には2万人を超えました。合格者数も1,500人を超えており、コロナ禍を経てもニーズが強く人気のある士業の資格であることが伺えます。
| 年度 | 出願者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和1年(2019年) | 12,532人 | 1,337人 | 11.10% |
| 令和2年(2020年) | 13,231人 | 1,335人 | 10.10% |
| 令和3年(2021年) | 14,192人 | 1,360人 | 9.60% |
| 令和4年(2022年) | 18,789人 | 1,456人 | 7.70% |
| 令和5年(2023年) | 20,317人 | 1,544人 | 7.60% |
このデータからも明らかなように、公認会計士試験の合格基準は厳しく、10%前後の合格率を維持しています。このような厳しい難易度を考慮し、試験受験を検討する際には、十分な準備と確固たる決意が求められます。
税理士、司法書士など他試験の合格率と比較
公認会計士の資格を取得することで、キャリアアップや転職を考えている方は多いのではないでしょうか。
また、他の国家資格や難関資格との比較をしている方や、すでに別の国家資格を持っている方にとっても、各試験の合格率は資格取得の選択の参考となるでしょう。
ここで、公認会計士試験以外の、以下の4つの難易度の高い資格の令和5年度(2023年)の合格率を紹介します。
| 他試験 | 合格率 |
|---|---|
| 税理士 | 21.7%(令和5年度実績) |
| 司法書士試験 | 5.2%(令和5年度実績) |
| 司法試験 | 45.34%(令和5年度実績) |
| 医師 | 91.6%(令和5年度実績) |
これらのデータからも、公認会計士試験は他の難関資格と比べても、合格率が低く挑戦的な資格であることが伺えます。
さらに、多くの受験者が大学や専門学校を卒業してすぐに受験しているため、勉強時間をフルに活用しているケースが多いです。
この点を考慮すると、仕事や家庭の責任を持ちながら公認会計士試験に挑むのは、非常に大変な挑戦と言えるでしょう。
公認会計士試験はなぜ難しいのか
公認会計士試験の近年の合格率や他の難関資格との比較を見ると、試験合格を目指す際のハードルの高さが伺えます。では、公認会計士試験がなぜこれほどまでに難しいとされるのでしょうか?
出題内容の難しさが一因となっているものの、以下のようなその他の要因も大きく影響しています。
- 試験科目が多い
- すべての科目を一度に合格する必要がある
- 試験範囲が広い
- 試験内容が複雑
- 試験科目に合った学習方法の確立が必要
- 合格基準点が決まっている
それぞれ解説していきます。
試験科目が多い
公認会計士試験には、短答式と論文式の2つの形式があり、合計で9つの試験科目が設定されています。
短答式試験は4科目から成り立っており、「財務会計論」「管理会計論」「監査論」「企業法」の内容がマークシート形式で問われます。4科目の総得点で合格基準が決まります。
この短答式試験の合格は、次に進む論文式試験の受験資格を得るための必須条件となっています。
論文式試験は「会計学」「監査論」「企業法」「租税法」の基本4科目に加え、「選択科目(経営学・経済学・民法・統計学から1つ選ぶ)」が含まれており、合格の判定は偏差値に基づいて行われます。
すべての科目を一度に合格する必要がある
公認会計士試験は、短答式4科目と論文式5科目の2つの主要な試験形式で構成されています。この試験の内容は非常に広範で、特定の条件を満たすことで一部の試験科目が免除される制度も存在します。しかし、その免除を受けるためには、実務経験や学歴などの特定の条件を満たす必要があります。そして、それぞれの試験科目には異なる基準が適用されます。試験の免除申請や審査待ちの期間など、詳細な情報の収集とスケジュールの管理が必要です。
試験範囲が広い
公認会計士試験は、その試験科目の多さとそれぞれの科目の内容の深さから、非常に幅広い出題範囲を持つ試験として知られています。この広範囲な出題範囲は、受験者にとって多くの時間と努力を要求する要因となっているのです。
短答式試験の「財務会計論」を例に取ると、この科目はかつて「簿記」と「財務諸表論」という2つの独立した科目として出題されていました。これらの2つの科目は、それぞれ異なる会計の基本的な側面をカバーしており、受験者は2つの異なる試験範囲に対応する必要がありました。しかし、2006年以降、これらの2つの科目は「財務会計論」という1つの科目に統合されました。この変更により、受験者は1つの試験で2つの科目の内容を網羅する必要が生じ、その結果、試験の難易度はさらに高まりました。
また、論文式試験の「会計学」は、短答式試験の「財務会計論」と「管理会計論」の内容を統合して出題される科目です。これは、受験者が会計の理論と実践の両方に関する深い知識と理解を持っていることを確認するためのものです。このような統合された試験範囲は、受験者にとってはさらなる挑戦となります。
このように、公認会計士試験はその試験範囲の広さと深さから、受験者にとっては非常に難易度の高い試験となっています。それぞれの試験科目が持つ独自の特性と要求を理解し、それに対応するための適切な学習方法を見つけ出すことが、試験合格への鍵となります。
試験内容が複雑
公認会計士試験は、その内容の深さと幅広さから、非常に高度な複雑さを持つ試験として知られています。この試験は、単に会計の知識を試すだけでなく、法律、経済、経営など、関連する多岐にわたる分野の知識と理解も求められるので難易度が高いのです。
まず、解答方式について考えると、短答式と論文式の2つの異なる方式が存在します。短答式試験は、マークシート方式での回答が主となり、基本的な知識の確認が中心です。一方、論文式試験では、受験者の深い理解と分析能力が試されるため、より高度な回答スキルが求められます。これら2つの方式は、それぞれ異なるアプローチと対策が必要となり、受験者はこの2つの異なる試験方式に適応するための戦略を練る必要があります。
さらに、試験内容の多様性も複雑さを増しています。基本的な簿記の知識はもちろんのこと、税法、会社法、監査論など、多岐にわたるテーマが出題されます。これらのテーマはそれぞれ独自の専門知識を要求し、受験者はこれらの異なる分野に対応するための広範な学習が必要です。
また、公認会計士試験は、単に知識を問うだけでなく、実際の業務における応用力や判断力も試されるため、受験者は実務経験やケーススタディを通じて、実際の業界の状況や課題に対する理解を深める必要があります。
このように、公認会計士試験の内容は多岐にわたり、その複雑さは受験者にとって大きな挑戦となっています。しかし、試験制度の複雑さを乗り越え、試験に合格することで、受験者は真の専門家としての資格と信頼を得ることが可能です。
試験科目に合った学習方法の確立が必要
公認会計士試験は、その多岐にわたる試験内容と高度な難易度から、受験者にとっては困難な挑戦となる試験の一つです。この試験を乗り越えるためには、ただ漫然と学習を進めるだけでは不十分で、各試験科目ごとの戦略的な学習が求められます。
多くの受験者が初めて専門書店や予備校を訪れたり、通信講座やスクールのカリキュラム見ると、その膨大な量の参考書や教材に圧倒されることでしょう。しかし、この多数の教材の中から、自分の学習スタイルや理解度に合わせた最適なものを選ぶことが、効率的な学習の第一歩となります。
各試験科目は、その内容や出題傾向が異なるため、一律の学習方法では十分な効果を得ることが困難です。例えば、法律関連の科目では、条文の暗記やケーススタディを中心に学習を進めることが有効ですが、会計や経済学のような計算を伴う科目では、実際の問題を解く練習が重要となります。
また、知識の習得だけでなく、試験の時間制限内で迅速かつ正確に問題を解く能力も必要です。このため、模擬試験やタイムトライアルを定期的に行い、解答のスピードと正確さを同時に鍛え上げることが求められます。
さらに、公認会計士試験の学習は、単なる知識の詰め込みだけではなく、実際の業務や現場での応用を意識した学習が必要です。実際のケースを元にした問題集や、業界の専門家からのアドバイスを取り入れることで、より実践的な視点からの学習が可能となります。
最後に、公認会計士試験の試験勉強はマラソンのような長期戦です。継続的な努力と、適切な学習戦略のもとでの取り組みが、最終的な成功への鍵となるでしょう。
合格基準点が決まっている
公認会計士試験の合格基準は、他の多くの試験とは異なり、固定された点数以上を取得すれば合格、という明確な基準が設けられていないのが特徴です。この試験の合格基準は、相対評価に基づいており、受験者の中での相対的な順位や得点が合格の判断に影響を与えます。
この相対評価制度の背景には、公認会計士としての資質や能力を一定の水準以上に保つための意図があります。公認会計士は、その専門的な知識や技能を活かして、多岐にわたる業務を担当するため、一定の質を確保することが非常に重要とされています。
しかし、このような評価方法は、受験者にとっては予測が難しく、試験後の自己評価が非常に難しいという側面も持っていることも事実です。例えば、試験を終えて「今回は良い点数が取れた」と自信を持っても、他の受験者の成績が高ければ、その自信が裏切られることも考えられます。
このような相対評価の制度は、短答式試験だけでなく、論文式試験にも適用されています。そのため、受験者はどの試験科目、どの問題形式であっても、一貫して高いパフォーマンスを発揮する必要があります。
さらに、この評価方法は、受験者同士の競争を助長する側面も持っています。ただし、この競争を乗り越え、高い得点を挙げることができれば、それは公認会計士としての高い資質や能力を持っている証とも言えるでしょう。
公認会計士試験の合格基準に関するこの特性は、受験者にとっては厳しいものとなるかもしれませんが、それによって公認会計士としての質が一定以上に保たれるという意味では、業界や社会全体にとっては非常に価値のある制度と言えるでしょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
公認会計士試験の合格者はどんな人?
国家資格の中には多くの高難易度の資格が存在しますが、その中でも公認会計士試験は特に挑戦的なものとして知られています。この厳しい試験をクリアすることができるのは、どのような背景や特性を持つ人々なのでしょうか。公認会計士としての合格を果たす人々の特性や背景を理解することは、これからの受験生にとって有益な情報となるでしょう。このセクションでは、様々な角度からのデータをもとに、公認会計士試験合格者の共通点や特徴について深く探っていきます。
職業別の合格者数
公認会計士試験の合格者の職業背景を詳しく調査すると、多くの合格者が会計関連の職種に従事していることが明らかになります。具体的には、会計事務所のスタッフや、会計士事務所での研修を受けている研修生、さらには大手企業の会計部門での専門家、公的機関の会計担当者、金融機関の経理部門に勤務する者などが目立ちます。
このデータから、会計の実務経験を持つ者が試験に合格しやすい傾向があることが読み取れます。そのため、会計に直接関連しない職種の者が公認会計士の資格を取得しようとする場合、独学や予備校での学習だけでなく、実務経験の獲得も重要であることが伺えます。
年齢別の合格者数
公認会計士試験の合格者の中で、特に25歳から27歳の間の受験者が目立つ結果となっています。この年齢層は、大学や大学院での学習を終え、専門的な知識を深める時期と重なるため、学問に専念できる環境が整っていることが考えられます。
また、20代後半はキャリアの方向性を見直し、新たなチャレンジを考える時期でもあります。そのため、この時期に公認会計士の資格を取得しようとする動機が強まることも予想されます。さらに、会計事務所での初期の実務経験を経て、その後のキャリアアップのために資格取得を目指す方も多いのではないかと考えられます。
学歴別の合格者数
公認会計士試験の合格者には、高等学校を卒業したばかりの方から、大学院を修了した方まで、多岐にわたる教育背景を持つ人々が含まれています。しかし、試験に合格しただけでは、公認会計士としての資格を得るためには、2年間の実務経験と3年の実務補修の要件を満たす必要があります。そのため、学歴よりも、どれだけ迅速かつ効果的に公認会計士試験に合格するか、そして必要な実務経験を積むかが、キャリア形成において重要な要素となります。
男女別の合格者数
公認会計士試験の合格者における男女の割合を見ると、男性が大多数を占めており、約90%を占めています。一方、女性は約10%です。しかし、興味深いことに、男女間での合格率に大きな違いは見られません。実際、公認会計士試験の合格者の中で、4人のうち1人は女性であるというデータが示されています。この背景には、過去10年間で女性の受験者数が増加していることが関連していると考えられます。公認会計士という職種は、男女問わず多くの人々にとって魅力的なキャリアとして認識されており、その人気度は年々上昇していると言えるでしょう。
公認会計士試験に合格した後どうなる?
公認会計士試験に合格した後のステップは、多くの受験者や関心を持つ人々にとっては、まだ明確に知られていない部分が多いでしょう。試験の合格は、公認会計士としてのキャリアの第一歩に過ぎません。実際に公認会計士として活動するためには、さらなるプロセスや手続きを経る必要があります。このプロセスは、専門的な知識や技術を習得し、実務経験を積むことを目的としています。
公認会計士としての資格を持つことは、高度な専門知識を持ち、企業の財務状況や経営状態を的確に評価・分析する能力を持つことを意味します。そのため、試験合格後のプロセスは、これらの能力を身につけるためのものとなっています。
合格後の各ステップは、公認会計士としての実務能力を高めるためのものであり、それぞれのステップが公認会計士としての資質や能力を磨くための重要な役割を果たしています。公認会計士としての活動を開始するまでの道のりは長いかもしれませんが、その過程を経ることで、真の専門家としての資格と能力を身につけることができます。
この後のステップには、監査法人への就職、業務補助、実務補習の受講、修了考査、そして開業登録などが含まれます。それぞれのステップが公認会計士としてのキャリアを築く上での重要な要素となっており、詳しく解説していきます。
監査法人などへ就職
公認会計士試験に合格した後のキャリアパスとして、監査法人や会計事務所への就職は、非常に一般的な選択となっています。この選択の背景には、いくつかの理由やメリットが存在します。
まず、監査法人や会計事務所は、公認会計士の専門的なスキルや知識を最も必要とする場所の一つです。ここでの実務経験は、公認会計士としての専門性を深める上で非常に価値があります。特に、監査法人では、BIG4のような大手企業から中小企業まで、さまざまな規模や業種の企業の財務諸表の監査を担当することになるため、幅広い業界知識や経験を積むことができます。
また、監査法人や会計事務所での業務は、単に数字をチェックするだけでなく、クライアント企業の経営課題やリスクを深く理解し、それに対するアドバイスや提案を行うことも求められます。このような経験は、公認会計士としてのコンサルティング能力やコミュニケーション能力を養う上で非常に有益です。
さらに、監査法人や会計事務所には、公認会計士試験の合格者だけでなく、経験豊富な先輩公認会計士も多数在籍しています。彼らからの指導やアドバイスを受けることで、より高度な専門知識や技術を習得することができます。
結論として、公認会計士試験に合格した後の初めのステップとして、監査法人や会計事務所への就職は、キャリアの基盤を築く上で非常に有意義な選択と言えるでしょう。
3年間の業務補助を行う
公認会計士としての資格を得た後、ただちに高度な業務を担当するわけではありません。実際の業務に携わる前に、3年間の業務補助という重要なステップが待っています。この3年間は、新たな公認会計士が実務の現場での経験を積むための貴重な期間となります。
この業務補助の期間中、新人の公認会計士は、経験豊富な先輩公認会計士の指導のもと、様々な業務をサポートします。これには、財務諸表の監査、税務申告のサポート、クライアントとのコンサルティングなど、多岐にわたる業務が含まれます。
この3年間は、単に補助的な業務を行うだけでなく、実際の業務現場での問題解決の経験を積むことができるため、非常に価値のある時間となります。また、先輩公認会計士からの直接のフィードバックやアドバイスを受けることで、業務の質を向上させるヒントや、専門的な知識の補完を受けることができます。
さらに、この期間中には、クライアントとのコミュニケーション能力や、チームでの協力スキルも養われます。これらのスキルは、公認会計士としてのキャリアを長く続けていく上で、絶対に欠かせないものとなります。
3年間の業務補助は、新人公認会計士が実務の現場での経験を積むための重要な過程であり、この期間を通じて、公認会計士としての実力をしっかりと身につけることができるのです。
3年間の実務補習を受講する
公認会計士を目指す者にとって、3年間の実務補習は非常に重要なステップとなりますが、その集大成としての位置づけられるのが「修了考査」です。この考査は、3年間の実務補習を通じて習得した知識や技術、そして実務経験を基に、その成果を評価・確認するための試験となっています。
修了考査は、公認会計士としての業務を遂行する上で必要不可欠な知識や技術、実務経験がしっかりと身についているかを検証するものです。具体的には、財務諸表の分析や監査技術、税務知識、そして業務に関連する法律や規則に関する知識など、幅広い領域にわたる問題が出題されます。
この考査に合格することは、公認会計士としての資格を正式に得るための最終的な障壁とも言えるでしょう。合格すれば、公認会計士としての資格を手に入れ、その名のもとに様々な業務を遂行することが認められます。逆に言えば、この考査に合格しなければ、3年間の実務補習の成果を正式に認められることはありません。
したがって、修了考査は、公認会計士を目指す者にとって、その能力や資質を証明するための最も重要な試練となります。この試験に合格することで、公認会計士としてのキャリアをスタートさせる扉が開かれるのです。
修了考査に合格する
公認会計士を目指す者にとって、3年間の実務補習は非常に重要なステップとなりますが、その集大成として位置づけられるのが「修了考査」です。この考査は、3年間の実務補習を通じて習得した知識や技術、そして実務経験を基に、その成果を評価・確認するための試験となっています。
修了考査は、公認会計士としての業務を遂行する上で必要不可欠な知識や技術、実務経験がしっかりと身についているかを検証するものです。具体的には、財務諸表の分析や監査技術、税務知識、そして業務に関連する法律や規則に関する知識など、幅広い領域にわたる問題が出題されます。
この考査に合格することは、公認会計士としての資格を正式に得るための最終的な障壁とも言えるでしょう。合格すれば、公認会計士としての資格を手に入れ、その名のもとに様々な業務を遂行することが認められます。逆に言えば、この考査に合格しなければ、3年間の実務補習の成果を正式に認められることはありません。
したがって、修了考査は、公認会計士を目指す者にとって、その能力や資質を証明するための最も重要な試練となります。この試験に合格することで、公認会計士としてのキャリアをスタートさせる扉が開かれるのです。
開業登録を行う
公認会計士としての修了考査をクリアした後、次のステップとして独立開業を目指す方は「開業登録」の手続きを進めることとなります。この開業登録は、公認会計士として正式に業務を行うための許可を得るためのもので、登録が完了しないと公認会計士としての業務を開始することはできません。
開業登録を行う際には、所在地や事務所の設備、業務内容などの詳細情報を提供する必要があります。また、公認会計士としての業務を適切に行うための基準や規定を遵守することが求められます。
開業に際しては、事務所の立地選びや内装、設備の整備など、物理的な準備だけでなく、業務内容や専門分野の選定、クライアントの獲得戦略など、ビジネスとしての側面も考慮する必要があります。特に、クライアントの獲得は新規開業者にとっての大きな課題となることが多いため、ネットワーキングやマーケティング戦略の構築も欠かせません。
さらに、公認会計士としての信頼性や専門性を高めるための継続的な研修や学びも必要となります。開業後も業界の動向や最新の情報をキャッチアップし、クライアントに最適なサービスを提供するための努力が求められるのです。
公認会計士試験に不合格だった場合どうなる?
公認会計士試験は、その高い難易度から多くの受験者が挑戦するものの、残念ながら不合格となるケースも少なくありません。不合格となった場合、受験者は様々な感情や状況に直面することとなりますが、その後の選択や取り組み方によって、未来のキャリアや人生の方向性が大きく変わることも考えられます。
●再挑戦の選択
不合格となった受験者の中には、次回の試験に再挑戦することを選ぶ者も多いです。この場合、前回の試験での経験や反省点を活かし、更なる学習や準備を行うことが求められます。再挑戦することで、過去の失敗を乗り越える経験や成長を得ることができるでしょう。
●キャリアの再検討
一方で、試験に再挑戦することなく、他のキャリアパスや職種を検討する者もいます。公認会計士試験の学習で得た知識やスキルは、他の職種や業界でも十分に活かすことができるため、新しい道を模索することも一つの選択肢となります。
●サポートの活用
不合格となった受験者は、専門の予備校やコーチングサービスを活用して、次回の試験に向けたサポートやアドバイスを受けることも考えられます。専門家からのフィードバックや指導を受けることで、効率的な学習方法や試験対策を練ることができるでしょう。
公認会計士試験に不合格となったとしても、それは一時的な結果に過ぎません。多くの成功者が、過去に何度もの失敗や挫折を経験していることを思い出し、前向きな姿勢で次のアクションを考えることが重要です。
公認会計士が難しくても人気の理由
公認会計士試験は、多くの資格と比較しても、その合格難易度が非常に高いと言われています。多くの受験者が日常の仕事を持ちながら、この試験に合格を目指すのは、確かに大変な挑戦となります。
しかし、そんな厳しい試験にもかかわらず、多くの人々が公認会計士の資格を目指す背景には、何らかの独特の魅力や価値が存在するのでしょうか。
公認会計士という資格は、その高い難易度がゆえに、社会的な信頼性や認知度が非常に高いのです。この資格を持つことで、就職活動や転職の際に、企業からの評価が大きく向上することが期待されます。また、公認会計士は、専門的な知識や技術を持つプロフェッショナルとして、多くの企業や組織からの信頼を得ています。
さらに、試験に合格するだけでなく、その後の実務経験の積み重ねも必要とされるこの資格は、持続的な学びや成長を求められるものとなっています。このような点から、公認会計士が持つ独自の価値や魅力、そしてその人気の理由を深堀して考察してみると、多くの要因が絡み合っていることが理解できるでしょう。
高い年収が期待できる
キャリアの選択や転職の際、多くの人々が考慮する要素として、職務内容やワークライフバランスはもちろん、収入の面も大きな関心を持つポイントとなります。現在の収入よりも高い報酬を得られる職種や資格には、自然と注目が集まるものです。
公認会計士の資格を持つことは、その高い専門性から、収入の面でも大きなメリットが期待されます。特に、公認会計士試験に挑戦することを検討している方々にとって、この資格を取得することは、収入の向上に大きく寄与する可能性が高いと言えるでしょう。
実際、令和4年(2023年)賃金構造基本統計調査によれば、公認会計士の平均年収は約746.6万円以上と、他の職種と比較しても非常に高いレベルに位置しています。このような高収入が、公認会計士という資格が持つ魅力の一部として、多くの人々に注目されている理由となっているのです。
受験資格の要件がない
公認会計士試験を受験する際、確かに会計や法律のような専門分野の知識の習得は欠かせません。しかし、その挑戦自体には学歴や年齢、性別、国籍といった特定の条件は設けられていません。これは、多様なバックグラウンドを持つ人々が平等に試験に挑むことができるという意味で、非常に公平な資格と言えます。
さらに、試験に合格した後のステップとして、実務の経験を積むことや実務補修の過程を経ることは必須ですが、これはキャリアの発展のための段階として捉えることができます。公認会計士としての活動を続けることで、給与の増加やキャリアの向上が期待されるため、受験資格の制約がないこの資格は、投入した時間や努力が大きな成果として返ってくる可能性が高いのです。このような特性が、公認会計士試験の魅力を一層高めている要因となっています。
働きながら公認会計士を目指すことは可能?
多くの人々が働きながらでも公認会計士を目指すことは可能かという疑問を抱きますが、答えは「可能だが、非常に挑戦的」であるといえるでしょう。
公認会計士試験は、その高い難易度から多くの受験者にとって大きな壁となっています。そのため、フルタイムで働きながらこの試験に合格するためには、時間管理や計画的な学習が不可欠です。
そのため、公認会計士試験の合格者の60%前後は勉強時間を確保し易い学生なのです。合格者の平均年齢についても24.5歳ですので、公認会計士に挑む人の大半が学生であり、20代前半という若手ということからも以下に社会人になってから合格することが難しいのか図りしれます。
日常の業務、家事、育児、そして通勤といった日常のタスクをこなしながら、効果的な学習時間を見つけ出すのは容易ではありません。しかし、その中で継続的に学習を進めることで、知識の定着や理解を深めることができます。公認会計士試験の内容は幅広く、深い専門知識が求められるため、短期間での合格は難しいと言われています。そのため、長期的な視点での学習計画と、それに伴う持続的な努力が必要となります。
必要な勉強時間
公認会計士試験は、多くの国家資格試験の中でも特に難易度が高いとされています。この試験に合格するためには、専門的な知識の習得はもちろん、それを実際の問題に適用する能力も求められます。そのため、合格を目指す受験者は多くの試験勉強時間を費やす必要があります。
一般的に、公認会計士試験の合格者は、試験日までに1,500時間以上、場合によっては2,000時間以上の勉強時間を確保していると言われています。しかし、この時間はあくまで目安であり、個人の学習効率や前提知識、使用する教材や学習方法によって変動します。
例えば、会計や経済の専門学校や大学を卒業した方は、基本的な知識が既に身についているため、必要な勉強時間が短縮される可能性があります。一方で、全くの初学者や他の分野からの転職を考えている方は、基礎から学ぶ必要があるため、より多くの時間を要するでしょう。
また、効率的な学習方法を取り入れることで、必要な勉強時間を短縮することも可能です。模擬試験を繰り返し解くことや、過去問の分析を行うことで、試験の傾向や自身の弱点を把握し、ターゲットを絞った学習を進めることが推奨されます。
最後に、公認会計士試験の勉強はマラソンに似ています。短期間での集中的な学習よりも、長期間にわたる継続的な学習が合格への鍵となるでしょう。毎日の学習習慣を築くことで、確実にステップアップしていくことが可能となります。
効率よく公認会計士を目指す方法
公認会計士試験は挑戦する価値のある難関の資格試験です。年齢、職業などを問わずに受験することができるため、誰でも合格を目指せる試験となっています。直近5年の受験者データを見ても、出願者数は増加しており、令和6年(2024年)も更に受験者数が増える見込みですので、公認会計士の需要も下がることはないでしょう。
就職しながら学習するポイントとしては、受験資格予備校のような試験対策をサポートする環境に身をおいたり、実務経験が試験の勉強に直結するような会計事務所を選ぶことが、効果的な学習アプローチとなるでしょう。
実際に、会計事務所での勤務を選ぶことで、日常の業務が試験対策としての役割を果たすことが期待できます。これは、実務と学習が一体となることで、双方の知識の深化を促進するためです。
このような環境に身を置くことを希望する場合には、会計業界に精通した転職エージェントのアドバイスが非常に役立ちます。例えば、会計求人プラスのような転職支援サービスは、公認会計士の資格を追求する方々のために、試験対策をサポートする企業情報や、資格取得を後押しする制度を持つ企業の詳細を提供しています。会計専門の求人情報を提供するこのようなサービスは、情報の品質や信頼性が高いため、初めての情報収集から具体的な転職活動まで、幅広く活用することがおすすめです。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
投稿者情報

- 税理士や公認会計士、会計業界に関する記事を専門に扱うライター。会計業界での執筆歴は3年。自身でも業界についての勉強を進めながら執筆しているため、初心者の方が良く疑問に思う点についてもわかりやすくお伝えすることができます。特に業界未経験の方に向けた記事を得意としています。
最新の投稿
 公認会計士2025.06.29監査法人の就職は難しい?難易度・就活対策・Big4の特徴を徹底解説
公認会計士2025.06.29監査法人の就職は難しい?難易度・就活対策・Big4の特徴を徹底解説 経理2025.06.24日商簿記2級・3級の正式名称とは?履歴書に記載するポイントを解説
経理2025.06.24日商簿記2級・3級の正式名称とは?履歴書に記載するポイントを解説 税理士試験2025.04.04税理士試験に合格後のキャリアパスとは?選択肢とそれぞれの特徴を解説
税理士試験2025.04.04税理士試験に合格後のキャリアパスとは?選択肢とそれぞれの特徴を解説 転職ハウツー2025.03.12簿記1級を取っても就職できない?「やめとけ」といわれる理由とは?
転職ハウツー2025.03.12簿記1級を取っても就職できない?「やめとけ」といわれる理由とは?