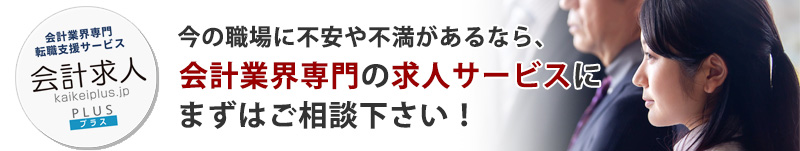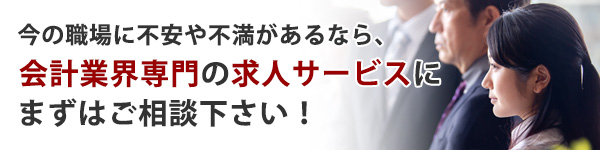公認会計士の仕事はAIによってなくなるはウソ?なくならない理由を解説
公認会計士の仕事がAIにより近い将来にはなくなる流れになっていくという話を聞いたことがありませんか?
超難関国家試験に合格し、実務経験を積むことでやっと公認会計士として登録できるほど、難易度の高い資格である公認会計士、独占業務もありますから高年収が期待できる資格ですが、公認会計士の仕事がなくなるといわれているのはとても気になりますよね。
近年、OpenAIのChatGPTやMicrosoftのCopilotが話題になり、急速に生成AIが日常に浸透してきています。生成AIが今後も進化していくと、多くの仕事はAIが賄ってくれるという時代になることも不可能ではないでしょう。
この記事では、AIによって公認会計士の業務がどのような影響を受け変化していくのか、公認会計士の仕事は将来的に本当になくなってしまうのかについて解説します。
コンテンツ目次
公認会計士の仕事がなくなると言われる背景
2015年12月に発表された野村総合研究所とイギリスのオックスフォード大学による共同研究では、601種の職業についてコンピュータ技術で代替可能かどうかの確率が試算されました。
その結果、日本の労働人口の49%が従事する職業で技術的には人工知能やロボットに代替される可能性が高いことが示されました。そして「会計監査係員」がその対象職種に含まれていたため、「将来、公認会計士の仕事がなくなるのではないか?」と業界に衝撃を与えました。
また1991年に旧ソ連から独立したエストニアでは、eガバメント(電子政府)システムの構築が進行し、政府は口座取引や年金、納税、社会保険などの情報をクラウド上に統合し、99%の行政サービスを電子化しました。その結果、「以前は人の手で行っていた業務が電子化され、税理士や公認会計士の仕事が大幅に減った」というニュースが話題となりました。
こういった背景があり現在でも公認会計士の仕事が将来的にはなくなると言われることがあります。
公認会計士の業務にもAIが導入される可能性は高い
エストニアの税務申告の例を見ると、eガバメントシステムの導入とともに税制が簡素化され、個人の税務申告が自動化されたと言われています。
近年の監査業務では日本においてもチェック作業の割合が増加しています。この膨大なチェック業務だけが注目を浴び、公認会計士の仕事が将来AIに奪われると考えられたのでしょう。
確かに公認会計士の業務にもAIが導入される可能性は高いといえます。また、既に一部の業務ではAIの活用が始まっているとも言える状況になっています・

公認会計士の仕事はなくならない
公認会計士の業務には定型的でないものも含まれます。この章ではAIが代替できる業務とAIが代替できない業務の違いについて説明し、公認会計士の仕事全体がなくなるわけではないことを解説します。
会計業務が完全になくなるということはない
AIが得意とするのは、既定のルールに従い指示された業務を正確に遂行することです。決まった会計処理のルールに従って会計事務を行い、さらにその処理をチェックする作業については、AIが人間の公認会計士よりも得意とする業務内容と言えるでしょう。
しかし、会計処理は経済活動を数字で表すためのものであり、経済活動は常に変化し続けています。そして特に近年の経済活動の変化は目覚ましいものがあります。ビジネスの形態が変わるにつれて、会計処理も変化していかなければなりません。新しい会計処理が求められる場面も出てくるでしょう。
変わり続ける経済に対応するためには、AIではなく人間の公認会計士の判断が不可欠です。
単純な仕訳入力だけを行うような事務員を雇う必要性はなくなる可能性
経理業務においてAIの活用は非常に効果的ですが、「AIが代替できる業務」と「AIが代替できない業務」に大別されます。AIに任せられる一部の業務は自動化が可能で、単純な仕訳入力だけを行うような事務員を雇う必要性はなくなる可能性があります。
ただし「AIが代替できない業務」として、人の手が必要な業務も依然として存在します。全ての経理業務を自動化するのは不可能であるため、どの分野をAIに任せ、どの分野を人が担当するかを明確に区別することが重要です。
例外的な条件判断が求められる専門家としての業務や臨機応変な対応が必要な業務はAIには向いていません。例えば、従業員の税金計算などの複雑な業務は人の判断が不可欠です。
働き方を改善したいなら
「会計求人プラス」
「残業が多い」「テレワーク対応した職場で働きたい」と思っていませんか? 会計事務所・税理士事務所で働き方を変えたいなら、専門の転職・求人サイト「会計求人プラス」がおすすめです。
AIにはできない公認会計士の仕事
公認会計士の業務にはAI化と親和性の高い監査業務だけでなく、税務相談、各種コンサルティング業務、ガバナンス支援などの多岐にわたる仕事が含まれています。つまり、AIが対応できない業務は引き続き公認会計士が担当する必要があり、その領域を中心に活動すれば公認会計士としての役割を果たし続けることができるでしょう。
監査先との対話はAIだけでは出来ない
公認会計士の業務を全面的にAI化することが難しい理由の一つに、クライアントとの直接的なコミュニケーションが欠かせない点が挙げられます。
例えば、適切な監査業務を遂行するためには、監査法人がクライアント企業に対して必要な提出書類を明示する必要があります。これは、監査対象企業が粉飾決算を行っている場合に、自主的に書類を提出することが期待できないからです。
クライアント企業に書類の提出範囲を全て任せてしまうと、適正な監査が行えず、粉飾決算などの問題が発覚した場合には監査法人自体が処分や損害賠償責任を問われるリスクもあります。
そのため公認会計士が適正に業務を遂行するためには、クライアント企業との良好な関係を構築し、現場レベルでの信頼関係を築くことが不可欠です。これは「人対人」の関わり合いを通じて初めて成し得るものであり、AIには代替できない重要な要素です。
取引の妥当性や例外をAIは判断できない
AI技術は事前に定められたルールに従って業務を処理します。そのため、公認会計士業務をAI化するには以下の工程が欠かせません。
- 税務処理ルールや監査規範のシステム化
- 税法改正や制度変更に応じたシステムの更新
- AIの精度向上のための機械学習期間の確保
例えば税法は頻繁に改正されるため、一度確立したAI技術ではすぐに対応できなくなります。そのため適正な税務相談を提供するには、その都度専門知識を利用してAIのシステムを更新する必要があります。
また、取引の妥当性や例外をAIは判断できないという課題もあります。
最終的な判断は人が行う必要がある
公認会計士の業務では、最終的な意思決定は専門資格を持つ公認会計士自身が行います。どれだけAIによって公認会計士業務が効率化されても、公認会計士の存在は不可欠です。
確かに国際会計基準や画一された判例法理は存在します。しかし、個別に聴き取り調査を行い、状況に応じた判断をしなければならない場面は確実に存在します。この段階では、前例や類似案件との比較を通じて、担当者が事案ごとに臨機応変な判断を下す必要があります。
情報を「一定の条件下で処理」するだけであれば、AI技術で代替可能です。しかし、以下の情報については公認会計士による直接の判断が求められることが多いです。
- どの情報を収集するか
- 収集した情報をどの規範に当てはめるか
- 処理後の結果が税制運用上適切であるかどうか
したがって、公認会計士業務においては人が果たすべき役割が広範囲に及ぶと考えられます。
公認会計士の仕事はAIによって楽になる?
AIの進化により公認会計士の仕事がなくなるわけではなく、AIを活用することで業務の効率化を図ることも可能です。
AI技術によって定型業務が自動化できる
監査業務は財務諸表のチェックを行うため、一般事業会社の決算後に実施されます。決算は毎年同じ時期に行われ、そのタイミングで監査も行われます。通常、企業の事業内容が大きく変わることは少なく、決算の内容が大幅に変わらないことも珍しくありません。監査自体は数字の正確性を確認し、特に大きな変動があった部分についてはその理由を裏付ける資料を確認します。
取引はシステムに登録されています。現代では、システム内に資料が添付されており取引が毎期同じものであれば、AIに学習させることで対応可能と考えられるかもしれません。AIは繰り返しの業務に強く、学習によって誤りを発見する可能性も高いです。これらの理由から、AI技術によって定型業務という考えも理解できます。
大手監査法人では積極的にAIを導入
AIが業務を奪う可能性についての懸念は理解できますが、業務の効率性を向上させる観点から考えると、公認会計士業務においてAIの導入は一定の範囲で避けられないと考えられます。
実際、大手監査法人では例えばデロイトトーマツが「Audit × AI」という取り組みを推進し、AIを積極的に導入して次世代型の業務体制を構築しようとしています。
人材リソースに余裕が生まれ、ビジネスの発展を目指せる
AIが定型業務を自動化することで、雇用の機会が減少し失業率が上昇するのではなく、むしろ「人材リソースに余裕」が生まれます。時間にも余裕が生まれるでしょう。
これにより、創造的思考やソーシャルインテリジェンスをさらに活用してビジネスの発展を促進できる可能性が高まります。
過去には、公認会計士のキャリアパスは監査法人での就職から独立開業へという一本道でした。しかし、AIの導入により公認会計士の働き方が多様化することで、一般事業会社内での役職やベンチャー企業での活躍の場が広がります。また、公認会計士自身が新たなビジネスを立ち上げてクリエイティブなサービスを提供することも可能になります。
このように、公認会計士業務にAI技術が導入されることは、業界だけでなく社会全体にとっても大きなメリットをもたらすと考えられます。
AI化の波に流されないためには
今後、公認会計士の仕事が減少する可能性がある中、どのように準備すれば良いのでしょうか。
まず考えるべき点は、自分自身は監査法人での勤務を続けるか、それとも別の道を模索するかです。基本的な課題は、他の公認会計士との差別化や優位性の確保ですが、選択する道によって取るべき戦略は異なります。
監査法人は公認会計士が中心的に活動する場所です。これまでは単に「公認会計士」での差別化は難しい環境でした。
監査法人での差別化を図るためには、例えば海外での勤務経験やUSCPAの保有者が挙げられます。公認会計士は難易度の高い公認会計士試験においてそれなりの高得点を取得し合格しているため、TOEICなどの試験でも勉強を経て高得点を獲得することができる傾向があります。海外駐在は限られた枠ですが、実現すれば他の公認会計士との差別化が可能であり、昇進にもプラスの影響を与えるでしょう。
さらに、監査業務だけでなくコンサルティングファームなどでアドバイザリー業務の経験を積むことも、他の公認会計士との差別化に役立つ手段です。
次に、独立して税理士事務所を開く場合や一般企業に移る場合はどうでしょうか。監査法人を離れる場合は、他の公認会計士と差別化するために独自のスキルを身に付ける必要があります。
ここで重要なのは、複合的なアプローチです。例えば、会計士×IT、会計士×M&Aなど、会計士に別の要素を加えることで他者との差別化を図ることが求められます。
会計知識だけでは他者との差をつけるのは難しいため、何か付加価値を持たせることが重要です。

公認会計士の仕事はAIによって向上すると心得よ
将来、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などのテクノロジーが監査業務や被監査会社の業務に大きな影響を与えると予想されます。ITの知識とスキルがこれまで以上に重要となるでしょう。公認会計士としては、これらのツールを使いこなし、ルーチンな業務を効率的に自動化していくことが求められます。
ポジティブにキャリアプランを作成していくべし
AI技術は驚異的な速さで進化しています。そして、「効率性による収益性の向上」というテーマが公認会計士業界でも重要視されていますが、その過程でAI化の波が押し寄せるでしょう。
しかし、AI化によって公認会計士の仕事が未来に完全になくなるわけではありません。むしろ、「高度な専門性が求められる」という公認会計士業務の特異性が、一定範囲でのAI化を制限する要因となるでしょう。また、従来の業界の枠を超えたビジネスチャンスを見いだす可能性もあります。
公認会計士の将来性を見極め、AIに取って代わることなく業務を進められれば、年収アップも問題ないくらい、公認会計士は魅力がある資格だと言えます。
「AIが進む中で公認会計士の学びは意味がないのか」と不安になり否定的に考えるのではなく、「AIの進展が新たな挑戦を生み出すチャンス」と安心し前向きにとらえて、転職も含め自身のキャリアプランを積極的に進めていきましょう。
公認会計士資格取得を目指した転職なら会計求人プラスで探そう
会計求人プラスは、公認会計士や税理士などの求人情報を取り扱う、会計業界に特化した転職支援サービスです。税理士や会計士志望の方は、会計求人プラスでご自身に合った就職先を探しつつ、試験勉強に臨まれるのがおすすめです。
会計求人プラスは、自分で検索条件を設定し求人情報を検索して転職先を見つけたい、詳細な経歴やスキルを登録して会計事務所などからスカウトを受けるというダイレクトリクルーティングを利用したい人のための求人サイトと、初めての転職活動で不安がある、転職活動に割ける時間が限られているという人のために転職エージェントのキャリアアドバイザーがあなたに適した非公開の求人情報を紹介してくれたり、会計事務所と年収交渉や条件確認など話しにくいことも代行してくれたりします。
会計求人プラスは転職サイトと転職エージェントの2つのサービスであなたの転職活動をサポートします。
働き方を改善したいなら
「会計求人プラス」
「残業が多い」「テレワーク対応した職場で働きたい」と思っていませんか? 会計事務所・税理士事務所で働き方を変えたいなら、専門の転職・求人サイト「会計求人プラス」がおすすめです。
投稿者情報

- 現役公認会計士・税理士
- 公認会計士資格を取得しており、現役で公認会計士として仕事をしています。税理士資格も持っていますので、財務、会計、税務、監査などの専門的な業務経験も豊富にあります。ライターとして5年以上執筆しており、専門的でリアルな内容が好評いただいています。
最新の投稿
 公認会計士試験2025.06.02社会人から公認会計士を目指す!勉強法やメリットを解説
公認会計士試験2025.06.02社会人から公認会計士を目指す!勉強法やメリットを解説 転職ハウツー2025.06.02経営コンサルタントに必要な資格とは?おすすめの資格と必要性を解説
転職ハウツー2025.06.02経営コンサルタントに必要な資格とは?おすすめの資格と必要性を解説 公認会計士2025.02.03会計士にITスキルは必要か?ITを活かした業務とキャリアアップ
公認会計士2025.02.03会計士にITスキルは必要か?ITを活かした業務とキャリアアップ 経理2024.12.23経理の転職で求められる年齢別のスキルとは!20代と30代を比較
経理2024.12.23経理の転職で求められる年齢別のスキルとは!20代と30代を比較