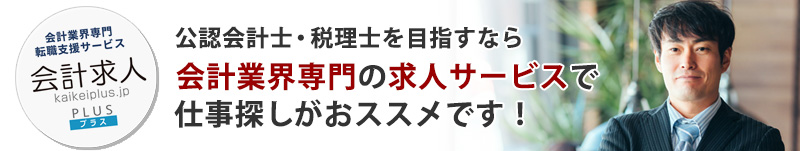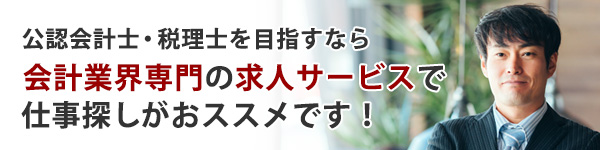税理士を目指すのに簿記1級は必要?試験の概要や税理士試験との関連性を解説
2025/02/10
日商簿記はいくつかの級に区分されており、1級はその最上位に位置します。専門的かつ高度な知識や技能を求められるため、合格するのは容易ではありません。ただし、税理士の税法科目の受験資格を資格試験で満たす場合は1級の取得が必須となります。
本記事では、簿記1級の取得を目指す方や税理士を希望する方に向けて、簿記1級の概要や資格の必要性、税理士試験との関連性、簿記1級に合格するポイントについて解説します。
■□■□会計業界へ効率的に転職活動を進めるなら専門転職サイト「会計求人プラス」が最適!完全無料の会員登録はこちらから■□■□
コンテンツ目次
簿記1級の概要

簿記1級とは、日商簿記検定の最上級資格です。企業の経営活動を記録・計算・整理し、経営成績と財政状態を明らかにする簿記技能の習得度を測ることを目的としています。検定試験は、日本商工会議所および各地商工会議所が実施しており、年間約60万人が受験しています。
日商簿記は原価計算初級・初級・3級・2級・1級の5つのレベルに区分されていますが、最上級に当たる1級は以下2つの水準を求められる高難度の検定試験です。
・極めて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算を習得していること
・会計基準や会計法、財務諸表等規則などの企業会計に関する法規を踏まえ、経営管理や経営分析を行えること
一般企業に勤めるビジネスパーソンであれば2級以下の取得でも十分であることが多いです。一方、公認会計士や税理士といった士業を目指す場合は、簿記1級相当の知識・技能が求められるため、これら士業を目指す方の登竜門として認識されています。
試験科目と合格基準
簿記1級の試験科目は以下4つです。
1.商業簿記
2.会計学
3.工業簿記
4.原価計算
試験時間は、商業簿記と会計学で合わせて90分、工業簿記と原価計算で合わせて90分となっています。合格基準は4科目合わせて70%以上の点数を取れていることですが、なおかつ1科目ごとの得点が40%以上である必要もあります。
つまり、全体で70%以上の正答率をクリアしていても、いずれか1科目の得点が40%を下回っている場合は不合格となってしまうため注意が必要です。
試験日程・受験料・試験会場
簿記1級の試験は、例年6月の第1日曜日、11月の第3日曜日に実施されます。具体的な日時は日本商工会議所の日商簿記公式サイトで公開されているので、事前に確認しておきましょう。受験料は試験日や試験会場にかかわらず、一律税込8,800円です。
なお、簿記1級は団体試験やネット試験の対象外となるため、商工会議所が指定した試験会場(高校や大学、専門学校などの教育施設)での統一試験のみとなります。
合格率
簿記1級の合格率は試験回によってまちまちですが、直近の試験(2024年11月試験)では15.1%でした。
直近10年では、最も高い合格率でも16.8%(2023年11月試験)なので、全体の1割程度と考えておいた方がよいでしょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
日商簿記1級を取得していると活躍できる求人をご紹介!
簿記1級の必要性

簿記1級の合格率は1割程度と狭き門ですが、検定試験に合格した場合、以下のようなメリットを得られます。
税理士試験の受験資格を得られる
税理士試験には、会計学に属する科目と、税法に属する科目の2種類がありますが、後者の場合、一定の受験資格を満たす必要があります。受験資格は学識によるもの、職歴によるもの、資格によるものの3つです。3つのうち、いずれかを満たすことで税理士試験の受験資格を得られます。
学識による受験資格は以下いずれかの条件を満たす必要があります(※)。
● 大学、短大、高等専門学校で社会科学に属する科目を1科目以上履修して卒業した者
● 大学3年次以上で、社会科学に属する科目1科目以上を含む62単位を取得した者
● 一定の専修学校の専門課程を修了した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
● 司法試験の合格者
● 公認会計士試験の短答式試験の合格者
学識による受験資格ですが、大学や短大、高等専門学校、一定の専門学校に通って一定の科目・単位を履修または取得するか、あるいは司法試験や公認会計士試験の短答式試験に合格しなければなりません。
現時点で条件を満たしていない場合、指定の学校に入学し直すか、あるいは難関試験にパスする必要があるため、ハードルがかなり高めです。
また、職歴による受験資格は以下の通りです(※)。
● 法人または事業を行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者
● 銀行、信託会社、保険会社等において貸金の貸付けや運用に関する事務に2年以上従事した者
● 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者
職歴による受験資格についても、特定の職場・業種に2年以上従属しなければならないため、かなりの時間を要します。
その点、資格による受験資格は、簿記1級または全経簿記上級のいずれかに合格するだけでパスできるのが魅力です。
もちろん、それぞれの試験に合格するのは簡単なことではありませんが、ストレートで合格すれば受験資格取得までの時間を短縮できますし、学校に入り直す時間やコストも節約できます。
※参考:国税庁「税理士試験受験資格の概要」(2024-12-20)
職業訓練指導員の試験科目が一部免除される
職業訓練指導員とは、公共職業能力開発施設や認定職業訓練施設などで指導を行う職業のことです。
指導員になるには職業訓練指導員試験に合格する必要がありますが、簿記1級試験に合格している場合、職業能力開発促進法に基づき、事務科の試験科目の一部が免除されます。
大学の推薦入学で有利になる
簿記1級を取得していると、一部大学の推薦入学で有利に働く可能性があります。
優遇内容は大学によって異なりますが、出願資格を獲得できたり、選考時に加点されたりといった恩恵を受けられることが多いです。
昇進や転職に役立つ
すでに社会人として働いている方や転職を考えている方は、簿記1級の資格を保有することで昇進や転職において優位に働く可能性があります。
特に高度な会計処理や連結会計を求められることが多い大企業や、工業簿記と原価計算のスキルが重宝されるメーカーへの転職では有利に働くでしょう。
税理士と簿記1級の関連性
前項では簿記1級を取得する必要性やメリットについて説明しましたが、中でも税理士を目指す方にとって、簿記1級の検定合格は特別な意味を持ちます。なぜなら、税理士試験の試験科目の一つである簿記論と、簿記1級の試験内容の一部が重複しているためです。
税理士試験の簿記論の出題範囲は、複式簿記の原理、その記帳・計算および帳簿組織、商業簿記、工業簿記です。一方、簿記1級の試験範囲は商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の4つです。
上記を比較してみると分かる通り、簿記1級で学んだ知識はそのまま税理士試験の簿記論を受ける際にも役立てられることが分かります。
もちろん、実際に出題される問題は税理士試験と簿記1級で異なるでしょう。しかし、全く出題範囲が異なる2つの試験の勉強を並行して行うケースに比べると、勉強時間を大幅に短縮できるでしょう。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
日商簿記1級を取得していると活躍できる求人をご紹介!
簿記1級の勉強方法
簿記1級は2級以下の試験よりも出題範囲が広く、より高度な知識や技能を求められます。合格率が全体の1割程度にしか満たないことも試験難度の高さを証明しており、ポイントを抑えて勉強しないと短期間での合格は難しいと言われています。
なるべく最短での合格を目指せるよう、以下のポイントを押さえて試験勉強に取り組みましょう。
試験科目の特性を理解する
簿記1級の試験科目は、商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算の4つですが、それぞれ特徴が大きく異なります。
それぞれの特性や出題傾向を把握した上で勉強に着手すれば、勉強効率がアップし、より短期間での合格を目指すことが可能です。
ここでは試験科目ごとの特性について解説します。
商業簿記
商業簿記は、購買活動や販売活動といった企業外部との取引を記録・計算するための技能です。経営管理者や取引先、出資者などに対して適切かつ正確な報告を行えるかどうかの知識・技能を問われます。
具体的には、収益認識や売価還元法に関する知識を問う問題や、個別財務諸表、連結財務諸表の作成問題などです。会計処理そのものに対する理解度や、会計処理が連結財務諸表におよぼす影響への理解を問う内容になっています。
基本的には資料の内容をきちんと読み取り、正しく集計する能力が試されますが、出題範囲が広範囲に及ぶので、さまざまなパターンを想定して問題練習を解くことが重要なポイントです。
会計学
会計学は、企業経営に必要なお金の計算方法や、キャッシュフローの評価、今後の予算の組み方などに関する科目です。
財務諸表の作成問題の出題が多い商業簿記とは異なり、会計学では空欄の補充あるいは正誤判定による理論問題や、個別の計算問題が多く出題されることが特徴です。空欄補充や正誤判定なら暗記で十分と思われるかもしれませんが、実際には理論をきちんと理解しておかないと解けない問題が多く出題されます。基本からしっかり押さえておきましょう。
難しいと思ったら、まず計算問題を解き、その計算の元になる理論を学ぶと理解しやすくなるかもしれません。
工業簿記
工業簿記は、部門別・製品別の材料・燃料・人材などの資源の投入について記録・計算に関する科目です。
主に製造業を対象としており、試験では製造業の生産活動に関する会計処理や原価計算の複雑性、製造プロセスの理解力などを問うために、原価計算方法の選択、製品別の原価計算、製造原価報告書の作成などの問題が出題されます。
計算パターンをただ覚えるだけでなく、一つ一つの問題や解説を熟読し、理解を深めていくことが重要です。
原価計算
原価計算は、製品を製造するのに費やす原価の計算に関する科目です。
試験では設備投資や業務的な意思決定に関する問題、予算実績差異分析、CVP分析といった分析系の問題が出題される傾向にあります。
複数の資料を正しく読み取って回答する必要がありますが、読み取りの段階でつまずくと、その後の一切が誤った方向に進んでしまうので、資料やデータを正確に読み取る練習を行っておくことが大切です。
勉強スケジュールを組む
目標や計画を立てないとだらだらと勉強してしまいがちなので、初めに勉強スケジュールを組んでおくことをおすすめします。
試験本番3カ月前までは、テキストの読み込みと問題集を一通りこなしておき、それ以降は過去問を中心とした問題集にひたすら取り組んでいくのが一般的です。
試験日が迫ってきたら、応用問題よりも基礎のおさらいをしておいた方が効果的でしょう。
勉強仲間を作る
簿記1級の取得には、一般的に400~1,000時間程度の勉強が必要とされています。
それだけの長い時間、モチベーションを維持しながら勉強するのは簡単なことではありません。お互い励まし合い、切磋琢磨するためにも、同じ簿記1級の取得を目指す勉強仲間を作ることをおすすめします。
勉強仲間がいれば、簿記1級に関する情報を共有したり、分からないところを教え合ったりすることもできるので、一人で勉強するより勉強効率が上がるかもしれません。簿記1級取得の目的が税理士になることであれば、税理士試験の情報共有もできるでしょう。
簿記1級は税理士を目指す人の登竜門
簿記1級は極めて高度な商業簿記や会計学、工業簿記、原価計算を習得していることが求められる資格試験です。
簿記1級に合格すると税理士試験の受験資格を得られる上、税理士試験と出題範囲が一部重複している分、勉強時間の短縮にもつながります。実際、簿記1級は税理士や公認会計士などを目指す人の登竜門としても知られている資格試験なので、税理士を目指す方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
会計求人プラスは、会計士・税理士事務所専門の求人・転職サイトとして、より業界に特化した求人探しをサポートします。税理士・会計士業界特有の項目で求人を検索できるのはもちろん、専門のエージェントが就職・転職活動をフォローしてくれるので、希望する職場がスムーズに見つかります。
登録や利用は完全無料なので、晴れて税理士の資格を取得した際は、ぜひ会計求人プラスのサービスをご利用ください。
目指して求人を探すなら
「会計求人プラス」
公認会計士や税理士を目指すなら、実務経験を積みながら資格取得も目指せる事が理想です。会計業界に特化した求人サイト「会計求人プラス」ならそんな職場も探せます!
日商簿記1級を取得していると活躍できる求人をご紹介!
投稿者情報

-
会計事務所や税理士事務所、一般企業の経理職など会計業界の求人情報が豊富な「会計求人プラス」を運営し、多くの求職者の方、会計事務所の採用ご担当者とお話をさせていただいています転職エージェントです。
異業種から会計業界へ転職を希望している方をはじめ、これから税理士や公認会計士を目指す未経験の方や、今までの税務・会計の知識・経験を活かして年収アップやスキルアップしたい方などを全力で支援しています。
その一環として、会計業界でお役に立つ情報をお届けするために10年以上記事を書いています。是非、会計業界で働く人が楽しく、知識を得られるような情報をお伝えできればと思います。
最新の投稿
 税理士2025.04.24女性税理士の平均年収を徹底解説!なぜ税理士は男女で給与が違うのか?
税理士2025.04.24女性税理士の平均年収を徹底解説!なぜ税理士は男女で給与が違うのか? 転職ハウツー2025.04.04税理士補助の志望動機はどう書く?未経験者向けのポイントや成功事例を解説
転職ハウツー2025.04.04税理士補助の志望動機はどう書く?未経験者向けのポイントや成功事例を解説 税理士の仕事2025.04.0430代・職歴なしから税理士を目指すには?未経験からの資格取得と就職成功のポイントを解説
税理士の仕事2025.04.0430代・職歴なしから税理士を目指すには?未経験からの資格取得と就職成功のポイントを解説 成功者インタビュー2025.02.21エクセライク会計事務所 成功者インタビュー 2025年度
成功者インタビュー2025.02.21エクセライク会計事務所 成功者インタビュー 2025年度